農業用水施設とその公益的機能の非農家世帯による認識
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
混住化に伴って農業用水施設の農業以外の役割が次第に大きくなっている。農業用水施設に対する非農家世帯の意識を定量的に明らかにして、施設管理への非農家住民参加とそのPRの必要性を示した。
- 担当:農業工学研究所・農村整備部・施設管理システム研究所
- 代表連絡先:0298-38-7666
- 部会名:農業工学
- 専門:農村計画・基幹施設
- 対象:計画・設計技術
- 分類:研究・行政
背景
農業用水施設は、農業生産に必要な灌漑用水の安定的供給のほかにも、用水が農業集落を流下する途中で、防火用水や生活用水として利用されることを可能にしてきた。また、居住者や来訪者に水辺の親水空間を提供したり、伝統的な農村景観の重要な構成要素としても重要な役割を果たしてきた。しかし、農業用水施設が農家や土地改良区によって管理されてきたため、非農家住民には、こうした施設の役割や土地改良区の存在が必ずしも十分理解されていない。
そのため、土地改良区及び非農家世帯を対象とした農業用水施設の管理に関するアンケート調査結果を分析することにより、農業用水施設に対する非農家世帯の意識を定量的に明らかにする。
成果の内容・特徴
- 土地改良区の管内に居住する非農家世帯を対象としたアンケート調査結果(農林水産省統計情報部、1999.3実施、6,421世帯対象)の分析では、農業用水施設の農業以外の役割として、回答者の76.1%が「雨水・生活用雑排水の排水」を指摘したほか、「防火用水や消・流雪用水」(45.0%)、「親水公園など憩いの場」(11.1%)の役割が指摘された。後2者は地域類型による差があるが、前者は地域類型を問わず高い割合であった。
- 土地改良区を対象とした用排水施設の利用実態は、非農業利用が経年的に増加していることを裏付けている(図1)。
- 維持管理費の公的負担については、一部を助成する市町村が61.5%(1992年)から72.9%(1997年)と漸増しているものの、土地改良費と水利費の農業所得に占める割合も5.8%(1990年)から7.1%(1997年)に上昇しており、公的支援が農家世帯の負担を軽減するには至っていない。
- 全国の農業集落における農家世帯の割合は、1970年の45.7%から1990年には15.7%へと約1/3に減少しており、農家世帯のみでの施設管理が困難になりつつある。
- 非農家世帯が期待する農業用水施設の農業以外の役割は、防火用水など安全性に関する項目が公園機能に関する項目を上回った(図2)。
- 非農家住民の土地改良区に対する認知度は低いが、比較的多くの世帯に農業用水施設が認知されていること、居住年数とともに農業用水施設の管理への参加経験が増加している実態から、新規転入者に対する農業用水施設の維持管理参加のPRの必要性が指摘された(図3、図4)。
成果の活用面・留意点
- 今後の農業用水施設の維持管理のあり方や土地改良区における施設管理運営を検討する際に有効な参考知見として活用できる。
- 農業用水施設の維持管理への参加形態は、多様であるため、非農家世帯の参加を呼びかける具体的手順については、地域の慣行にも配慮する必要がある。
- 維持管理への参加呼びかけに際しては、参加者の年齢や習熟度に配慮し、事故のないように充分留意する必要がある。
具体的データ
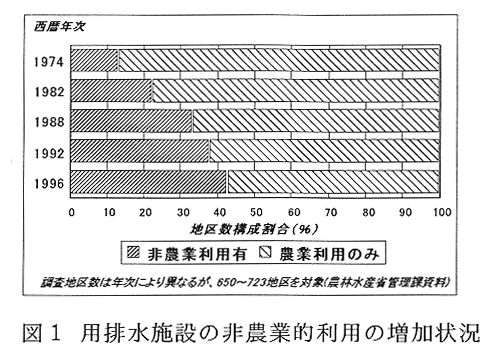
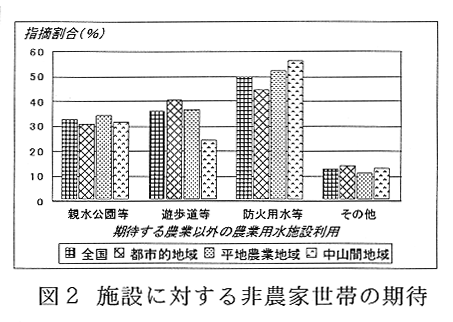

その他
- 研究課題名:基幹水利施設の管理に必要な基盤的情報の解明とその活用による施設診断・評価手法の開発
- 予算区分:経常・依頼
- 研究期間:平成12年度(平成10~12年)
- 研究担当者:石田憲治、吉村亜希子、渡嘉敷勝
- 発表論文等:1)石田憲治、社会的要請の変化と土地改良区機能の拡充、農業土木学会誌、68(11)、9-12、2000.
