地域用水利用の内容分類と洗い場の適正水深
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
農業用水は灌漑用水のほか、洗い物や防火用水などの生活用水として利用さ れてきた。農村集落の地域用水利用者に対するアンケート調査結果の分析により、接 触型と非接触型に分類した場合の利用内容別減少傾向と利用者からみた洗い場の適正 水深を定量的に明らかにした。
- 担当:農業工学研究所・農村整備部・施設管理システム研究室
- 代表連絡先:0298-38-7666
- 部会名:農業工学
- 専門:農村計画・基幹施設
- 対象:計画・設計技術
- 分類研究・行政:
背景
農業用水の炊事や飲用等での生活用水利用は、衛生上の問題もあり上水道の普及とともに減少している。しかしながら、地域によっては活発な農業用水の地域用水利用も存在しており、防火用水や消・流雪用水など保安や景観形成などの観点からも重要性が指摘されている。
そのため、地域用水利用を内容別に分類して利用が存続している内容を明らかにするとともに、利用者からみた適正水深を定量的に明らかにした。
成果の内容・特徴
- 既往の調査結果を分析すると、全国的な地域用水利用の増減傾向は利用内容によって多様であり、飲用水・食器洗い、風呂水・洗濯水としての利用は激減しているが、防火用水、農機具洗いなどの利用は5~10倍(土地改良区を対象とした回答件数)に増加しており、農業集落における地域用水需要は減少していない。
- 事例地区の地域用水の過去と現在の利用実態を比較すると、水遊び、食器や野菜洗い、洗濯など口にしたり身体が直接水に触れる「接触型」の利用内容は激減しているが、消・流雪や農機具洗い等の「非接触型」の利用の減少程度は小さい(図1)。
- 洗い場利用の中止理由では、接触型の利用内容では「水質の悪化」や「衛生上の問題」の指摘が多いが、非接触型の利用内容では、「水量不足」や「洗い場消失」が占める割合が高い(図2)。
- 接触型利用の減少理由が衛生上の問題を主としていることから、その歯止めは水質条件の制約からも困難であるが、非接触型利用が存続している現時点での非灌漑期の水量確保と施設整備による地域用水利用の保全が重要であることが指摘される。
- 全国4地区の洗い場利用に関するアンケート調査項目の分析結果からは、利用者にとって利用しやすい洗い場の水深が30~40cmであることが明らかになった(図3)。
成果の活用面・留意点
- この成果は、農業用水の地域用水機能を増進するための水路施設の更新・整備に際して有効な知見として活用できる。
- 農村集落を流れる農業用水路の更新に際しては、アンケート調査等により利用の存続が期待される利用内容を把握して対策を講じる必要がある。
- ここで得た洗い場の適正水深は幅をもった値であり、また、農村集落内の用水路(水路幅1~2m、灌漑期最大流量0.3~1.5m3/sec程度)を対象とした利用者による評価であり、水路断面構造や流量など水理上の制約条件にも配慮する必要がある。
具体的データ
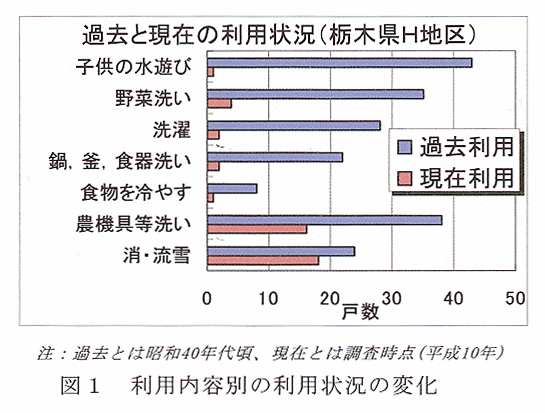

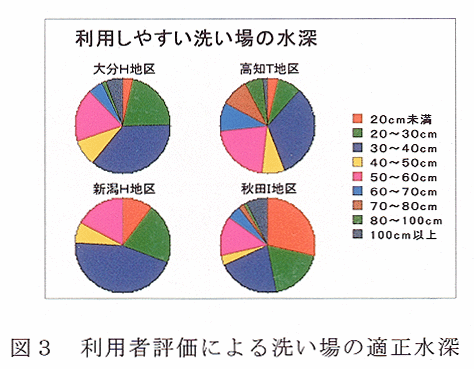
その他
- 研究課題名:灌漑用水と調和した地域用水の最適水利用期別パターンの解明
- 予算区分:行政対応特研[多目的水利用]
- 研究期間:平成12年度(平成9~12年)
- 研究担当者:石田憲治、渡嘉敷勝、吉村亜希子
- 発表論文等:1)石田憲治ら、住民アンケート調査にもとづく農業用水の生活用水利用の実態、平成10年度農土学会大会講演要旨集、764-765、1998.
2)渡嘉敷勝ら、地域用水の取水量及び環流量について-地域用水の実態解明における事例研究-、平成10年度農土学会大会講演要旨集、762-763、1998.
3)渡嘉敷勝ら、農業用水の水質が地域用水利用に及ぼす影響?平成10年度農土学会関東支部大会講演要旨集、5-7、1998.
4)渡嘉敷勝ら、農業用水の地域用水利用に関する住民意識、平成11年度農土学会大会講演要旨集、458-459、1999.
