琵琶湖周辺のR地区における用排水管理が下流の水質に与える影響
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
水田域における用排水管理と水質の関連について琵琶湖周辺のR地区における実測データを分析し、複数の取水源を有する広域水利ブロックの水質保全・浄化機能について検証した。
- 担当:農業工学研究所・水工部・水環境保全研究室
- 代表連絡先:0298-38-7545
- 部会名:農業工学
- 専門:基幹施設
- 対象:計画・設計技術
- 分類:行政
背景
水田の持つ水質保全・浄化機能については既に多くの報告がなされているが、農業水利システムを通じた用排水管理に伴う広域水利ブロックでの水質動向についての研究は少ない。そこで、複数の取水源を有する琵琶湖周辺のR地区における面的な広がりを持った水利用と、循環的な水利用に着目し、施設形態、水管理形態、水需給構造などが下流の公共水域の水質にどのような影響を与えるかということを調査・分析することにより、複数の取水源を有する広域水利ブロックの水質保全・浄化機能について検証した。
成果の内容・特徴
- 図1は水移動からみた農地の物質収支の概念図であり、農地から排出される汚濁負荷量は上流からの流入負荷量と下流への排出負荷量の差である差し引き排出負荷量(L)で評価する必要がある。
L=地表排出負荷量+浸透排出負荷量-用水負荷量-降水負荷量
また、十分広域で平坦な広域水利ブロックにおける浸透水は、下流排水路に流出すると考えれば差し引き排出負荷量は、図2において四角形A'B'C'D'とABCDの面積の差に相当することになる。 - 図3は図4のような水利系統を有し、湖水と河川から用水供給されるR地区でのM頭首工取水地点の河川水質濃度(用水A)、湖水の用水濃度、地区内下流S排水路の水質濃度(用水B)、本川下流F地点の水質濃度(T-N)の時系列変化を示したものである。用水Aよりも用水Bの濃度が低い浄化型の時期があること、M頭首工及びS排水路(水田排水+生活雑排水等)の水質濃度は、湖水よりも高い時期が多いことが判明した。
- 以上のことから、R地区のように複数の取水源を有し、かつ取水量・取水期間の自由度が高い地区においては、より濃度が高い河川水のかんがい面積を増やし、濃度の低い湖水等からの取水量を減らすといった水管理をすることにより、下流域への流出負荷量が減少し、公共水域の水質環境に好影響を与えるとともに、湖水等の富栄養化に対し抑制側に機能する可能性があることを示している。
成果の活用面・留意点
複数の取水源を持ち、かつ水利権の自由度が高い用水地区においては、農業水利システムにおける用排水管理を通じて、農業地域内のみならず下流公共水域の水質保全に貢献する水管理技術の高度化及び水質保全型水利事業の調査・計画の立案に寄与できる。
具体的データ
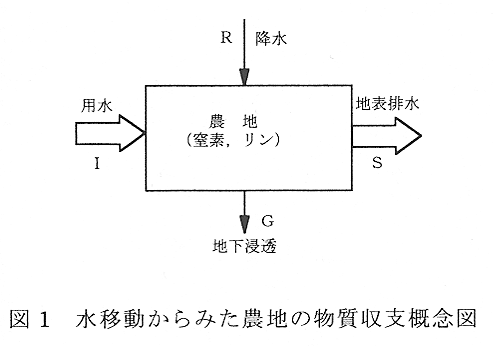
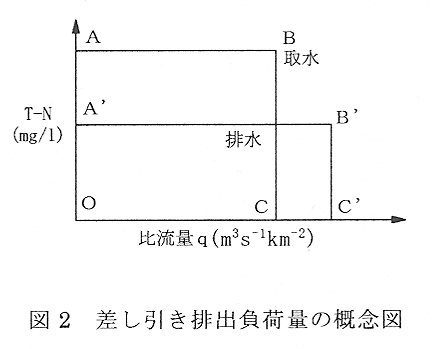
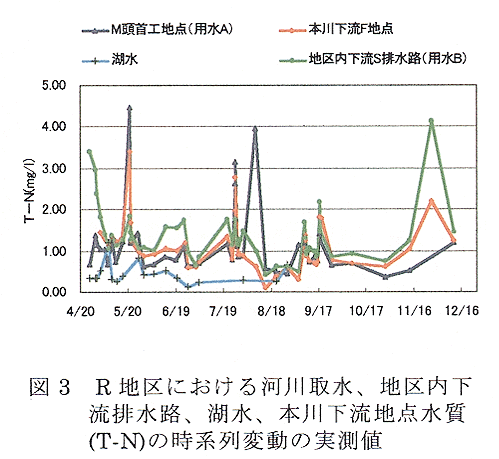
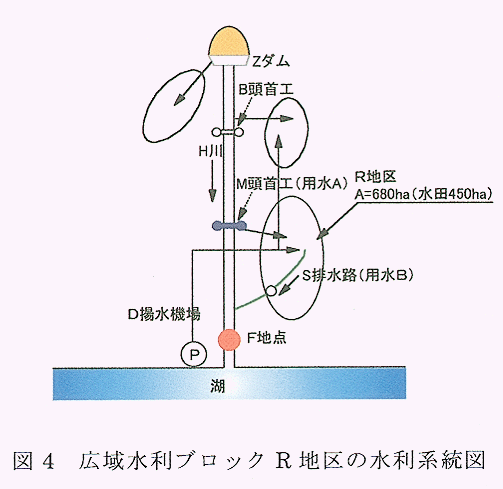
その他
- 研究課題名:農地に対する用排水管理が下流の水質に与える影響の評価
- 予算区分:環境研究(貿易と環境)
- 研究期間:平成12年度(平成8~12年)
- 研究担当者:長谷部 均、白谷栄作、吉永育生、(高橋順二)
- 発表論文等:1)高橋順二・白谷栄作・吉永育生:水田地帯の物質循環を考慮した水資源の量的・質的管理について、農業工学研究所技報、第196号、pp.1-13、1998
2)高橋順二・白谷栄作・吉永育生・森嶋利和:農業水利システムを活用した流域管理、農業土木学会誌、66(12)、pp.13-18、1998
