印旛沼流域農林地が有していた洪水緩和機能の評価
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
急速な都市化が進展する利根川下流域印旛沼流域について、昭和44年~平成9年までの約30年間に発生した41洪水の降水量と沼の最高水位の関係を分析し、流域農林地の減少(都市化)と洪水流出特性の変化の関連から表題の機能を統計的に評価した。
- 担当:農業工学研究所・水工部・河海工水理研究室
- 代表連絡先:0298-38-7567
- 部会名:農業工学
- 専門:資源利用
- 対象:維持・管理技術
- 分類:行政
背景
農林地が有する洪水緩和機能を評価するため、流域の都市化が進行している印旛沼流域について、印旛沼開発事業が終了した1969年以降30年間に発生した41豪雨時の印旛沼出水特性を10年単位に分けて分析する。農林地の減少(流域の都市化)と印旛沼の洪水位の増加量の関連を分析するに当たり、ピーク水位増加量を印旛沼流域農林地の減少によるものと考え、その値を農林地の洪水緩和機能と定義し、1haの農林地の有していた洪水緩和量を評価する。
成果の内容・特徴
- 1969~1997年の29年間に100mm以上の連続降雨は41件発生した。発生度数はA期(1969~1978年)15件、B期(1979~1988年)12件、C期(1989~1997年)14件と期別の発生頻度にあまり差がない。一方印旛沼水位が最も高くなった上位10洪水の発生頻度は、A期1件に対し、B期は5件、C期は4件と流域の宅地化が進んだB、C期の洪水頻度が増加している( 表1)。
- 100mm以上の連続降雨41件とそれに伴う印旛沼の最高水位の関係について、10年別に回帰式を求め比較するとA期に比べ、B期及びC期の最高水位は増大している(図1)。A期とC期の回帰式の比較から、洪水計画雨量278mmの場合、沼の最高水位は202mm増加(洪水量にして265万m3の増加)した計算になる。これを農林地面積(水田、畑、山林)の減少によるもの考えると農林地1haの減少は360m3の洪水量増大をもたらしたことになる。つまり農林地が有する洪水緩和量は水深換算で36mmと算定される。
- 印旛沼流域では1969年~1991年の22年間で、流域面積54,000haの15%に相当する8,100haの農林地が宅地等に変化した。図2に1976年~1989年の13年間の都市化の比率を排水ブロック別に示す。
- 1971年9月の台風25号(A期)による豪雨221mmと1991年9月の台風18号によるによる豪雨214mmで発生した印旛沼の最高水位は前者で、YP3.57mに対し、後者ではYP3.77mと約20cm高くなっている(図3)。
成果の活用面・留意点
洪水流出特性の変動要因は土地利用変化だけでなく、流入河川の改修による変化も要因と考えられる。分析では土地利用変化の要因について検討したことに留意する必要がある。
具体的データ
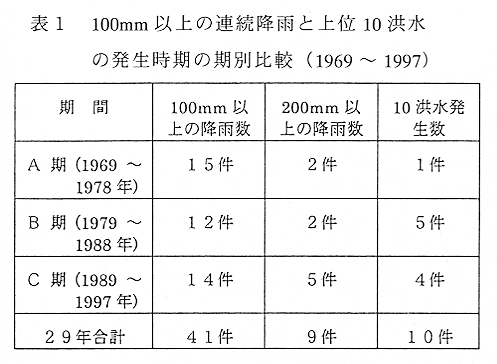
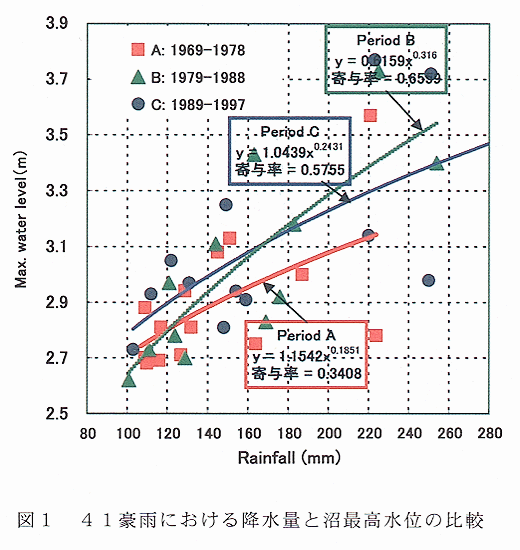
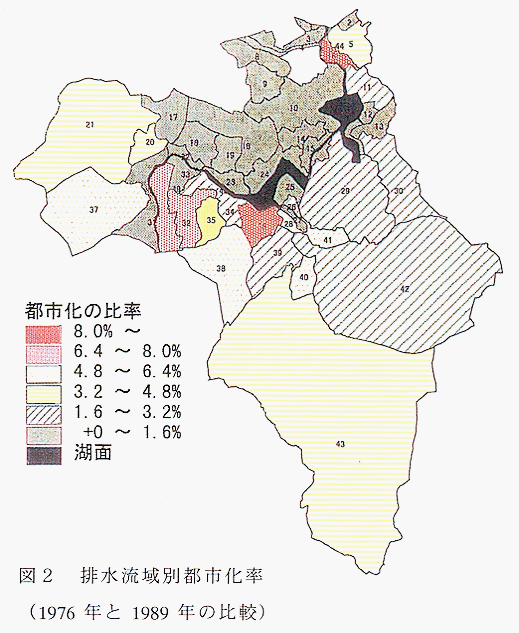
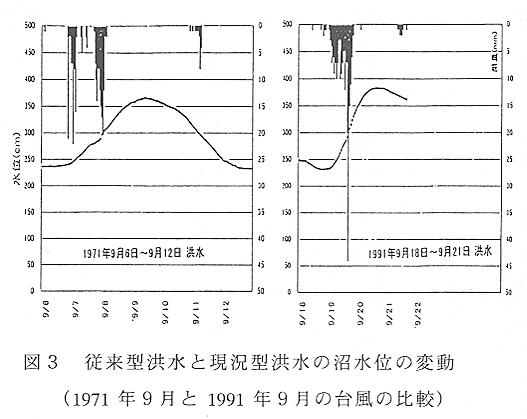
その他
- 研究課題名:都市近郊低平農地の洪水防止機能の評価
- 予算区分:環境研究(貿易と環境)
- 研究期間:平成12年度(平成8~12年)
- 研究担当者:藤井秀人、桐 博英、中矢哲郎
- 発表論文等:1) Fujii,H.,Kiri,H. and Nakaya,T.:Change of characteristics by the decrease of agricultural and forest land in suburban low land, Journal of Rainwater Catchment systems,Vol.6(1),2000(投稿中)
2)藤井秀人・桐 博英・中矢哲郎:都市近郊農林地が有する洪水緩和機能の評価-印旛沼 流域の都市化による洪水位の変化-,農工研技報199,2001
3)藤井秀人・桐 博英・中矢哲郎::都市近郊農林地の洪水緩和機能の評価,平成11年度農土学会大会講演要旨集,118-119,1999
