電熱式温度検層による深部水みちの検出法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ボーリング孔を使って地下の水みちの深度を調べる温度検層において、電熱を用いると均一に加温することができ、試験が容易になる。複数の温度センサーを用いて引上げ・下降の往復測定を行った深度別平均温度を使うと、温度分布測定の同時性を高めることができる。
- 担当:農業工学研究所・造構部・構造研究室
- 代表連絡先:029-838-7576
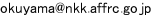
- 区分:技術及び行政
- 分類:参考
背景
大規模地すべりブロックでは、水みちが地下数十mまで分布している場合がある。地上調査ではわからない深部の水みちの深度、流動状況を、ボーリング孔中に下ろした電熱線によってわずかに昇温させた後の温度回復によって簡易に調べる方法を開発した。
成果の内容・特徴
- ボーリング孔を利用して地下水の流動状況を調べる方法としては、孔内に塩などを溶かして孔内水の電導度を変化させたり、温水を注入して温度を変えた後の回復状況を調べる方法が行われている。しかし、細く深いボーリング孔内を均一に変化させるには相当の熟練を要し、注水によって帯水層間の水頭のバランスを変えてしまう可能性がある。本方法は電熱によって均一に加温させるので、失敗が少ない。
- ヒーターには被覆電線(ベル線など)を用い、鉛蓄電池や発電機を電源とする(図1)。内径4cm、深さ40mのボーリング孔で540Wの発熱をさせると、20分間で約3°C昇温させることができる。白金測温抵抗体などの温度センサーによって分解能0.01°Cで温度測定を行えば、温度変化を精密に捉えることができる。
- 1本の温度センサーで深いボーリング孔の深度別温度測定を行うと、時間がかかって、同時刻の温度分布を得ることができない。図2のように、数本の温度センサーで5m程度ずつの区間毎に0.5m間隔の測定を行い、引上げと下降の往復を1セットとして同一深度の平均値をとると、温度分布の同時性を高め、測定時間を短縮できる。
- 大規模地すべりブロックで実施したところ、図3のように浅部の風化岩や崩積土層内、基盤との境界の想定すべり面に複数の水みちがあることがわかった。削孔時に行われた塩を用いた地下水検層よりも小さな水みちを検出することができた。複数のボーリング孔での調査によって図4のような断面図を作成できる。
- 砂模型実験の結果によると、内径4cm、側面開孔率が0.5%のケーシングパイプでは、流速がおよそ10-2cm/s以上の水みちを検出することができる。
成果の活用面・留意点
開孔率が0.5%程度の有孔ケーシングをもつ一般的な調査用ボーリング孔には本方法は適用できるが、開孔率を確認しておくことが望ましい。
具体的データ

図1 バッテリー加温による試験の状況
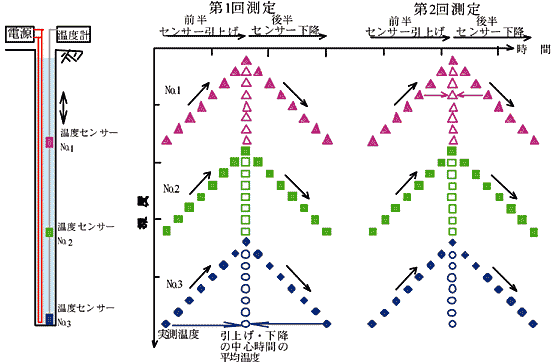
図2 少数の温度センサーで全深度の測定を行う方法
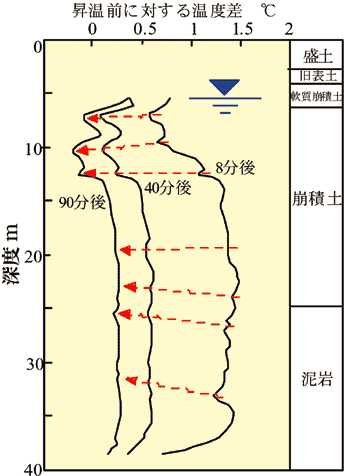
図3 図4のボーリング孔Aにおける試験結果。矢印が流動部
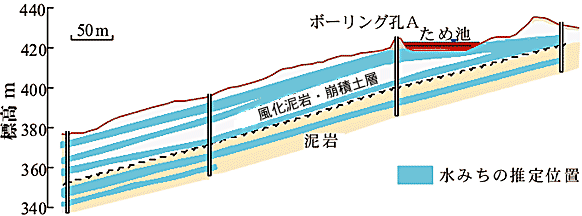
図4 地すべりブロックの推定水みち断面図
その他
- 研究課題名:地すべり地冠頭部凹地の浸透抑制工法に関する事例的検討
- 中期計画大課題名:農地地すべりの機構解明のための地表・地中センシング手法及び冠頭部浸透抑制工法の開発
- 予算区分:交付金研究
- 研究期間:2000~2002年度
- 研究担当者:奥山武彦、黒田清一郎、中里裕臣、長束 勇
- 発表論文等:奥山武彦・黒田清一郎・中里裕臣・長束 勇、地すべりブロック内におけるため池の浸透防止工による地下水流動の変化、農業工学研究所技報、201
