シラス台地の不圧帯水層に形成される水温・水質境界
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
農業系負荷により汚濁が進んでいるシラス台地の不圧地下水帯において、水温・水質境界の存在を明らかにした。この境界の深さは地下水涵養速度と高い相関が見られる。
- 担当:農業工学研究所・地域資源部・水文水資源研究室
- 代表連絡先:029-838-7538
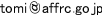
- 区分:研究
- 分類:参考
背景
農村地域では、農業系負荷排出の増大に伴って水資源の水質悪化が顕在化している。ここでは、畜産や茶畑が多く単位面積当たりの農業系窒素負荷が大きい南九州のシラス台地流域を対象として、水資源の賦存状況を量と質の両面から検討を行った。特に、代表的な地質構造を持つ台地中央部に設けた観測井において地下水位と地下水中の水温および水質の鉛直分布を定期的に観測して、不圧地下水帯の成層状況と地下水涵養速度との関係について検討を行った。
成果の内容・特徴
- 農業系窒素負荷により汚濁の進んだ畑流域の水文観測から、深い不圧地下水を持つシラス台地において地下水の水温・水質境界の存在を明らかにした。観測井(W-1)は笠野原台地中央部にあり、境界位置の標高はT.P.25m前後(GL-56m)に存在する。また、第一帯水層は、上方の約半分を占めるシラス層(入戸火砕流堆積物、透水係数K=10-3cm/s)とその下方の軽石層(大隅降下軽石、K=10-1-100cm/s)で構成され、軽石層直下の粘土層(祓川粘土層)によって不透水層が形成されている(図1左)。
- 境界における水温差は0.5°C、水質は電気伝導度の差で11mS/mであり(図1右)、境界は、観測期間を通じて明瞭に存在した。上層水の硝酸性窒素濃度は0.3-1.5mg/l、下層水の硝酸性窒素濃度は11mg/l程度であり、下層は窒素負荷による汚濁が進んでいる。
- 月降水量と地下水位変化量の対比から、多雨時期の浸透水が台地部の地下水面に達するまで、W-1(GL-44m)で4ヶ月、W-2(GL-60m、W-1の北東3.3km)で2~7ヶ月、W-3(GL-65m、W-1の北3.7km)で6~7ヶ月を要した。これより不飽和水帯におけるみかけの降下浸透速度は4×10-4cm/sと推定された。
- 観測された境界は、シラス層と軽石層の境界付近に存在するが、その位置は観測期間内で2m程度移動した。一方で、地下水位の変動と降水量の関係から多段タンクモデルにより地下水涵養速度の推定を行うと(図2)、地下水涵養速度と境界の位置に高い相関が見られた(図3)。これらの結果から境界の位置には、上層への地下水涵養により下層水を押し下げる作用が働いているものと考えられる。
成果の活用面・留意点
ここで得られた成果は、観測井における観測結果より得られたものである。
具体的データ
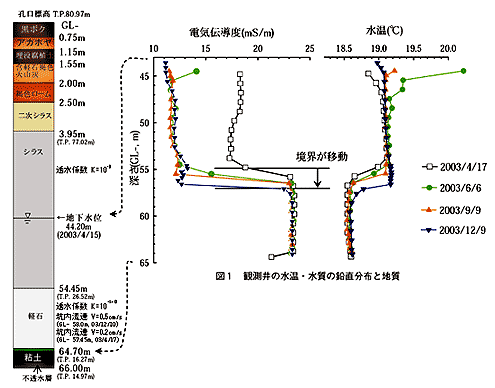
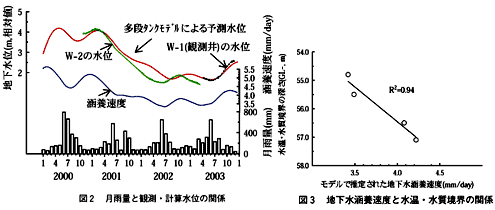
その他
- 研究課題名:シラス台地流域における水資源の量及び質の動的解析
- 関連する中期計画大課題名:水利調整と用水再編手法の開発及び利用構造の解明
- 予算区分:交付金研究
- 研究期間:2001~2003年度
- 研究担当者:久保田富次郎、増本隆夫、松田 周
- 発表論文等:1) 久保田富次郎・増本隆夫・松田周・森田重則・古江広治・松元順、笠野原台地における水文観測とモデル解析、応用水文、15、21-27、2002.
2) 久保田富次郎・増本隆夫・松田周、二層系帯水層を有するシラス台地地下水の動態、地球惑星科学関連学会合同大会予稿集(CD-ROM)、2004.
