木曽川から濃尾平野への地下水誘発涵養現象の推定方法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
木曽川から濃尾平野への地下水誘発涵養の発生時期と涵養量は,水理地質構造から推定される誘発涵養地点の上下流2観測所の流量変化から計算できる。1975年から1993年の間の年間平均誘発涵養量は,3.4億m3/年である。涵養地点に最も近い江南市の地下水位は,誘発涵養が生ずると上昇する。
- キーワード:補給涵養,誘発涵養、濃尾平野,木曽川
- 担当:農工研・農地水資源部・地下水資源研究室
- 連絡先:電話029-838-7200、電子メールimaizuma@affrc.go.jp
- 区分:農村工学
- 分類:研究 普及
背景・ねらい
深層地下水の揚水より被圧水頭が低下すると,これを補うように水平方向からの涵養が増加する(水平補給涵養)。帯水層の付近に河川があると河川水が帯水層へと引きずり込まれる(誘発涵養)。さらに,被圧水頭が低下すると,補給漏水や難透水層からの絞りだし涵養など補給涵養が発生し,地盤沈下が生じる。補給涵養の一部には水田の灌漑水も寄与していたと考えられる。誘発涵養の実態を明らかにすることは水田の地下水涵養機能を評価するために重要である。これまで,誘発涵養の研究は水収支数値シミュレーションでの仮想の数値として取り扱われており,その実態を明らかにした例は少ない。木曽川から濃尾平野への誘発涵養の発生を,木曽川の2観測所の流量変化から推定し,その影響が地下水位変化に表れていることを確認した。誘発涵養は濃尾平野のみならず日本の海岸平野や扇状地で一般的な現象であり,ここで示した方法は,これらの地域でも有効である。
成果の内容・特徴
- 濃尾平野の帯水層は,埋没谷に堆積した氷期の砂礫層で, ボーリングデータからG1層,G2層,G3層に区別されている(東海三重県地盤沈下調査会編,1985)。図1にG2層の基底面分布図を示す。この図から木曽川の河川水が誘発涵養を生じる可能性のある場所は,図中の矢印で示した部分であることが推定される。既存資料によれば,この付近では,G1とG2層が地下浅所に分布しており,誘発涵養が生じやすい地質構造である。
- 図1の矢印をはさむ木曽川上下流の犬山と越観測所の流量と犬山頭首工の農業用水の取水量データを,次式に代入して,誘発涵養量X を計算した。
X = O(越観測所流量)+N(犬山頭首工取水量)-I(犬山流量観測所流量) - 計算は日単位で,1975年から1993年まで行った。図2は,1985年の誘発涵養量の計算結果を示している。誘発涵養は,年数回発生しており,最も大きな涵養は6月から7月に生じている。
- 図3は1985年の誘発涵養の発生と,涵養をうけた直下流の江南市の地下水位の関係を示している。江南市の観測所では6月から7月の誘発涵養の影響で,浅層と深層の地下水位が上昇している。
- 年間の平均涵養量は3.4億m3/年で,この値は,既存の文献のシミュレーション結果とも整合する。
成果の活用面・留意点
平野や扇状地末端の水田からの涵養した地下水は,浅層地下水を涵養するだけで,非農業者が利用している深層地下水を涵養することはまれである。しかし,誘 発涵養が生ずるほどの多量の深層地下水の利用がある場合は,灌漑水は深層地下水を涵養して,外部経済を発生する。精度の高い水田の地下水涵養機能の解析で は,誘発涵養を考慮する必要がある。
具体的データ
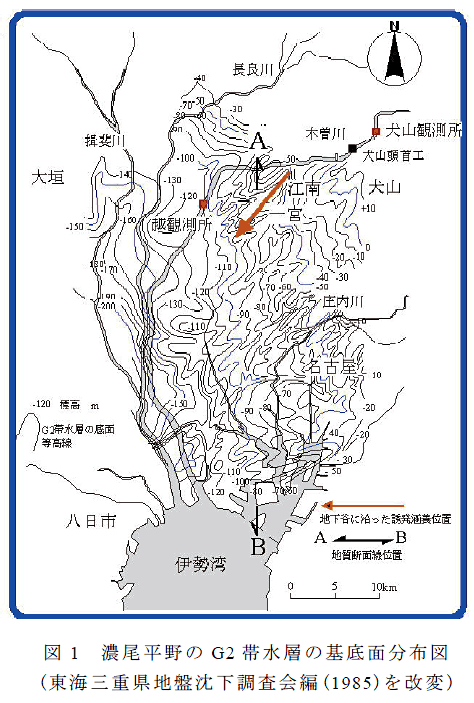
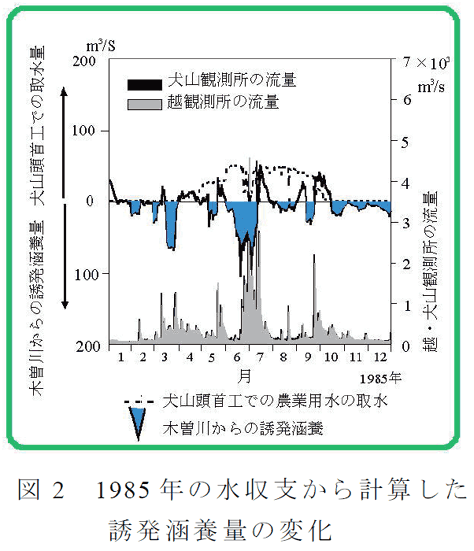
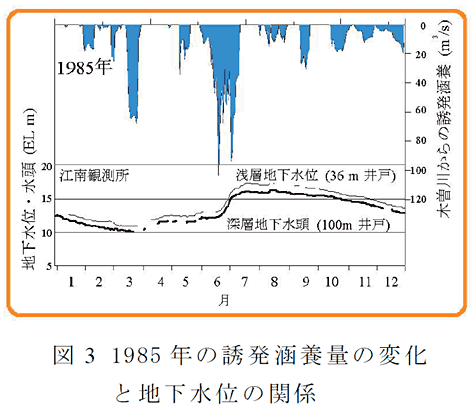
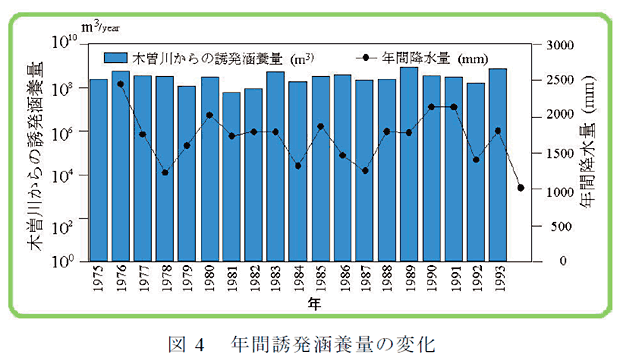
その他
- 研究中課題名:農村地域における健全な水循環系の保全管理技術の開発
- 実施課題名:亀裂構造を考慮した岩盤斜面の地下水流動機構の解明
- 課題ID:421-a-00-002-00-I-06-8202
- 予算区分:交付金研究
- 研究期間:2006~2008年度
- 研究担当者:今泉眞之,土原健雄,吉本周平,石田 聡
- 発表論文等:Masayuki Imaizumi・Satoshi Ishida・Takeo Tsuchihara,Long-term Evaluation of the Groundwater
Recharge Function of Paddy Fields Accompanying Urbanization in the Nobi Plain, Japan,
PADDY AND WATER ENVIRONMENT,4(4),pp.251-263,2006.
