ため池底樋のパイピング発生メカニズム
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
軟弱地盤上に位置するため池底樋では、盛土荷重による底樋周りの地盤の不等沈下に伴って、底樋管下部、特にコンクリート撒き立ての角部において空洞が発生し、パイピングが発生する可能性がある。
- キーワード:ため池、底樋、軟弱地盤、土圧
- 担当:農工研・施設資源部・土質研究室
- 連絡先:電話029-838-7575、電子メールthori@affrc.go.jp
- 区分:農村工学
- 分類:研究 参考
背景・ねらい
農業用ため池は、全国に21万個所存在し、地域の貴重な水資源となっている。底樋は基盤と堤体の間に設置される取水管であるが、底樋沿いに漏水が発生し決壊に至る事例が数多く報告されている。このような事例は、老朽化したため池で報告されている場合が多いが、底樋を部分改修した後に発生している場合もある。本研究では、底樋を有する地盤模型を用いて、底樋沿いの漏水が発生するメカニズムを明らかにした。
成果の内容・特徴
- 図1に示すような底樋を設置した地盤の模型を用いて載荷実験を行った。土槽中に24cm角で長さ2mのコンクリート製の底樋模型を設置した後、Table1に示す笠間土を用いて地盤を盛り立てた。底樋は沈下しないように支柱で土槽に固定されている。模型作成後、エアーバッグを用いて模型上面から140kPaまで段階的に載荷を行った後、上載圧を維持しながら、模型下部から給水し、地盤を飽和した。また、底樋管頂、管側、管底に設置した土圧計より、実験中の底樋周りの土圧を計測した。土槽のアクリル面を通してデジタルカメラで模型断面を撮影し、PIV解析によって変位を算出した。
- 図2に載荷中における底樋周りの土圧の変化を示す。示すように、上載圧の増加に伴い、底樋上面に応力集中が発生して底樋管頂部の土圧は大きく増加するが、底樋側面および下面では土圧が減少することが分かった。底樋下部の地盤の沈下によって底樋と地盤の間に空洞が発生することが分かった。
- 変位計測の結果を図3に示す。載荷によって底樋側部の地盤が沈下するのに伴って、底樋下部の地盤も沈下していることが分かった。
- 載荷完了後、底樋周辺のパイピング実験を行った。底樋の片側から色水を注水した結果、底樋下面、特に角部分を通って色水が流下したことが観察され、底樋沿いにパイピングが発生したことが分かった(図4)。
- 以上のことから、基礎地盤が軟弱な場合、底樋周辺の地盤の変形によって、底樋沿いにパイピング等の水みちが発生する可能性があることが分かった。
成果の活用面・留意点
- 基礎地盤が軟弱な場合、底樋の改修に際して、底樋周辺の土圧が維持されるように、施工を行う必要がある。
具体的データ
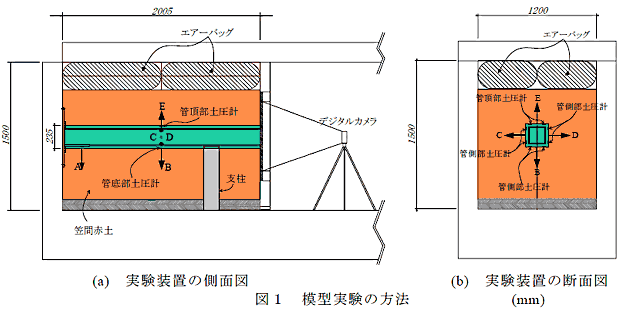
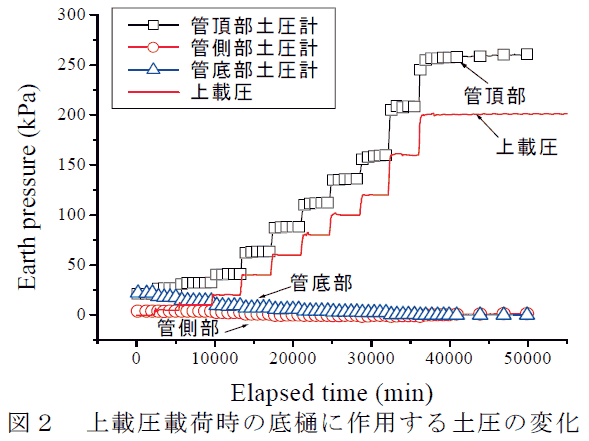
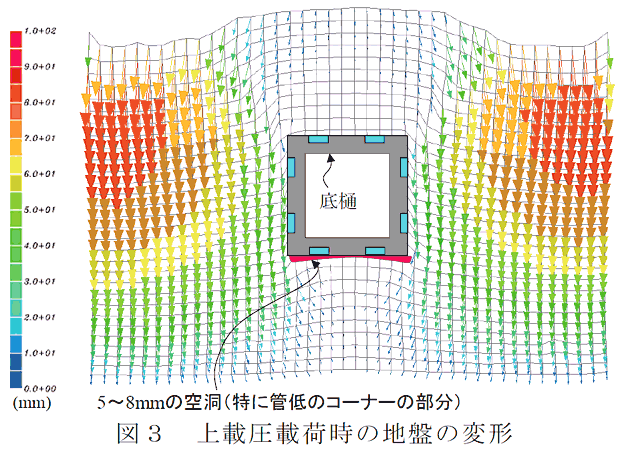
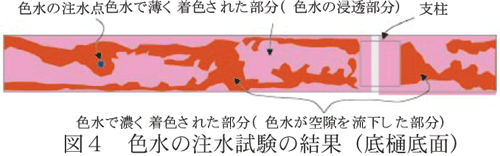
その他
- 研究中課題名:農業水利施設の機能診断・維持管理及び更新技術の開発
- 実施課題名:老朽底樋の構造機能診断法の開発
- 課題ID:412-a-00-008-00-I-06-4806
- 予算区分:交付金プロ(施設機能)
- 研究期間:2004~2006年度
- 研究担当者:堀 俊和、毛利栄征、松島健一、有吉 充
- 発表論文等:
1)ため池底樋周辺の浸透に関する模型実験、第40回地盤工学研究発表会、pp.1925-1926、2006/07、毛利 栄征、
藤田 信夫、末永 悟志
2)ため池底樋に作用する土圧の検討、第39回地盤工学発表会、pp.1749-1750、2004/07、澤田 豊、河端 俊典、
毛利 栄征他
特願2006-051405
