老朽化フィルダムの性能照査型耐震診断および改良土による補強
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
大規模地震動が想定される地域にある老朽化フィルダムでは、耐震性が不足することが想定されている。性能照査型設計手法および改良土による具体的補強工法により、老朽化フィルダムの耐震補強を行うことができる。
- キーワード:老朽化フィルダム、性能照査型設計手法、改良土による補強工法
- 担当:農工研・企画管理部・防災研究調整役
- 連絡先:電話029-838-8193、電子メールstani@affrc.go.jp
- 区分:農村工学
- 分類:技術および行政 参考
背景・ねらい
設計基準の確立していない時代に築造され、長期間を経ている堤高15m以上の老朽化したフィルダムのうちで、東海地震のような大規模地震動が想定される地域では、耐震性が不足することが想定されている。特に設計基準が確立していない時代に築造されたものについては、耐震性の照査、災害時の下流の影響等を考慮して補強が必要なフィルダムを抽出し、適切な補強を行っていく必要がある。このために、老朽化フィルダムの耐震補強を行うための、性能照査型設計手法および改良土による補強工法の検討を行う。
成果の内容・特徴
- 大規模地震動(レベル2地震動)が想定される地区の中央防災会議による予測震度データをデータベース化し、既存の「ため池データベース」から参照できるデータ構造とし、予測震度、築造年等から耐震補強の必要なフィルダムの抽出を行った。
- フィルダムの性能照査のための具体的性能目標を、過去のフィルダムの地震被害事例の検証から天端沈下量の数値として提案した。表-1に示す内容で地震動の設定、解析法、評価パラメータについて、具体的な既存フィルダムの事例で検証を行い、ISO23469(2006年制定の国際耐震基準)に適合する設計事例を作成した。レベル2地震動に対応した性能照査法として、フィルダムを完全弾塑性体として有限要素法による変形解析を行って評価した。
- 耐震性が不足する場合の耐震補強法として`砕・転圧盛土工法`を使用したフィルダムの耐震補強工法の開発及び設計法を開発した。図-1は既存のフィルダムを開発した工法による補強断面を示したものである。表-1に示す流れで耐震性を評価し、地震時の性能目標を満足する補強効果を確認した。
成果の活用面・留意点
- 耐震性の検証方法として、構成則等の違いにより動的応答解析の結果に差異があるが、`安全係数`的な係数を導入することにより、動的応答解析を設計に使用していく必要がある。
- 耐震補強工法として`砕・転圧盛土工法`を利用した方法を提案したが、堤体の条件、敷地上の条件等により、`砕・転圧盛土工法`では効率的な補強が出来ない場合が想定される。このため、他の補強法も利用したフィルダムの`ハイブリッド補強工法`を今後検討、開発する必要がある。
- 本研究では性能照査型耐震補強法に関する、性能目標、照査法、耐震補強工法についてマニュアル化に必要な項目は整理、開発した。今後、基準化の際の資料として活用できる。
具体的データ
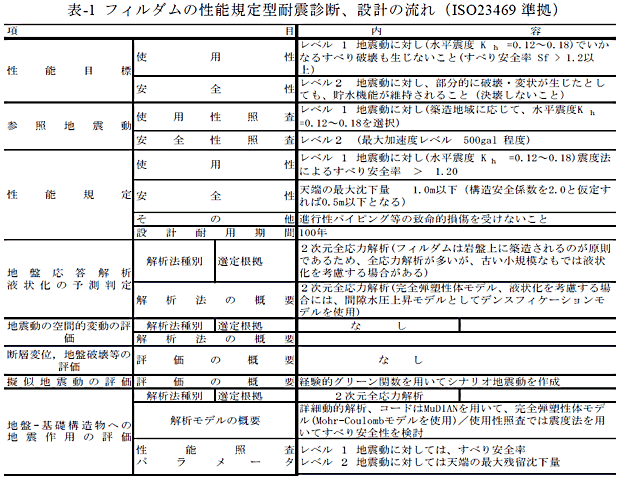
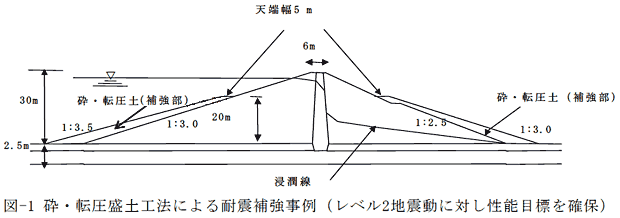
その他
- 研究中課題名:農業用フィルダムの高地震力を考慮した堤体機能回復技術の開発
- 実施課題名:農村における施設等の資源の維持管理・更新技術の開発
- 課題ID:412-a-00-003-00-I-06-4305
- 予算区分:交付金研究プロジェクト(農業水利機能の実体解明と機能回復手法の開発)
- 研究期間:2004~2006年度
- 研究担当者:谷 茂
- 発表論文等:
1)谷茂、福島伸二、北島明、西本浩司(2006)、老朽化フィルダムにおける固化処理した底泥土を用いた堤体改修の
設計法、農業工学研究所所報、45、pp.1-20
2)谷茂(2007)、ため池の耐震設計のポイント、基礎工、35(1),pp.100-102
