棚田景観の保全計画策定のための景観変化解析手法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
田面、畦畔木、樹林地の3つの景観構成要素を空中写真の判読により把握し、変化とその要因を解析することにより、棚田景観の変化を視覚的に捉えることができる。
- キーワード:棚田景観、景観構成要素、農業形態、変化・形成要因、動態保全
- 担当:農工研・農村環境部・景域整備研究室
- 連絡先:電話029-838-7583
- 区分:農村工学
- 分類:技術及び行政・参考
背景・ねらい
都市、農山漁村等における景観への関心の高まりを受けて、景観の保全・整備を目的とする景観法が、平成16年6月に成立し、平成 17年6月に全面施行された。これにより農村景観の保全に向けた動きが活発化している。なかでも棚田の呈する景観(棚田景観)は、各地で保全活動が展開さ れるなど、農村景観の保全・形成において、きわめて重要な対象となっている。棚田景観に代表される文化的な景観の保全をめぐっては、景観を成立させてきた 地域の営農活動や生活などの継続を重視しつつ動態的に景観の保全を図っていく「動態保全」のあり方の検討が求められている。本成果では、「動態保全」概念 を導入した景観保全計画策定のための棚田景観の景観変化解析手法について提案する。
成果の内容・特徴
- 本手法は、棚田景観を構成する要素に着目し、棚田景観を、①棚田の田面、②畦畔木、③樹林地の3つの景観構成要素と、要素の組み合わせからとらえ(図1)、空中写真を用いて、各景観構成要素とセル(方形50m)を単位とした景観類型の変化を解析することにより、棚田景観の変化を把握することができるものである。本成果における解析対象例は、新潟県東頸城郡の2地区(A地区,B地区)である。
- 棚田景観の景観構成要素は、棚田の田面の面積・筆数の減少、樹林地面積の拡大、畦畔木の減少など変化してきたこと(表1)、棚田景観の景観類型(図2)は、1976年から1995年の間に小規模な筆で構成される棚田景観(類型①,②)や畦畔木を有する棚田景観(類型①,③,⑤)が大きく減少し、一方で耕作放棄等が進んだ景観(類型⑧)、樹林地が卓越する景観(類型⑦,⑨)が増加してきたこと(図3)が明らかになった。
- 棚田景観の変化は、小規模な筆や畦畔木といった旧来の農業形態のもとに成立してきた景観構成要素が、機械化などの農業形態の 変化の中で改変され、減少していく過程であったと整理することができる。変化には、まちなおし(隣接する筆の畦畔を取り払う等の方法で一筆の面積を拡大す る簡易な整備)や畦畔木の伐採など住民が主体となって実施した小規模な整備(営農的な改変)によるものと、耕作・管理放棄に伴う植生遷移の進行など、住民 の働きかけが失われていくなかで生じてきたものがある(図4:左)。
- 変化解析の結果を用いることにより、景観の変化・形成要因を踏まえた棚田景観の保全方策を現場レベルで住民自らが検討可能となる。本成果において把握された結果(図4:左)に基づいた場合、①まちなおしなどの営農的な改変などを含めた住民による景観形成活動への支援、②小規模な筆や畦畔木などの保全を目的とした旧来の農業形態などの営みも含めた景観形成活動の再生などの保全方策が検討できる(図4:右)。
成果の活用面・留意点
本研究の成果は、動態的な保全が求められている棚田景観などの文化的景観の保全方策の検討において活用できる。成果の活用にあたっては、各地域の棚田景観の特徴(景観構成要素、農業形態等)を十分に踏まえる必要がある。
具体的データ
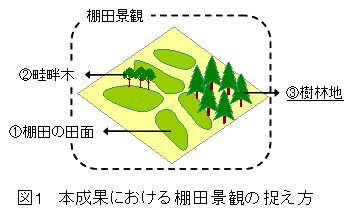
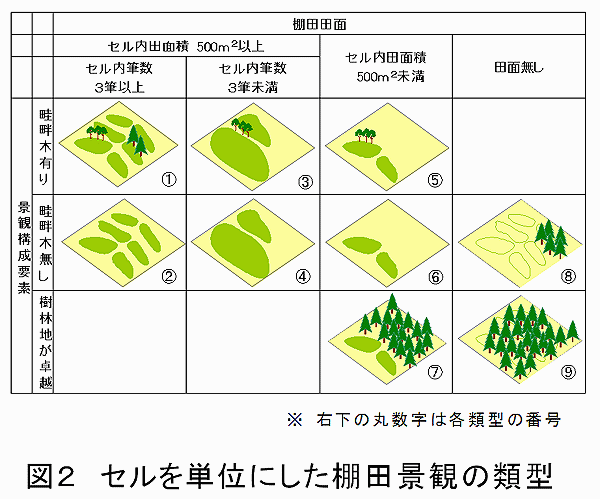
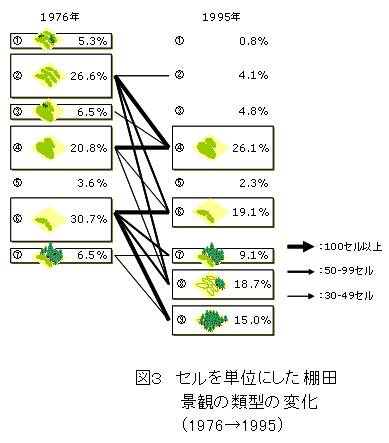
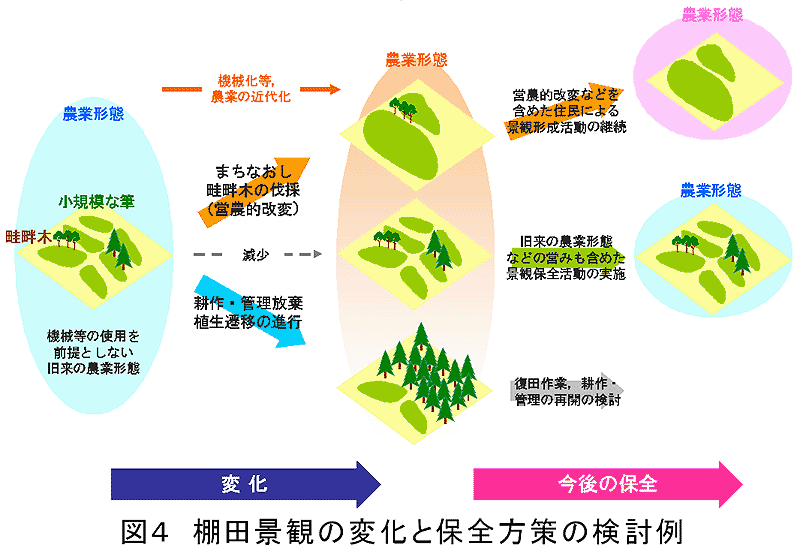
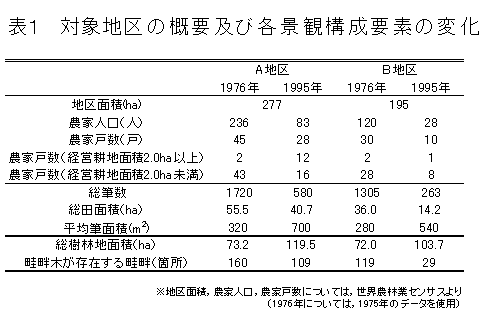
その他
- 研究課題名:地域資源を活用した豊かな農村環境の形成・管理技術の開発
- 実施課題名:地域特性を踏まえた環境協働管理のインセンティブ評価手法の開発
- 課題ID:421-d-00-001-00-I-07-9202
- 予算区分:交付金プロ(資源保全)
- 研究期間:2006~2008年度
- 研究担当者:栗田英治・山本徳司
- 発表論文等:栗田ら(2007)景観構成要素と農業形態の変化からみた棚田景観の変容、農村計画学会誌、26巻 論文特集号: 239-244
