たい肥施用による硝酸態窒素溶脱量の分布推定
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
たい肥や化学肥料を施用した圃場や点源などからの硝酸態窒素溶脱量を,GISと窒素・炭素の動態モデルを組み合わせて推定する。この手法により,バイオマスを利用した場合の地下水保全効果について評価することが可能である。
- キーワード:宮古島、地下水、硝酸態窒素、バイオマス、環境負荷
- 担当:農工研・農地・水資源部・農地工学研究室
- 代表連絡先:電話029-838-7552
- 区分:バイオマス
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
地下水における硝酸態窒素濃度の環境基準超過は深刻な問題であり,特に化学肥料や畜産ふん尿など農業活動に由来する汚染も少なからず,排出量の削減を求める意見も多い。たい肥の利用促進や畜産ふん尿の適切な変換と利用など,バイオマスの適正利用を通じ,硝酸態窒素溶脱量の抑制を進める必要がある。
そこで本研究では,GIS手法と窒素・炭素の動態モデル(DNDC,DeNitrification and DeComposition model,Li et al.,1992)を組み合わせて,事例として沖縄県宮古島の地下水集水域における硝酸態窒素溶脱量を推定し,その分布を表示する。この手法を用いて,地下水の保全を目的とした作物導入やバイオマス利用の影響を事前に評価でき,地下水集水域管理のツールとしての活用が期待される。
成果の内容・特徴
- 航空写真や地籍図を用いてGISデータを整備し,各圃場の作付けなどは実測や航空写真などから推測し,圃場の施肥量等の営農管理情報と畜産頭数などは既往文献や聞き取り調査で収集して整理する。これらを入力値としてDNDCモデルを用いて,各圃場や点源などの排出源からの硝酸態窒素溶脱量を推定し,再度GISを用いて空間分布を可視化する(算定の流れは図-1参照)。
- 宮古島において実測した,サトウキビ畑,1作期の硝酸態窒素溶脱量63.6kgN/haに対して,DNDCモデルによる試算値は59.2kgN/haであり,おおむね合致している。
- 宮古島市砂川地下水集水域を対象に各圃場における硝酸態窒素溶脱量を推定する。航空写真を用い砂川地下水集水域の土地利用を把握する(図-2は1994年の事例)。次に,同域における各圃場からの単位面積あたり,年間の硝酸態窒素溶脱量を計算し,可視化する(図-3は1994年の状況)。
- 地下水の硝酸態窒素濃度改善シナリオとして,たい肥を化学肥料代替で施用した場合の,各圃場からの硝酸態窒素溶脱量について,同年を対象に同域で計算を行うと,効果を評価することができる(図-4 )。
成果の活用面・留意点
- DNDCモデル適用のためには,土壌,作物,気象,営農管理など様々なデータが必要である。
- この手法は,研究機関の支援を受けて実務者が利用することができ,バイオマスタウン構想の策定などに活用することが可能である。
具体的データ
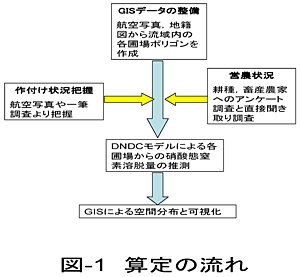
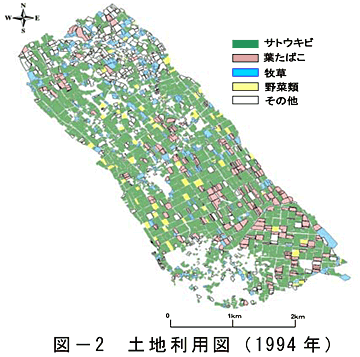
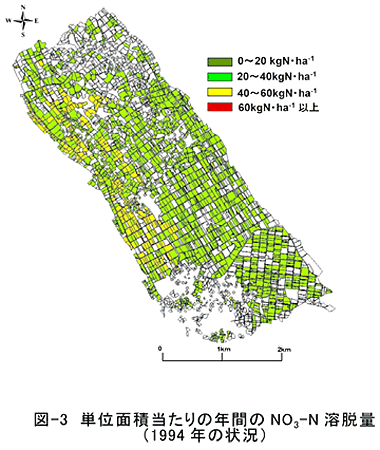
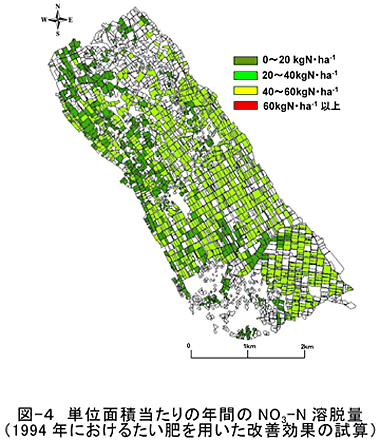
その他
- 研究中課題名:畜産廃棄物,食品廃棄物等の有機性資源の循環利用のためのシステム整備技術
- 実施課題名:バイオ燃料製造を含めたバイオマス利活用システムの導入評価
- 実施課題ID:411-e
- 予算区分:委託プロ(バイオマスモデル)
- 研究期間:2007~2011年度
- 研究担当者:凌 祥之,塩野隆弘(企画チーム),宮本輝仁,亀山幸司,島武男(土地資源研究室),
藤家里江(重点研究支援者),中川陽子(重点研究支援者) - 発表論文等:1)藤家ら(2008),農工研技報207号,127~138
2) Y. NAKAGAWA,et. al.(2008)JARQ,Vol.42, No.3,163~172
