評価グリッド法を用いた非農業者が揚水水車を好ましいと評価する要因
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
非農業者が身近にある揚水水車を好ましいと評価する要因を評価グリッド法で調査・解析する。本手法の適用から、非農業者が揚水水車を好ましいと評価する要因は、地域らしさがあり、音が良いと感じて好ましいと評価することである。
- キーワード:農業資源、地域らしさ、パーソナル・コンストラクト理論
- 担当:農工研・農村環境部・環境評価研究室
- 代表連絡先:電話029-838-7684
- 区分:農村工学
- 分類:技術及び行政・参考
背景・ねらい
非農業者が農業・農村景観をどのように理解し好ましいと評価するかを知ることは、農業・農村への理解や、農業資源を保全する活動への参加の促進に重要である。しかし、それを定量的に明らかにしている事例は少ない。
人間が環境を理解し好ましいと評価する構造の構築は、評価グリッド法が多用される。これは、G.Kellyが提唱した人間の行動を情報処理の結果として捉えることが特徴であるパーソナル・コンストラクト理論による個人の評価構造を抽出するレパートリー・グリッド法を、総合評価を頂点とする評価構造のみを抽出するように発展させた手法である。
本成果は、評価グリッド法を用いて非農業者が揚水水車を好ましいと評価する構造を構築し、アンケート調査によって、揚水水車の選好性評価により強い影響を及ぼす要因を検討する。
成果の内容・特徴
- 22基の揚水水車(図1)を利用する岡山県S地区(全98世帯中非農家92世帯)の結果である。
- 揚水水車を「好ましい」と評価する要因を得るために、非農業者17人に農業用水路を好ましいと評価する理由を聞き取り(具体的なコンストラクトの抽出)、その上位項目(抽象的なコンストラクト)と下位項目(目や耳等の感覚器で知覚した環境)を誘導する質問技法であるラダーリング手法で評価構造を構築(図2)するインタビュー調査を行い揚水水車が関係する構造を抽出する。
- 農業用水路に対するインタビュー結果から揚水水車が重要な影響を果たしていることが分かり、揚水水車に対してその評価構造を定量化するためにアンケート調査を行う。非農業者へのインタビュー調査で得られた評価構造を元に設定された、表1に示す質問項目で141人の回答から、重回帰分析を行って階層間の関係を算出すると図3のようにコンストラクト別に結びつきの強さが標準偏回帰係数(β)でわかる。
- 標準偏回帰係数(β)の積より、S地区の非農業者が揚水水車を好ましいと評価する要因は主に、具体的なコンストラクトである「S地区らしさがある(地域性)」、「音が良い(音環境)」が抽象的なコンストラクトである「美しさ」、「親しみ」に影響し、それらが「選好性評価」に影響する関係で示される。したがって、揚水水車を好ましいと評価する際に、S地区らしさを感じることや音が良いことを重視していることがわかる。
成果の活用面・留意点
- 保全すべき農業資源の好ましさの評価を明らかにすることで、非農業者の農業資源保全活動への参加促進に寄与する資料となる。
- 対象が他の特徴的な農業・農村景観(通潤橋のような歴史的水利施設等)でも、本手法のように評価構造を構築することができる。
- 評価グリッド法は讃井純一郎氏の登録商標である。
具体的データ

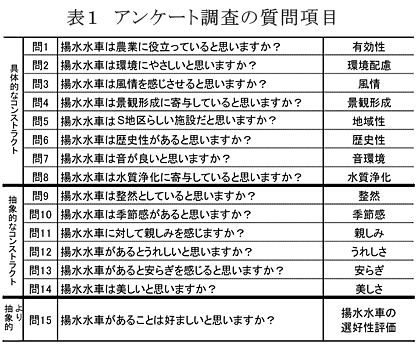
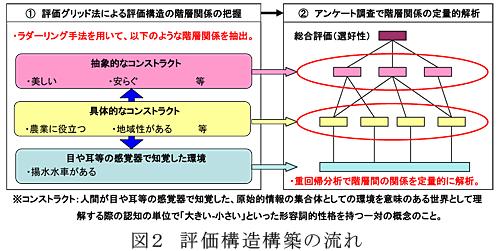
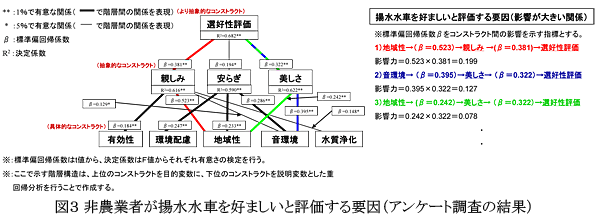
その他
- 研究中課題名:地域資源を活用した豊かな農村環境の形成・管理技術の開発
- 実施課題名:農村の水辺環境における空間構造の変容に伴う環境水準の影響評価手法の開発
- 実施課題ID:421-d-00-003-00-I-08-9304
- 予算区分:交付金研究
- 研究期間:2006~2008年度
- 研究担当者:廣瀬裕一、嶺田拓也、松森堅治
- 発表論文等:1)廣瀬ら(2009)農村計画学会誌、27:305-310
