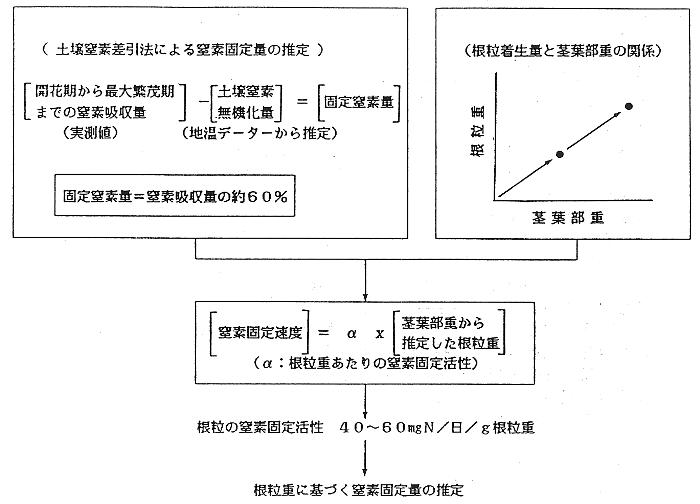根粒着生重および茎葉部重に基づくダイズの根粒窒素固定量の推定
要約
- 担当:東北農業試験場・地域基盤研究部・低温ストレス研究室
- 部会名:総合農業
- 分科会名:生産環境
- 分類:(3)
成果の内容
- 技術・情報の内容及び特徴
- 黒ボク土畑地における昭和54年から59年までの各種ダイズ栽培試験成績に基づいて、開花期以降最大繁茂期までの根粒窒素固定量推定法を案出した。すなわち、この期間のダイズ窒素吸収量から地温に基づいて推定される土壌窒素無機化量を差引くことによって、同期間の根粒固定窒素量が算出される(土壌窒素差引法)。本土壌における窒素固定量は、年次・肥培管理の違いに関係なしに吸収量の60%(変動係数17%)とほぼ一定の値を示した。
- 開花期以降の茎葉部重と根粒着生重量の間には、年次・肥培管理の違いによらず、一定の傾向が認められた。すなわち、根粒数の増加は開花期以降頭打ちになるが、根粒重の茎葉部重増加に対する増加割合は開花期以前とほぼ同じであり、15mg根粒重増/g茎葉部重増であった。このことは、気象・肥培管理の違いによらずダイズの光合成産物の一定の割合が根粒に配分されていることを示している。
- 開花期以降最大繁茂期までの単位根粒重当りの窒素固定活性は、(1)で得られた窒素固定量から求めた窒素固定速度及び(2)で得られた関係に基づいて茎葉部重から推定した根粒重から、40~60mgN/g根粒/日と推定された。したがって、この値を用いて開花期から最大繁茂期までの根粒着生重量の経時的変動を積算すれば、この期間の固定窒素量を推定することが可能である。
- 技術・情報の適用効果
地温から土壌窒素無機化量を推定するための情報が得られていれば、既往の成績からダイズの窒素固定量をおおよそ推定することが可能である。また、この推定値は大豆の肥培管理を策定する上での基礎資料となる。
- 適用の範囲
根粒着生の良好な圃場
- 普及指導上の留意点
窒素固定量の少ない開花期以前の推定は難しい。
具体的データ
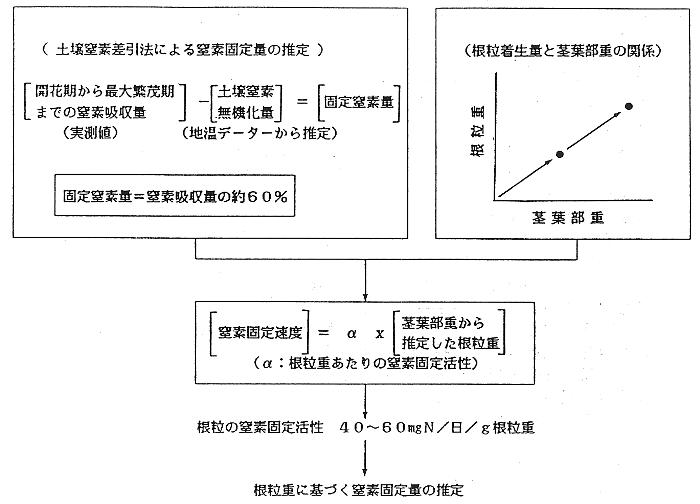
その他の特記事項
- 研究課題名:
寒冷地大豆の好適肥培管理エキスパートシステムの開発 -土壌窒素肥沃度評価システムの開発-
- 予算区分:別枠(情報処理)
- 研究期間:昭和62年度~平成元年度
- 発表論文等:平成2年度土壌肥料学会東北支部大会において発表