稲作のコストダウン限界の要因
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
- 担当:東北農業試験場・農村計画部・経営管理研
- 部会名:経営
- 分科会名:
- 分類:(2)
成果の内容・特徴
-
技術・情報の内容及び特徴
稲作の生産コストは、規模が大きくなるにつれて連続的に低下しつづけるのではなく、9~10haを超えると一定の限界に達する(図)。この点についてこれまでは、大規模化に伴う圃場の分散化の影響 を強調し、団地化や圃場区画の整備で大幅なコストダウンが達成されるとする理解が多かった。しかし、経営規模拡大に伴い機械装備を大型化しても、 必ずしも省力化は十分果たし得ないという、わが国の稲作技術構造を背景とするより基本的な要因には考慮が払われてこなかった。そこで、このような点を 踏まえてわが国稲作のコストダウン限界を規定する要因と、それを克服するための中心課題を提示した。 稲作の生産コストが9~10ha以降低下していかない理由は、以下のとおりである。
1.このような大きい面積規模にいたると、作業適期幅規制や労働負荷の増大等から機械の大型化、複数化が不可避となり、農機具償却費総額も増加する。
2.一方、大型化、複数化される以前の機械装備においてすでに、田植機やコンバイン等自走式機械を用いた作業時間割合は表に示すように1割近くまで低下している。
3.そのため、それら機械類を大型化、複数化したとしても、それによる省力効果 はごく限られたものにしかならず、労働費の減少や、一層の規模拡大による償却費の削減も期待できない。
4.すなわち、機械化一貫体系といわれながらも、現実には、今日なお、人力作業工程(表中のB・D)を多く残す現代稲作の技術 構造が、わが国の稲作コストダウンの限界を特徴付けている。
5.したがって、稲作の一層のコストダウンを図っていくためには、わが国の高温多湿な自然条件を踏まえた上で、人力依存の稠密な作業工程をいかに省力化して いくかという視点からの技術開発こそ今後の中心課題とする必要がある。 - 技術・情報の適用効果
稲作のコストダウンへの適正な期待と限界に対する認識および技術開発 の方向に関する知見が得られる。 - 適用の範囲
東北地域を中心とした平場水田地帯の稲作経営。 - 普及指導上の留意点
条件の不利な中山間地帯並びに経営複合化によるコストダウンは別途検討 が必要。
具体的データ
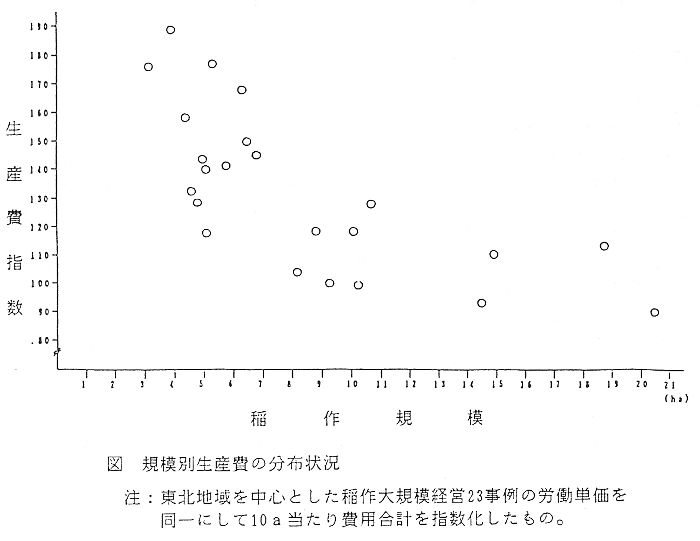
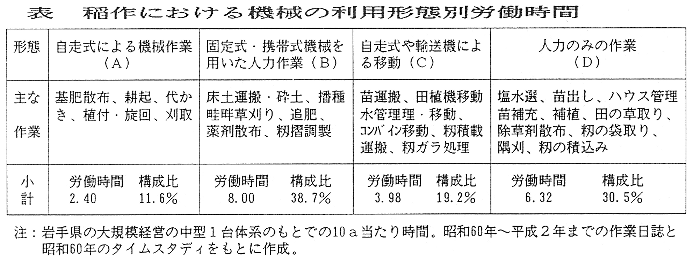
その他
- 研究課題名:大規模水田作経営の経営管理モデルの開発、寒冷地水田営農におけるコストダウン限界の解明。
- 予算区分 :経常、総合(高品質輪作)
- 研究期間 :平成元年~3年、平成2年~3年。
- 発表論文等:梅本雅;稲作における規模の経済性、東北農業試験場報告、第84号
