野草地への牧草導入とその後の植生動態及び牧養力
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
- 担当:東北農業試験場 草地部 草地管理研究室
- 部会名:畜産
- 分科会名:草地
- 分類:(2)
成果の内容・特徴
-
技術・情報の内容及び特徴
放牧利用の減少により木本植物が侵入するなど牧養力が低下した野草地を肉用 繁殖牛用の低コストな飼料資源として再開発するため、このような野草地に牧草を 導入し放牧圧を加えた条件下での植生の動態と牧養力の推移を検討した。 その結果、牧草が容易に定着し、年次的に拡大、維持されること、牧養力が野草地 に比べ向上し、長期にわたって維持されることを明らかにした。
1. シバ型野草地からクマイザサとミヤマヤナギの優占する低木そう林へ遷移しつつある 野草地に牧草種子を表面播種した。基肥として大粒緩効性肥料を用い、その量 を少肥(牧草導入I区)及び多肥(牧草導入II区)とした。利用1年目以降は 無追肥条件とした。またシバの被度が比較的高い野草地を無処理(野草区)とし 比較に供した(表1)。各区とも日本短角種 繁殖牛を6年間毎年6月上旬から10月上旬まで約4ヵ月間定置放牧した。
2. 導入後牧草の被度は経年的に拡大し、6年後においてもオーチャードグラス、フェスク 類、シロクローバを主とする牧草類の被度が高く維持された。一方、主要構成種であった クマイザサとミヤマヤナギの被度は低下した。牧草化の速度は緩効性肥料の量が 多く、放牧圧が高い牧草導入II区で早かった(図1)。
3. シバ、クマイザサ、ミヤマヤナギの優占する野草区では、放牧にともないクマイザサの被度が 低下し、シバが回復する植生変化がみられた(図1)。
4. 牧草の導入により牧養力は向上し、190CD(I区)から320CD(II区)を長期にわたり維持 することができた。また野草区でも140CD程度の牧養力が得られた(表2)。 - 技術・情報の適用効果
東北地方の山間野草地の植生改善、牧養力の向上、植生管理を行なうときの参考 となる。無追肥のため省力、低コストで放牧利用できる。 - 適用の範囲
東北地方の山間地、特に木本植物が侵入した野草地 - 普及指導上の留意点
緩効性肥料の肥効は2~3年持続するのでこの間に適正な放牧圧を加えることによって 牧草の定着を促進することが重要である。
具体的データ
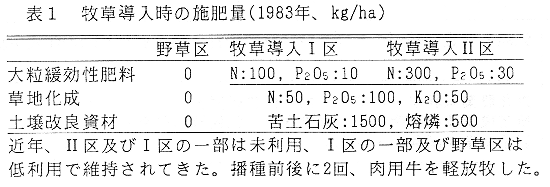
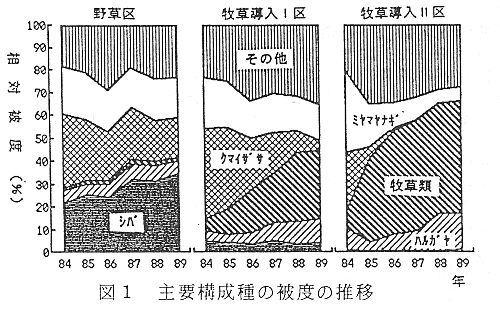
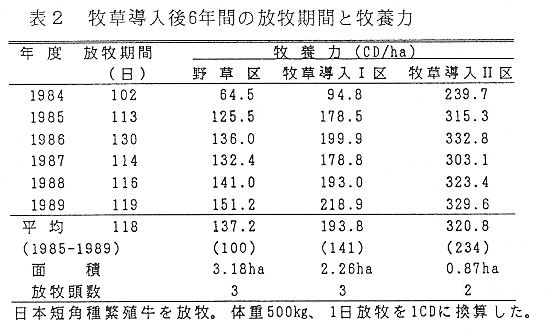
その他
- 研究課題名:植生及び家畜生産力の年次変動ならびにその要因の解析
- 予算区分 :経常
- 研究期間 :1982~1991年
- 発表論文等:須山ほか(1990)野草地の放牧利用と植生遷移に関する研究.
日草誌36(別),57-58.
