家畜寄生性ハエ類の生物的防除のための競合種の選定基準
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ノイエバエやノサシバエ等の食糞性家畜害虫に対する防除法として、競合現象を利用 した生物的防除が有望な手法であることを明らかにした。また、導入および放飼すべき 有力競合種の発育生態を提示した。
- 担当:東北農業試験場・畜産部・家畜虫害研究室
- 連絡先:019-643-3544
- 部会名:畜産(家畜)
- 専門:飼育管理
- 対象:家畜類
- 分類:研究
背景・ねらい
牛糞が多量に排出される放牧地では、ノイエバエやノサシバエ等の食糞性ハエ類が大きな個体群を形成し放牧牛を加害する。これらの防除は、労力、経済性、環境汚染の面から化学的防除法だけに頼ることができない。食糞性ハエ類にとって、幼虫の生息場所である牛糞塊が、一つの閉鎖生態系となっている点に注目し、糞塊内で起こっている種内・種間での競合現象を利用した防除法の可能性を明らかにし、同時に有力競合種導入のための、発育生態の解明を試みた。
成果の内容・特徴
- 食糞性ハエ類には、糞塊内での過密条件下で発育期間が延びる型と短縮する型の2型(前者をイエバエ型、後者をノイエバエ型と呼ぶ)が存在する(表1)
- 東北地方に分布する食糞性ハエ類は50余種を数えるが、その内、放牧地で定着できるのは10種程で、いずれも大きな個体群を形成する。これらの多くの種はノイエバエ型を示す。
- ノイエバエ型とイエバエ型との食糞性ハエ類の種間密度飼育では、前者が競合的に優位となる。
- 放牧地での経年トラップ調査から、東北地方では6月中旬~下旬以降(それまでの有効温量により変動)、糞塊内競合が顕著に現れる(図1)。
- 以上の食糞性ハエ類の発育生態の分析から、有力競合種を導入・放飼することにより食糞性家畜害虫の個体群を低く抑えることが理論的に可能となった。
- その有力競合種を導入および育種する基準として、競合的に優位となりうる発育生態である次の3点を提示した。
1)幼虫期高密度条件下での羽化成虫における平均サイズ減少率が大きいこと。
2)幼虫期高密度条件下での羽化に至るまでの発育期間が短縮すること。
3)羽化成虫のサイズが減少し始める密度水準が、死亡率の増加し始める密度水準より低いこと。
成果の活用面・留意点
競合種を放飼するには、その地域に分布していない種を導入しなければならない。また、当然ではあるが、害虫とならない種でなければならない。
具体的データ
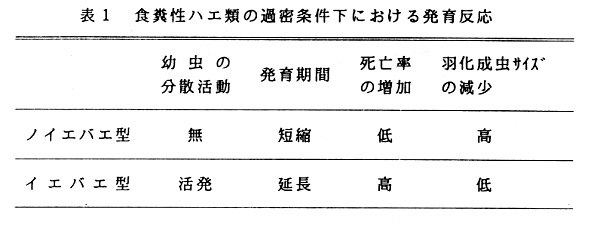
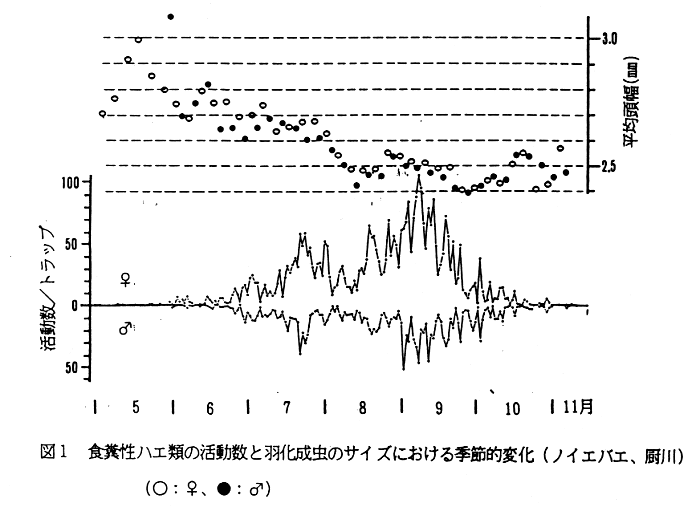
その他
- 研究課題名:食糞性ハエ類の種間競合
- 予算区分:経常
- 研究期間:平成6年度(平成1~5年)
- 発表論文等:
Ecological study of the dung-breeding flies, with special reference to the intra- and inter-specific larval competitions in cattle dung pats. 東北農業試験場研究報告 80号 Orthellia caesarion Meigen における幼虫期密度とその発育との関係.北日本病害虫研報 44巻
