ダイズ莢先熟個体における栄養体貯蔵タンパク質の蓄積
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ダイズの莢先熟個体では登熟中期(R6)より栄養体貯蔵タンパク質(27、29kDa)が茎部へ蓄積され、タンパク質の合成・供給量に対して子実のタンパク質蓄積が相対的に劣る傾向を示す。
- 担当:東北農業試験場・水田利用部・栽培生理研究室
- 連絡:0187-66-2776
- 部会名:畑作物
- 専門:栽培
- 対象:豆類
- 分類:研究
背景・ねらい
ダイズの莢先熟現象は莢が十分に成熟し、収穫可能な状態に達しているにもかかわらず、茎が水分と緑色を保ち続けている状態であり、機械収穫時に汚粒発生など品質低下の原因となる。ダイズでは、子実などの養分の転流先が不足した場合に葉、茎などの栄養器官で合成、蓄積される栄養体貯蔵タンパク質(VSP)が知られている。VSPの蓄積に着目することにより莢先熟現象発生の生理的な要因の解明をはかり、品種の育成や管理技術の改善に役立つ情報を得ようとした。
成果の内容・特徴
- 莢を切除した個体は収穫期において茎部に著しいVSPの蓄積を示す(表1)。正常個体ではほとんどVSPの存在が見られないのに対し、莢先熟となった個体では莢切除個体よりは少ないもののVSPが蓄積されている(表1)。
- クロロフィルの分解が進まず、莢先熟が多発した試験区(スズマル-E)では、小発区(スズマルーL、スズカリ-E)に比べ、収穫期の約4週間前のR6(表2)において多量のVSPが蓄積されている(表3)。こうした莢先熟多発区におけるVSPの蓄積は可溶性タンパク質含量に対する比率で見ても同様である(図1)。
- 以上の点は、莢先熟現象を生じる個体や品種では、登熟中期にはすでに余剰のタンパク質が栄養体内に生じていることを示唆している。
成果の活用面・留意点
- 莢先熟現象の発生を誘導する環境要因の解明や品種間差の解析研究の進展に役立つ。
- 外見からは莢先熟発生が区別できない時期から発生を予測する手法の開発に役立つ。
具体的データ
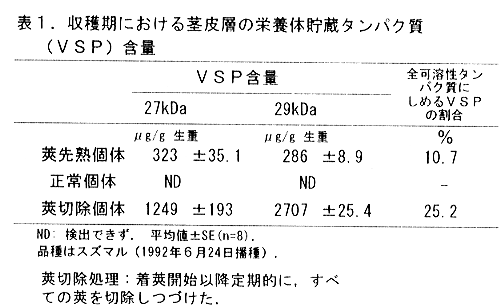
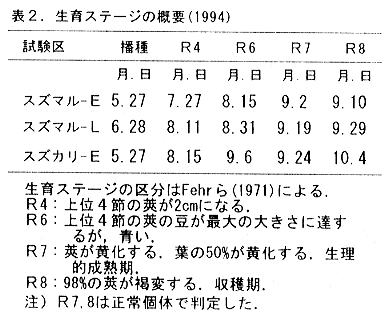
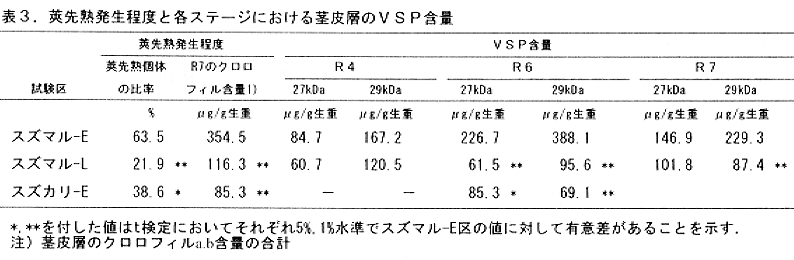
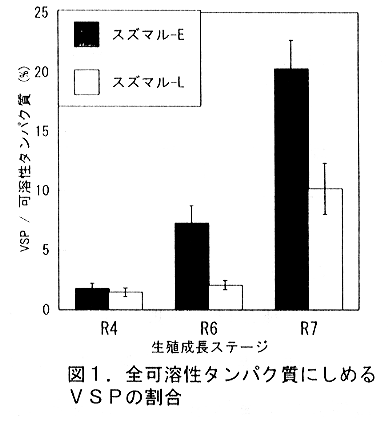
その他
- 研究課題名:水田輪作畑作物(大豆)の水分特性の解明莢先熟現象の生理的機構の解明
- 予算区分:経常
- 研究期間:平成7年度(平成2~7年)
- 発表論文等:萩原均・石倉教光.1994.ダイズの「莢先熟」現象の生理的解析と発生予知の可能性.
日作紀63(別2):201-202.
Ogiwara,H.and Terashima,K. 1995.Accumulation of vegetative storage protein in soybean plants that developed delayed stem maturation.Proc. 2nd Asian Crop Science Conference.(in printing)
