世代促進栽培における小麦の硬軟質性の選抜
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
温室で世代促進を行った小麦の雑種初期世代の種子の胚乳側を粉砕した粉の 硬質結晶粒子の多少を光学顕微鏡で観察することで、 硬軟質性を個体選抜することができる。
- 担当:東北農業試験場・作物開発部・品質評価研究室
- 連絡先:019-643-3513
- 部会名:畑作物
- 専門:育種
- 対象:麦類
- 分類:研究
背景・ねらい
硬質小麦と軟質小麦を交配した場合、蛋白含量や粉色等の特定の品質形質だけで選抜すると硬質小麦もしくは軟質小麦に片寄る可能性があるため、育成初期に硬質小麦と軟質小麦を選抜する必要がある(伊藤ら1995)。一方、赤さび病等の耐病性育種では世代促進を行いながら選抜することが多く、世代促進中に品質形質の選抜ができれば効率的である。そこで、小麦粉の硬質結晶粒子の観察による硬軟質性の検定方法(池田1961)が世代促進中の初期世代における選抜に適用可能か検討する。
成果の内容・特徴
- 硬質品種・銘柄の小麦の種子をハンマーで粉砕し、 篩をとおした粉について光学顕微鏡で観察すると硬質結晶粒子が多く認められる。 一方、軟質品種・銘柄の小麦では、硬質結晶粒子がほとんど認められない。 「キタカミコムギ」(軟質)と「コユキコムギ」(硬質)を温室で栽培した材料でも 硬質結晶粒子の多少はあまり変わらない。
- 軟質品種と硬質品種を正逆交配し、 温室で世代促進を行って得たF2種子を「半粒検定法」で評価し (図1)、 硬質結晶粒子「無」と判定したもののうち、F3個体で 5粒とも硬質結晶粒子が「無」である個体の割合は58~64%である。 同様にF2種子で硬質結晶粒子「多」と判定したもののうち、 F3個体で5粒とも硬質結晶粒子が「多」である個体の割合は 33~43%である(表1)。
- F3個体を圃場に播種して得られたF4系統の子実を ブラベンダー製粉機(篩:70GG)で製粉した粉について、 ブレーン空気透過装置・粉末度測定器で比表面積を測定すると、 F3個体で5粒とも硬質結晶粒子「無」を選抜した F4系統のほとんどが2300平方センチメートル/g以上に分布し、 F3個体で5粒とも硬質結晶粒子「多」を選抜した F4系統のすべてが1700平方センチメートル/g以下となる (図2)。 通常、比表面積2000平方センチメートル/g以上が軟質、 2000平方センチメートル/g以下が硬質とされているので、 これらの手順により硬軟質性の選抜ができたと考えられる。
成果の活用面・留意点
- 硬軟質性の早期選抜における評価法として活用可能である。また、硬質結晶粒子の結晶性が降雨により影響されるとされていることから、雨害のない世代促進栽培での選抜は安定していると考えられる。
- 少数の組み合わせから得られた結果なので、他の組み合わせでは選抜効率が変わる可能性がある。
- 本試験の世代促進は、1葉期から緑体春化(8度C、24時間照明、6週間)した後、温室(15~25度C、14時間日長)で養成した。
具体的データ
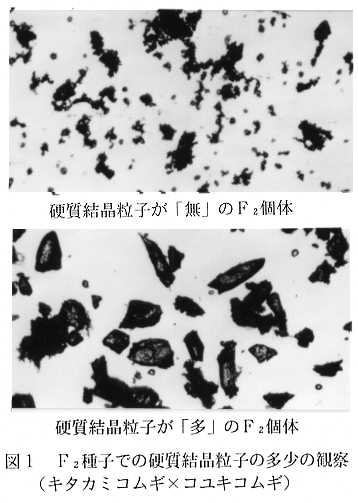
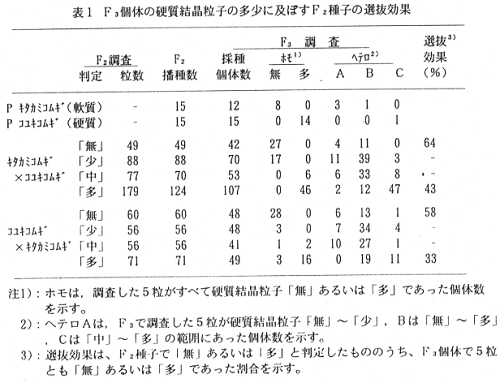
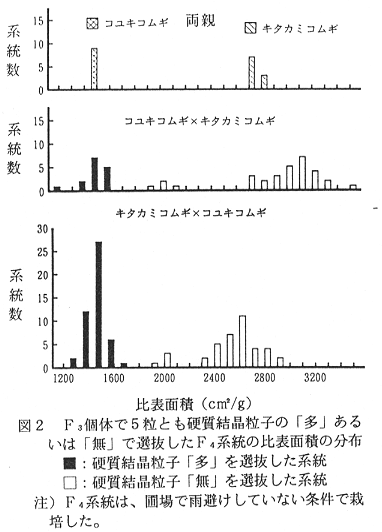
その他
- 研究課題名:グリーンバーナリ世代促進における高品質選抜法の開発;小麦の世代促進における硬軟質性の選抜
- 予算区分:高品質輪作;経常
- 研究期間:平成9年度(平6~8)
- 発表論文等:世代促進栽培におけるコムギの硬軟質性の選抜、東北農試研報、93号、101~106、1998。
