枠試験での食菌性トビムシによるアブラナ科野菜の苗立枯れ症抑制効果
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
苗立枯れ症の原因となる糸状菌Rhizoctonia solani を混和した枠土壌に、食菌性トビムシの一種Folsomia hidakana を導入することにより、ハクサイ、キャベツの苗立枯れ症を抑制することができる。
- 担当:東北農業試験場・畑地利用部・畑土壌管理研究室
- 連絡先:024-593-6176
- 部会名:生産環境
- 専門:土壌
- 対象:葉茎菜類
- 分類:研究
背景・ねらい
ポット試験で苗立枯れ症に抑制効果が認められた食菌性トビムシの一種 F.hidakana を、実際の野菜栽培に活用するための予備試験として、露地育苗を模した枠試験においても同様の効果が認められるかを確認する。
成果の内容・特徴
- 露地育苗を模した2.7×2.7m2の枠試験においても F.hidakana はキャベツ、ハクサイの苗立枯れ症を抑制する効果が認められる (図1)。
- R.solani 汚染土壌のみを混入した区では、正常に生育する苗が対照区の1割程度であるのに対し、汚染土壌にF.hidakana を125,000個体/m2(概算値)加えた区では、 9割以上正常な苗である(図2)。
- 抑制効果はキャベツ、ハクサイの品種間で大きな違いが認められない (図2)。
- トビムシ導入区で栽培した苗の根表面からはR.solani は分離されなかった。トビムシ導入区で栽培した苗にR.solani は感染していないものと考えられる。
- F.hidakana を導入した後、播種までに2週間の間隔をとる必要がある (図3)。
成果の活用面・留意点
- トビムシ導入個体数を2/3にすると、正常に生育する苗が6割以上減少することをポット試験で確認している。
- トビムシを定着させることは難しいため、毎回育苗時毎に、新たにトビムシを導入する必要がある。
- F.hidakana の大量飼育法は既にほぼ確立している。
- 屋内の枠試験というF.hidakana にとって最適環境下での試験結果であり、より高温・乾燥条件下で効果が得られるような新たなトビムシ類を探索している。
具体的データ
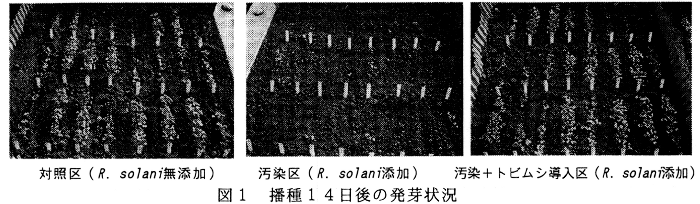
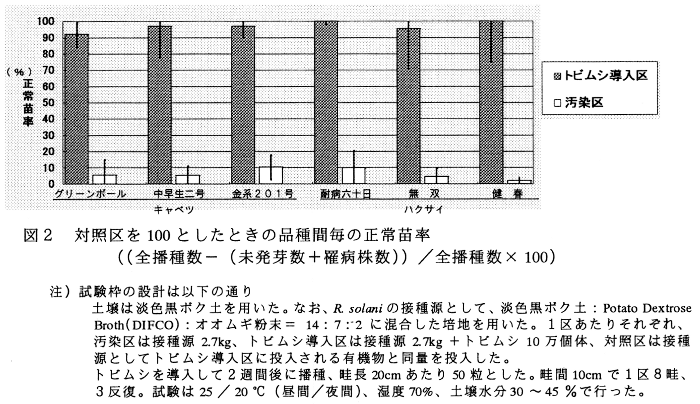
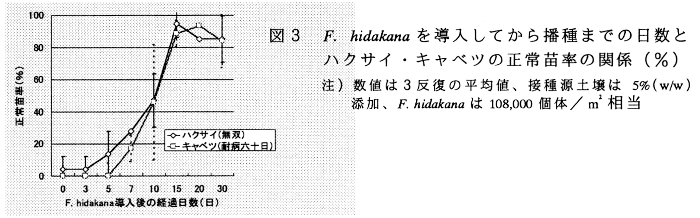
その他
- 研究課題名:疑似圃場条件下におけるトビムシ類の野菜苗立枯れ発病抑制
- 予算区分:経常
- 研究期間:平成11年度(平成8~10年)
- 研究課題名:有用トビムシの選抜並びに大量飼育法の確立
- 予算区分:地域総合
- 研究期間:平成11年度(平成10~12年)
- 発表論文等:
疑似圃場枠でのトビムシFolsomia hidakanaの苗立枯れ症抑制効果、日本土壌動物学会講要、12、1999
