東北地域の標高の高い草地へのチモシーの導入
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
東北地域の標高の高い草地へのチモシーの導入は、年間2回刈りの条件下でオーチャードグラスに比較して多収である。また、1番草の刈り取りが適期より遅れても、植生の安定や品質的にも優れている。
- 担当:東北農業試験場 草地部 飼料作物研究室
- 連絡先:019-643-3563
- 部会名:畜産(草地)
- 専門:栽培
- 対象:牧草類
- 分類:研究
背景・ねらい
東北地域の草地はオーチャードグラスを基幹草種とした造成が一般的に行われてきた。標高の高い地帯にも多くの草地が造成されたが、この草地の刈り取りは適期から遅れることがしばしばで、刈り取り回数も年間2回以下と少ないところが多く、オーチャードグラスの株化や植生および品質の低下を招いている。このような条件下においては、熟期が遅く耐寒性にも優れているチモシーを導入することにより、草地植生の維持と高品質飼料の安定的な生産を図ることができると考えられるため、東北地域の標高の高い草地でのチモシーの適応性と生産性を明らかにする。
成果の内容・特徴
試験草地は1994年8月に、標高の高い草地とsて姫神地区(標高900m、1995年5~10月 の日平均13.1度C)と低い草地として厨川地区(標高160m、同期間平均気温17.8度C) に、チモシー(4品種:クンプウ、ノサップ、ホクセン、ホクシュウ)と オーチャードグラス(キタミドリ)を各々単播した。刈り取りは年間2回刈りとし、 1番草を各品種の出穂期頃に刈る適期刈り区と、梅雨明け直後に刈る遅刈り区を 設けた(厨川地区の適期刈りキタミドリのみ年3回刈り)。
- 姫神地区の草地における乾物収量は、年2回刈りの条件下では、1番草の刈り取り時期にかかわらずチモシーがオーチャードグラスより高く、またチモシー品種間の差は適期刈り、遅刈り共に小さい (表1)。
- 姫神地区においてオーチャードグラス草地の植生は、遅刈り条件下で他のイネ科草種の侵入が著しいが、チモシー草地は適期刈り、遅刈り条件とも他草種の侵入は少なく植生は安定している。しかし、厨川地区では逆にチモシー草地への他のイネ科草種の侵入が多く見られる(図1)。
- 1番草の刈取り時期と品質について、出穂以降日数の経過とともに消化率は低下するが、その低下の速度はチモシーがオーチャードグラスに比べ遅い (図2)。
- 以上の点から姫神地区のような標高の高い草地で、特に刈り遅れの予測がされる場合においては、チモシーの導入により、より安定した飼料生産が可能になる。
成果の活用面・留意点
- 東北地域の標高の高い草地にチモシーを導入するための指針として活用できる。
- 地域や条件によってチモシーの適する標高の境界は異なると考えられるため、別途検討する必要がある。
具体的データ
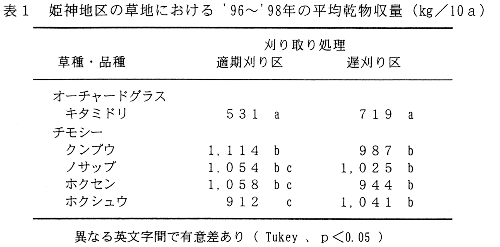
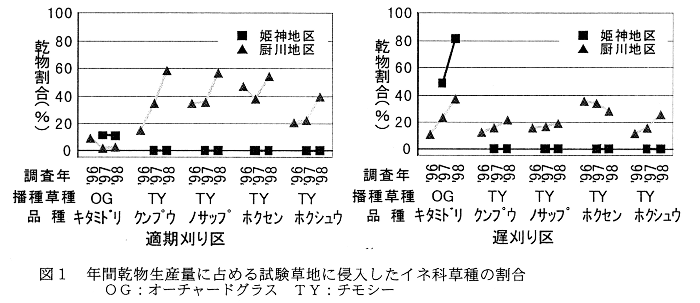
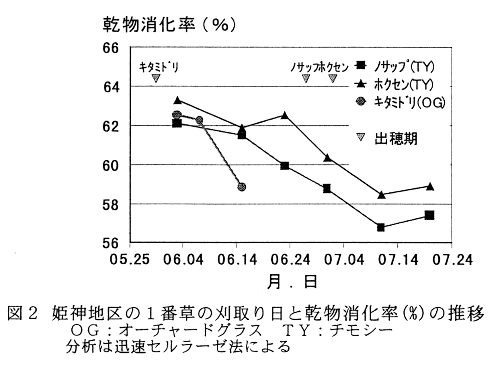
その他
- 研究課題名:刈り取り時期がチモシー草地の植生と品質に及ぼす影響
- 予算区分:経常
- 研究期間:平成11年度(平成7年~11年)
