ダイズわい化ウイルス(SbDV)YP系統に対する大豆の抵抗性遺伝資源
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
大豆品種ツルコガネおよびツルムスメは、東北地方で問題となるダイズわい化ウイルスエンドウヒゲナガアブラムシ媒介黄化系統(SbDV-YP系統)に感染しても収量構成要素(株当たり粒重・百粒重)に対する影響が少い抵抗性遺伝資源である。
- キーワード:ダイズわい化ウイルスYP系統、抵抗性遺伝資源、ツルムスメ、ツルコガネ
- 担当:東北農研・地域基盤研究部・病害管理研究室
- 連絡先:019-643-3465
- 区分:共通基盤・病害虫、東北農業・生産環境
- 分類:科学・普及
背景・ねらい
北日本の大豆生産にとって最大の脅威となるダイズわい化病の防除には抵抗性品種の開発・導入が有効と考えられる。病原であるダイズわい化ウイルス(SbDV)には、媒介するアブラムシおよび病徴の違いにより、4つのタイプがある。これまで、それぞれのタイプに対する抵抗性遺伝資源は明らかではなかった。東北地方には、エンドウヒゲナガアブラムシで媒介され黄化症状を示すYPと呼ばれる系統が広く分布する。そこで、東北地方向けの抵抗性品種の開発のために、このYP系統に対する抵抗性遺伝資源を明らかにしようとした。
成果の内容・特徴
- YP系統のみを保毒させたエンドウヒゲナガアブラムシを用いて、大豆をウイルス感染させ、無接種株に対する収量構成要素(株当たり種子重・百粒重)の減少を比較することで抵抗性を評価する実験系を確立した(図1)。このとき、感染を確認したソラマメでアブラムシを保毒させることで、接種効率の安定化を図った。
- 供試した抵抗性遺伝資源候補品種中で、ツルムスメとツルコガネは、2年間の試験を通して、SbDV-YP系統への感染による株当たり粒重および100粒重に対する影響が安定して少なかった(図2・3)。
- 他の収量構成要素(草丈・節数・着莢数)では、2年間の試験を通して安定して有意な差は認められなかった(データ省略)
成果の活用面・留意点
- ツルムスメおよびツルコガネは、SbDV-YP系統に対して抵抗性であり、SbDV-YP系統が主に問題となる地域を対象として、これらを抵抗性遺伝資源とした抵抗性品種の開発が可能と考えられる。
- 本成果で示したツルムスメおよびツルコガネの抵抗性は、SbDV-YP系統に対するものであり、他の系統については別に検討する必要がある。
具体的データ
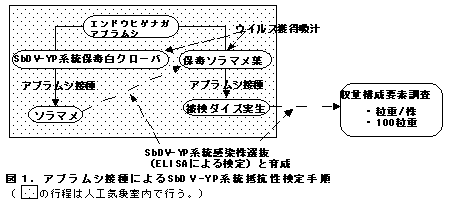
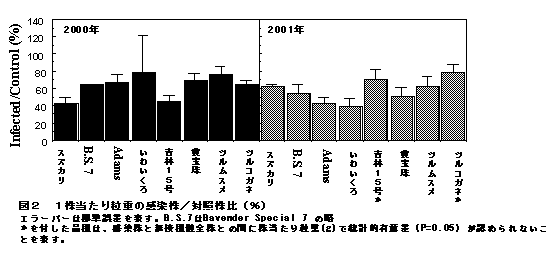
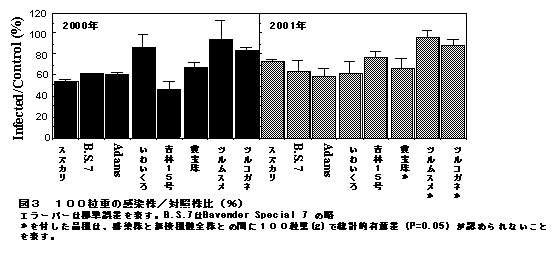
その他
- 研究課題名:ダイズわい化病の圃場における高精度検定法の開発と抵抗性遺伝資源の検出
- 予算区分:プロジェクト研究「転作作物」
- 研究期間:1999~2001年度
- 研究担当者:大藤泰雄、寺内英貴、兼松誠司、石黒潔、本多健一郎、小田島裕、阿部陽
- 発表論文等:1)小田島ら(2001) 北日本病虫研報 52 p250、
2)阿部ら(2002)第55回北日本病害虫研究発表会にて発表
