寒冷地におけるヒエ病原菌Drechslera monoceras製剤の除草効果と他の管理法との組合せ効果
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ヒエに感染する植物病原菌Drechslera monoceras製剤は、寒冷地においてはタイヌビエの発生盛期頃の処理で比較的高い除草効果が得られ、他の管理法との組み合わせによりその効果は大きく向上する。
- キーワード:植物病原菌、Drechslera monoceras、生物除草剤、ヒエ、処理時期、水稲作
- 担当:東北農研・水田利用部・雑草制御研究室
- 連絡先:0187-66-2771
- 区分:東北農業・水稲
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
植物病原性不完全菌Drechslera monocerasはヒエ対象微生物除草剤としての開発がはかられており、その分生胞子を活性本体として製剤化されたMTB-951(M社)は、我が国初の水稲用生物除草剤として期待されている。処理された分生胞子は田面水中でヒエ実生に付着感染するが、水中での生存日数は短く、一般に広く使用される化学除草剤に比べると環境条件による効果変動が大きいとされている。処理時期及び他の雑草管理法との組合せ効果を明らかにし、雑草発生が不斉一な寒冷地での効果的な使用に資する。
成果の内容・特徴
- Drechslera monocerasの高密度処理(6×109分生胞子/a以上)では高く安定した除草効果が得られるが、低密度処理(3×109分生胞子/a以下)では早い処理時期ほど除草効果が不安定となる(表1)。
- 雑草の発生が不斉一な寒冷地においては、早く発生したタイヌビエの1葉期(最大葉令1)でも80%以上は未発生であり(図1)、この時期の処理では感染個体が少なく除草効果が低い。発生数が30~60%となる発生盛期の処理では、感染個体が多くなることから高い除草効果が得られる(図2)。
- タイヌビエ2葉期前後の処理でも発生盛期には至らずDrechslera monoceras単独の効果が劣る場合があるが、雑草の生育を抑制する活性炭スラリーあるいは中耕除草との組合せによって、その除草効果は大きく向上する(表2)。また、ヒエ以外の雑草を防除する上でも、他の管理法との組合せは有効である。
成果の活用面・留意点
- 寒冷地における使用指針作成の参考となるが、ヒエの発生・生育が速やかな温暖地以西では処理時期の検討が別途必要である。
- 処理後1週間はヒエが水没するだけの水深を確保し、特にヒエ1.5葉期以降の処理では草丈伸長が速やかであることから、7~10cm以上の深水を維持する必要がある。
- 第3葉が抽出したヒエに対しては、除草効果が著しく劣る場合がある。
具体的データ
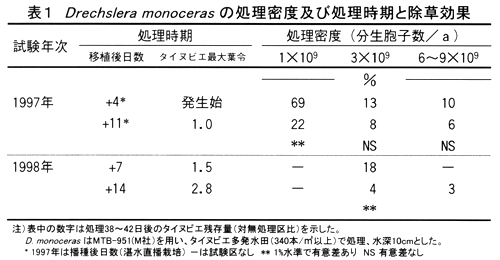
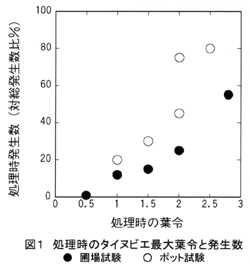
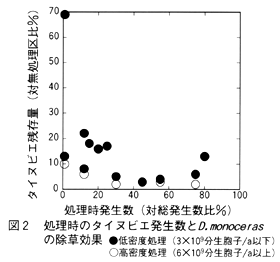
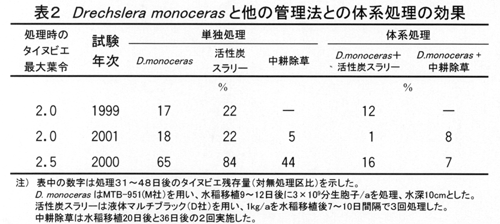
その他
- 研究課題名:水田雑草の耕種的・生物的防除法の開発
- 予算区分:経常(一部受託)
- 研究期間:1995~2001年度(2000~2001年度は受託)
- 研究担当者:渡邊寛明、内野彰、橘雅明
- 発表論文等:1)Watanabe, Uchino and Tachibana (2001) Proc. The 18th Asian-Pacific Weed Sci. Soc.
Conf. Beijing, China, 416-421.
