食糞性コガネムシ類の導入種と在来種2種の種間関係
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
Digitonthophagus gazella(導入種)とカドマルエンマコガネ(在来種)が同じ糞で繁殖しても互いの増殖率への影響はほとんどない。しかし、D.gazellaとオオマグソコガネ(在来種)が同じ糞で繁殖すると、オオマグソコガネの幼虫の影響によってD.gazellaの幼虫の生存率が低下する。
- キーワード:食糞性コガネムシ類、導入種、在来種、種間関係、昆虫機能、昆虫類
- 担当:東北農研・畜産草地部・家畜環境研究室
- 連絡先:019-643-3544
- 区分:東北農業・畜産、共通基盤、畜産草地
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
これまでに放牧地の牛糞分解を促進するため、糞の埋め込み能力に優れた食糞性コガネムシ(D. gazella)を海外から導入し、大量に飼育する技術が開発されている。しかし、導入種を野外で利用するには事前に在来種との相互作用を調べておく必要がある。そこで、D.gazellaと同様に地下に糞を埋め込んで幼虫のための餌(育児塊)を作る在来種のうち、体の大きさが同程度で、広く分布し、個体数の多いカドマルエンマコガネ(以下、カドマルと略)とオオマグソコガネ(以下、オオマグソ)をD.gazellaと相互作用を及ぼす可能性の高い種として取り上げ、D.gazellaとの種間関係を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 自種密度効果:3種とも一つの糞に自種だけがいる場合は、親世代の成虫密度が高くなると次世代の成虫数が減るという密度効果がある(図1)。
- 他種密度効果:
1)カドマルとD.gazellaでは、2種が同じ糞で繁殖しても、次世代の成虫数(図2)は、自種だけの時(図1)と有意に異ならない。
2)オオマグソとD.gazellaが同じ糞で繁殖すると、D.gazellaでは親の密度が低い方が子供の数が少なくなるという、通常の密度効果とは逆の結果になった(図3)。一方、オオマグソはどの密度でも自種だけの時より子供の数が多くなった。 - 上記2-2)の結果は、オオマグソとD.gazellaが同じ糞で繁殖すると、自種だけの時に比べ、幼虫の生存率がD.gazellaでは下がり(図4)、オオマグソでは上がる事による。これはオオマグソの幼虫の一部がD.gazellaの育児塊に侵入し、直接的、間接的にD.gazellaの幼虫を殺すためとわかった。他種の幼虫の餌を奪う行動は労働寄生と呼ばれ、数種で知られているが、育児塊を作る種の幼虫が労働寄生を行うのは珍しい。
成果の活用面・留意点
- オオマグソの密度が高いところではD.gazellaは増殖率を低く抑えられる可能性があるので、D.gazellaを野外で定着利用するにはオオマグソの密度が低い地域を選ぶ事が望ましい。
- D.gazellaの野外放飼にあたっては、育児塊を作らずに地上の糞内で繁殖する種など、異なるタイプの繁殖習性を備えた在来種への影響も考慮する必要がある。
具体的データ
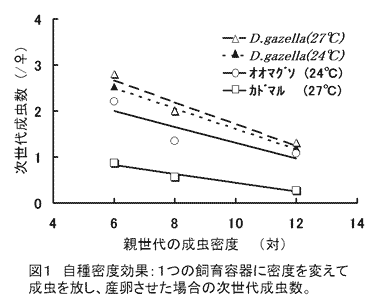
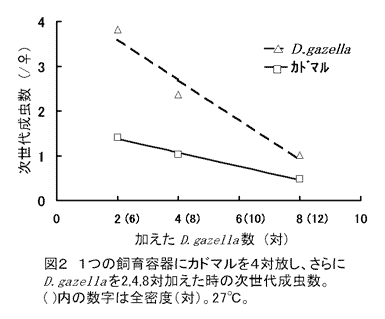
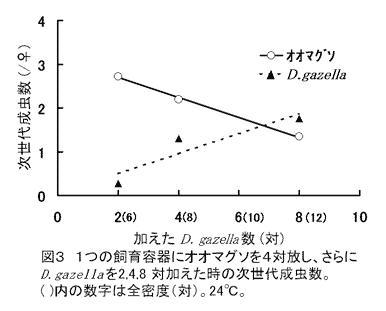
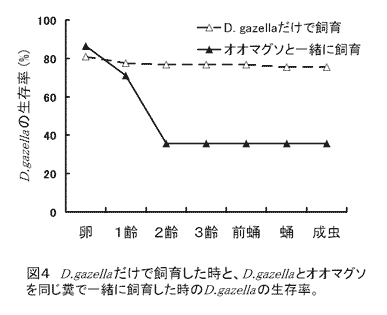
その他
- 研究課題名:家畜糞の分解における食糞性昆虫の利用
- 予算区分:経常
- 研究期間:1996~2000年度
- 研究担当者:吉田信代
- 発表論文等:1)吉田(2000) 日本昆虫学会第60回大会
2)吉田(2001) 日本昆虫学会第61回大会
