積雪寒冷地水田におけるタイヌビエの土中種子数予測モデル
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
本モデルは、寒冷地水田でのタイヌビエ土中種子の動態や種子生産特性に基づいて、前年の土中種子数と除草効果から翌年の土中種子数を予測するモデルである。これによれば、1000粒/m2以下の種子密度で水田を維持するには97%以上の除草効果が求められる。
- キーワード:積雪寒冷地、タイヌビエ、土中種子、除草効果、種子数予測モデル
- 担当:東北農研・水田利用部・雑草制御研究室
- 連絡先:電話0187-66-2771、電子メールwatahiro@affrc.go.jp
- 区分:東北農業・水稲、共通基盤・雑草
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
タイヌビエは全国に分布する一年生ヒエ属植物(ノビエ)の1種であり、寒冷地水田でもその発生は多く、残草すれば水稲の減収をまねく強害雑草である。本研究では、発生密度を低く抑えるための要防除水準を策定するために、除草程度の異なる水田において土中生存種子数及び種子生産量等の調査を行い、土中種子数予測モデルを作成する。
成果の内容・特徴
- タイヌビエを完全に除草すれば、土中種子数は土中死滅や発芽・出芽などで毎年60%ずつ減少し、残りの40%が翌年の春まで生存して発生源となる(図1:完全除草)。
- 完全に除草できない場合は新たな種子が供給され、その数は除草効果によって異なる残草量に依存し、無除草や機械除草では1万粒/m2以上の高い種子密度で推移する(図1)。
- 本モデルは、ある年tの土中種子数SP(t)(粒/m2)とその年間生存率SV1、および種子生産量P(粒/m2)とその越冬生存率SV2から、翌年t+1の土中種子数SP(t+1)(粒/m2)を推定するものである(式1)。式中のSV1とSV2は、完全除草区と無除草区の土中種子数の推移をもとに推定する(図2)。
SP(t+1) = SP(t)×SV1 + P×SV2 (式1)
種子生産量Pは残草量Ge(g/m2)から単回帰式を用いて推定する(式2, R2=0.766)。Geは無処理区の残草量G(g/m2)と除草効果Eによって決まる(式3)。Gは土中種子数SP(t)から対数ロジスティック式を用いて推定する(式4)。
P=84.821×Ge-42.728 (式2)
Ge=G×(1-E) (式3)
G=277.59/(1+14010×exp(-1.6288×ln(SP(t)))) (式4)
したがって、式1~4より、SP(t+1)はSP(t)とEから推定できる。 - 圃場試験で得られたSV1(0.4)とSV2(0.73)及び各処理区の除草効果E(完全除草1, 薬剤除草0.98, 機械除草0.46, 無除草0)を用いて翌年の種子数を推定すると、本モデルは除草効果が高い場合にはよく当てはまるが、除草効果が低い場合には若干当てはまりが悪い(図3)。
- このモデルによれば、土中種子数1000粒/m2から種子数を減らすには除草効果0.97以上、100粒/m2からさらに種子数を減らすには除草効果0.99以上が求められる(図4)。
成果の活用面・留意点
- 除草技術を評価する際の参考となる。
- 本モデルを他地域で適用するためには、土中種子の年間生存率SV1、新鮮種子の越冬生存率SV2、及び回帰式である式2及び式4を、地域毎に求める必要がある。
- 草種毎のパラメータを求めることにより、他の一年生雑草にも適用できる。
具体的データ
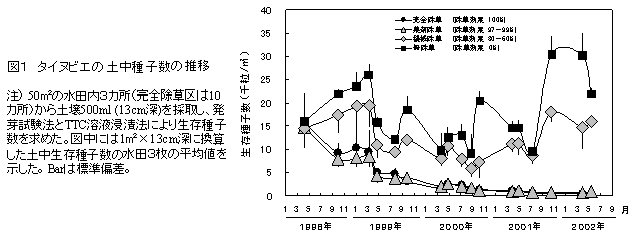
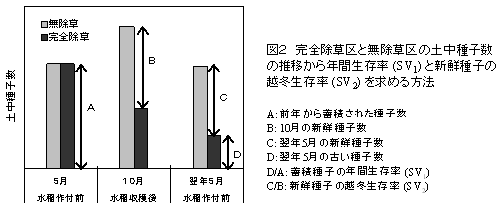
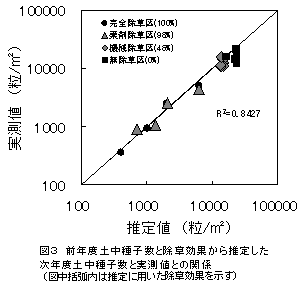
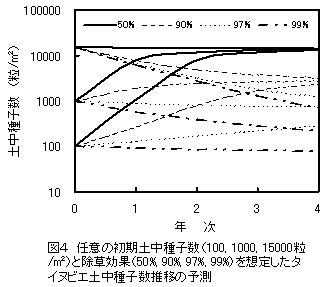
その他
- 研究課題名:積雪寒冷地におけるノビエの動態解明と要防除水準の策定
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2000~2003年度
- 研究担当者:渡邊寛明、内野彰、橘雅明
