リポキシゲナーゼ全欠失・サポニン組成改良大豆系統「東北151号」、「東北152号」の特性
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
「東北151号」および「東北152号」は、青臭みの原因となる大豆子実中のリポキシゲナーゼを全て欠失し、かつ、えぐ味の原因物質であるグループAアセチルサポニンあるいはソヤサポゲノールAが欠失している大豆系統である。実需者による豆乳および豆腐の官能評価は極めて良好である。
- キーワード:大豆、リポキシゲナーゼ、グループAアセチルサポニン、ソヤサポゲノールA、豆乳、豆腐、加工食品
- 担当:東北農研・水田利用部・大豆育種研究室
- 連絡先:電話0187-75-1043、電子メールsakat@affrc.go.jp
- 区分:東北農業・畑作物、作物・夏畑作物
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
大豆作付けが急増し販売価格が低下傾向にあるため、より付加価値の高い品種の育成とその用途開発が求められている。大豆加工食品、特に豆乳などで感じられる渋みやえぐ味等の不快味(収斂味)は満腹感を促し、量的摂取の制限要因となっており、リポキシゲナーゼ(L-1,2,3)により生じる青臭みと共にその改善が求められている。特に胚軸中に局在しているソヤサポゲノールAをアグリコンとするグループAサポニンが最も強い不快味を呈することが知られているため、グループAサポニン変異大豆とリポキシゲナーゼ全欠失大豆との交配による不快味の遺伝的低減化と、新規利用技術の開発を図る。
成果の内容・特徴
- 「東北151号」はリポキシゲナーゼ全欠失(L-1,2,3欠、以下、リポ全欠)の「刈系508号」を母、グループAアセチルサポニン欠失(A0型)の「0459F1」を父とし、「東北152号」は良質多収で病害虫抵抗性の「スズユタカ」を母、リポ全欠でソヤサポゲノールA欠失(A0S型)の「0564F2」を父とし、それぞれ選抜・固定を進めた系統である(表1)。成熟期は「東北151号」、「東北152号」の両系統とも比較品種の「スズユタカ」並の“中の晩”から“晩の早”にあたる。「東北151号」は劣性形質マーカーとして花色が“白”という特性を具えているため、圃場における他品種との交雑回避と特性維持が容易である。
- 「東北151号」の豆乳は負の味覚(えぐみ、青臭み等)が少なく、甘み・コクがありすっきりとして飲み易い。豆腐は「スズユタカ」より青臭み・渋みや不快味が少なく、甘みが感じられるなど実需者による官能評価は良好である(表2・3、図1a)。
- 「東北152号」の豆乳はクリーミーで甘み・コクに関する評価が高い。豆腐も「東北151号」と同等の評価である(表2・3、図1b)。
- 両系統を用いた豆乳は、負の味覚を低減させるための脱皮・脱胚軸工程を省略でき、イソフラボン等の機能性成分が高濃度で含まれる胚軸部分を活用できる。
成果の活用面・留意点
- 従来の大豆より不快味・不快臭の点で改善しており、新規加工利用の開発が期待できる。
- サポニン組成改良・リポキシゲナーゼ全欠失性大豆を用いた加工食品の製造に関する実需者との共同特許を日本、アメリカ合衆国、カナダに対し申請中である。
- サポニン組成・リポキシゲナーゼ全欠失の特性を維持するため、他品種との交雑や混種を回避する必要がある。
具体的データ
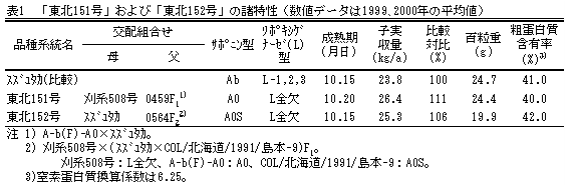
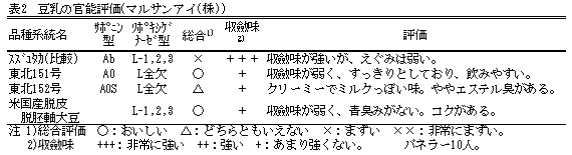
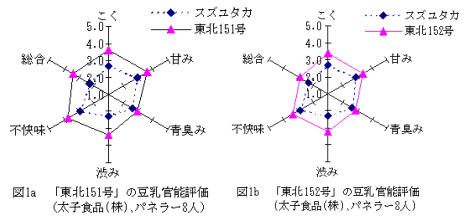

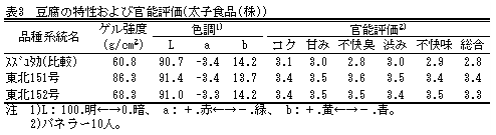
その他
- 研究課題名:だいずの新品種の育成
- 予算区分:新需要創出・交付金
- 研究期間:1998~2002年度
- 研究担当者:境 哲文、菊地彰夫、島田信二、高田吉丈、河野雄飛、国司功(太子食品)、手塚正教(太子食品)、
浅尾弘明(マルサンアイ)、都築公子(マルサンアイ) - 発表論文等:1)境ら(2002)特願2002-88449
