培養環境の段階的な酸素濃度調節によるウシ卵母細胞の発育の向上
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
直径約90∼100 µmのウシ卵母細胞を14日間培養して発育させる時、酸素濃度5%の環境で培養を始め、培養4日後に20%に切り替えると、効果的に卵母細胞を発育させることができ、体外受精後の胚発生も良好である。
- キーワード: 家畜繁殖、ウシ、卵母細胞、培養、発育、酸素濃度
- 担当:東北農研・畜産草地部・育種繁殖研究室
- 連絡先:電話019-643-3542、電子メールyujih@affrc.go.jp
- 区分:東北農業・畜産、畜産草地
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
ウシ卵巣内には多くの発育途上卵母細胞が存在するが、ほとんどは卵巣内で死滅する。培養技術を使って卵子にすることができれば優良 家畜の増産等に利用できる。最近、ウシ卵母細胞を育成する開放型培養システムが開発されたが、胚発生率はまだ低く、その向上が課題となっている。そのため には長期培養後の卵母細胞の生存率を高め、それと同時により多くの卵母細胞を生体内と同等まで発育させることが必要である。本研究では、培養細胞の健康状 態に大きく影響する酸素濃度に着目し、その調節を通して、効率的に卵母細胞を発育させる培養系を開発する。
成果の内容・特徴
- 直径約90∼100 µmのウシ卵母細胞と顆粒膜細胞の複合体を酸素濃度5%の低酸素環境で14日間培養すると、酸素濃度20%の高酸素環境で培養するよりも卵母細胞の生存率は有意に高いが、発育成績では高酸素環境が低酸素環境よりも有意に優れている(図表略)。
- 低酸素環境の問題点である発育の停滞は、培養5日後にはすでに起こっている。そこで、培養4日まで酸素濃度5%で培養した後、20%に切り替えて10日間培養すると、卵母細胞の生存率は低酸素と高酸素の成績の間の値となり(図1)、発育成績は良くなる(図2)。
- 酸素濃度5%で4日間培養し、続く10日間を20%で培養した卵母細胞を体外受精に用いることにより、効率よく胚盤胞が得られる(表1)。
成果の活用面・留意点
- 現在広く使われている卵子及び胚の培養法は、それぞれ酸素濃度20%と5%を基本とするものが多い。本培養系はその二つの培養設備の併用で実施することができる。
- 酸素濃度以外の主な培養条件は、4%ポリビニルピロリドン、5%ウシ胎子血清、ヒポキサンチン等を添加した培養液と、コラーゲンコート96穴組織培養プレートを使った開放型培養システムである。
具体的データ
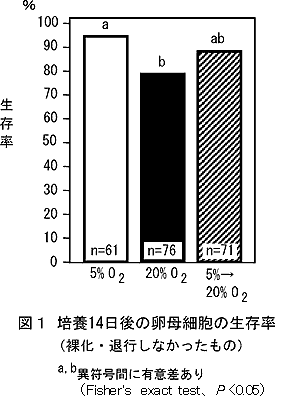
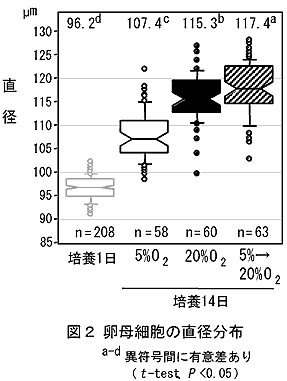
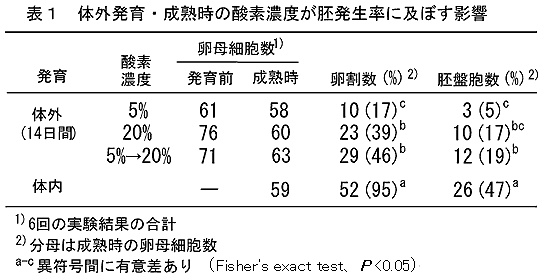
その他
- 研究課題名: 牛発育途上卵母細胞の培養技術の高度化
- 課題ID: 05-05-05-*-09-05
- 予算区分: 交付金
- 研究期間: 2002∼2005年度
- 研究担当者: 平尾雄二、志水学、伊賀浩輔、竹之内直樹
- 発表論文等: Hirao et al. (2004) Biol Reprod 70(1):83-91.
