ファイトレメディエーションにおけるカドミウムの動態と土壌酸性化の影響
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
生理的酸性肥料を用いてソルガムによる土壌修復を3年間行なうと、作土の塩酸可溶性カドミウム(Cd)と無機物結合性Cdは減少するが、水溶・交換性Cdは必ずしも減少しない。また、作土のpHが5以下になると、Cdの一部が作土次層へ移動・集積する。
- キーワード: カドミウム、ファイトレメディエーション、土壌修復、ソルガム、土壌pH
- 担当:東北農研・水田利用部・水田土壌管理研究室
- 連絡先:電話0187-66-2775、電子メールnkato@affrc.go.jp
- 区分:東北農業・生産環境(土壌肥料)、共通基盤・土壌肥料
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
カドミウム(Cd)は、土壌pHが低いほど可溶化し、植物に吸収されやすくなるので、ファイトレメディエーションの際には、生理的 酸性肥料や硫黄粉末の施用により、土壌を積極的に酸性化し、収奪効率を向上させることが望ましい。しかし、過度の酸性化は生育障害や土壌中Cdの溶脱を引 き起こすことが予想されるので、ソルガムを用いたファイトレメディエーションにおけるCd吸収量や土壌の形態別Cd濃度の推移、およびCdの下方移動の可 能性を異なる土壌pH条件下で明らかにする。
成果の内容・特徴
- ソルガムのCd吸収量はCd収奪の進行に伴い年々減少する(図1)。苦土石灰を施用しない低pH区では、1年目のソルガムのCd吸収量は他の試験区よりも多いが、3年目には連作による土壌の酸性化が著しいため乾物重が低下し、吸収量も少なくなる。
- ソルガムによるCd収奪に伴い、作土の塩酸可溶性Cdと無機物結合性Cdは大きく減少するが、水溶性・交換性Cdは、土壌の酸性化によって存在割合が増加するので、一定した減少傾向がみられない(図2)。
- 高pH区では、1年目は土壌pHの上昇による水溶・交換性Cdの減少と無機物結合性Cdの増加が見られるが、pHが低下する2年目以降は、他区との差は小さくなる(図2)。
- 低pH区と中pH区では、深さ15∼20cmの水溶・交換性Cdが修復前よりも増加したが、高pH区ではこのような現象は見られない(図3)。塩酸可溶性Cdでも同様の現象が認められる。一方、無機物結合性Cdは作土のみで減少し、下層土では変化しない。このことから、酸性化によって増加した作土の水溶・交換性Cdの一部がこの部位へ移動・集積したと言える。
- 酸性化の影響が少ない低pH区の25cm以下、中pH区の20cm以下、高pH区の15cm以下では、水溶・交換性Cd濃度が修復前よりも減少しており、ソルガムによるCdの収奪は少なくとも深さ30cmまで及んでいる(図3)。
成果の活用面・留意点
- ソルガムを修復植物としたファイトレメディエーションにおいては、Cdの下方移動を回避しつつ、安定したCd収奪を確保するために、土壌pHを5∼6の範囲で管理する。
- 作土のpHが5以下になった場合は、Cdが下方に移動するので、修復効果を評価するには、作土だけではなく、下層土を含めたCd濃度の推移を把握する必要がある。
具体的データ
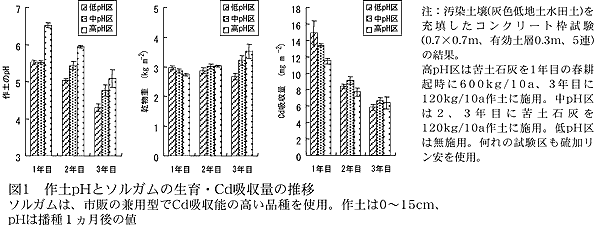
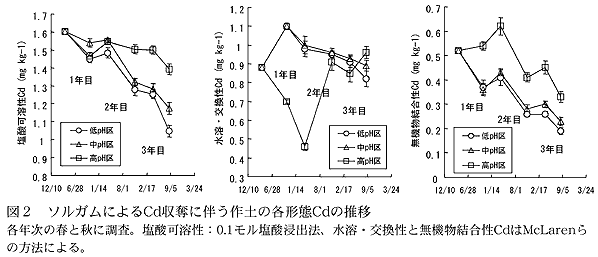
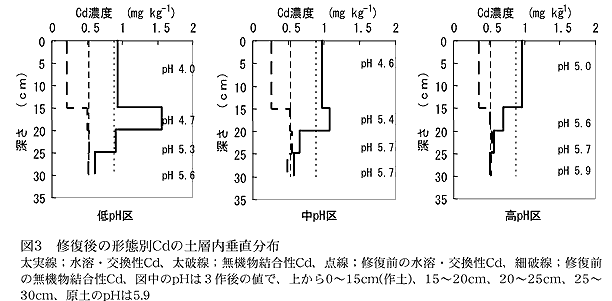
その他
- 研究課題名: Cd可溶化資材を利用した植物のCd吸収促進技術の開発
- 課題ID: 05-02-10-01-05-05
- 予算区分: 異分野融合研究(地域コンソーシアム)
- 研究期間: 2001∼2005年度
- 研究担当者: 加藤直人、関矢博幸、西田瑞彦
