玄米が極めて小さい紫黒米新品種「紫こぼし(奥羽紫糯389号)」
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
水稲「紫こぼし」は、東北地域に適する早生の紫黒米糯系統である。玄米は、粒長および粒幅が短く、千粒重は紫黒米「朝紫」の約半分で、極めて小さい。玄米にアントシアニジンを含むほか、「朝紫」や一般糯より食物繊維、カルシウム等を多く含む。
- キーワード:イネ、紫こぼし、極小粒、紫黒米、糯、東北地域
- 担当:東北農研・低コスト稲育種研究東北サブチーム
- 連絡先:電話0187-66-2773
- 区分:東北農業・作物(稲育種)、作物
- 分類:技術・普及
背景・ねらい
近年、食の健康志向や多様化を背景として高付加価値化を狙った多くの紫黒米及び赤米品種が育成されている。東北地域では既に普及 している紫黒米糯種の「朝紫」(1996年)に加え赤米糯種の「夕やけもち」(2006年)の作付けが拡大している。これらは玄米として販売されるだけで なく、菓子、日本酒、麺等の着色素材としても幅広く活用されている。さらに、極小粒種の「つぶゆき」(2003年)が育成され、その特徴的な食感から新し いタイプの調理飯の素材として活用されている。そこで、栄養成分が高く食感が特徴的な極小粒の紫黒米糯品種を育成する。
成果の内容・特徴
- 「紫こぼし」は、極小粒の「関東195号」と早生の紫黒米糯品種「朝紫」を1998年に交配し、その後選抜固定を図ってきた極小粒の紫黒米糯系統である。
- 出穂期と成熟期は、育成地では“早生の晩”に属する。短稈で倒伏に強く、脱粒しにくいため、一般品種と同様に機械化体系での栽培が可能である。生育期間を通じて葉縁等が紫色を呈し、また、ふ先色が紫色のため一般品種との識別は容易である(表1)。
- 耐冷性は“弱”、穂発芽性は“難”、いもち耐病性は葉いもちが“やや強”、穂いもちが“やや弱”である。粗玄米重は「朝紫」 の71%、「ヒメノモチ」の68%と低収であるが、極小粒の「つぶゆき」とは同程度である。玄米の粒長および粒幅が短く、千粒重は「朝紫」の54%、「つ ぶゆき」の71%と極めて小さい(表1、写真)。
- 「朝紫」の玄米より食物繊維、カルシウム、チアミン、ビタミンE等の含量が高く、「ヒメノモチ」との比較ではこれら成分に加えタンニン等の含量が高い(表1)。
- 着色米飯の食味は、「あきたこまち」白米に「朝紫」玄米を10%混米したものと比較して、同じ10%では「朝紫」より優れ、20%では同程度であるため、「朝紫」よりも多くの紫黒米を摂取しやすくなる。(表2)
成果の活用面・留意点
- 着色飯や雑穀飯をはじめとする調理飯のほか多様な料理や加工品の素材としての利用が期待されている。東北地域中南部の有色米取扱業者から強い要望があり、30ha程度の普及が見込まれている。
- 一般品種への混入を防ぐために、播種、移植時に種子や苗の混入に注意するとともに、収穫時、脱穀調製時にも専用機械を用いる等の対策が必要である。また、出穂期が近い一般品種の周辺では、自然交雑の可能性があるので注意する。
- 障害型耐冷性が弱く、いもち耐病性が不十分なため、栽培地域の選定に注意し、適正施肥、適期防除に努める。
- 播種量は、極小粒のため慣行より40%程度減らし、一箱あたり60~80gとする。
- 登熟期が高温になる地域では、玄米の着色が悪くなる恐れがあることに留意する。
具体的データ
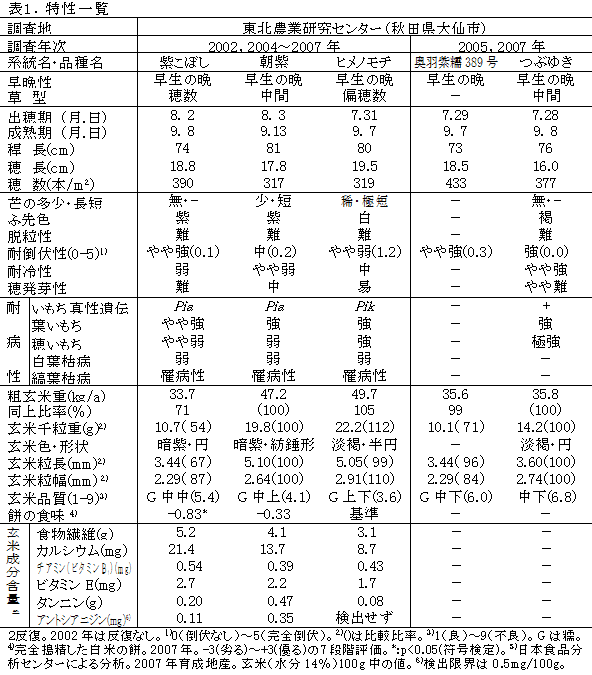
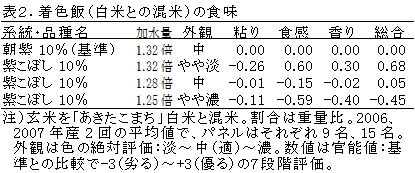

その他
- 研究課題名:直播適性に優れ、実需者ニーズに対応した低コスト業務用水稲品種の育成
- 課題ID:311-a
- 予算区分:委託プロ(加工プロ4系)
- 研究期間:1998~2007年度
- 研究担当者:山口誠之、片岡知守、遠藤貴司、中込弘二、滝田正、横上晴郁、加藤浩
