連用開始から5年間の完熟堆肥由来窒素の水稲吸収量と土壌残存量の推移
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
寒冷地水田では、連用開始から5年間の各年次施用の完熟稲わら堆肥、牛ふんオガクズ堆肥由来窒素の水稲による吸収量には大きな変化はみられない。施用された堆肥由来窒素の約7割以上が5作後の土壌に残存し、堆肥由来窒素の下方浸透による消失は少ない。
- キーワード:重窒素標識、稲わら堆肥、牛ふんオガクズ堆肥、寒冷地水田、イネ
- 担当:東北農研・東北水田輪作研究チーム
- 連絡先:電話0187-66-1221
- 区分:東北農業・基盤技術(土壌肥料)
- 分類:研究・参考
背景・ねらい
水田に施用された有機物の窒素収支については、近年重窒素標識有機物を用いた直接的な解析が進められてきているが、その事例は限 られており、特に寒冷地ではその事例はほとんどない。そこで、無標識の稲わら堆肥あるいは無標識の牛ふんを主体とする家畜ふん堆肥をそれぞれ5年間連用し て水稲を栽培するなかで、それぞれに年次別に重窒素標識稲わら堆肥と重窒素標識牛ふんオガクズ堆肥を施用して窒素収支を経年的に追跡する(表1、2)。
成果の内容・特徴
- 稲わら堆肥に由来する窒素の水稲による吸収量は0.3~0.6gN/m2年(単年施用量の3~6%)、牛ふんオガクズ堆肥では0.1~0.3gN/m2年(単年施用量の1~3%)と施用してからの年数や連用年数による大きな変化がみられない(図1)。
- 5作目における水稲による各年次施用の堆肥由来窒素吸収量の合計は、稲わら堆肥で1.7gN/m2(単年施用分の17%に相当)、牛ふんオガクス堆肥で1.5gN/m2(単年施用分の15%に相当)となる(図1)。
- 初年目に施用された稲わら堆肥の5作後の残存量は5.7gN/m2(単年施用量の57%)、牛ふんオガクズ堆肥では6.8gN/m2(単年施用量の68%)となり、5作後に土壌に残存する各年次施用の堆肥由来窒素の合計は稲わら堆肥で35gN/m2、牛ふんオガクズ堆肥で40gN/m2となる。これはそれぞれ全施用量に対して約70%および80%に相当し、堆肥由来窒素の多くが残存する(図2)。
- 初年目に施用された堆肥の有底枠と無底枠の未回収率の差から推定される下層への浸透による窒素の消失は、5年間の累計で4~5%と少ない(データ略)。
成果の活用面・留意点
- 重窒素標識した完熟堆肥を20年以上有機物無施用の細粒灰色低地土壌に施用して得た情報であり、堆肥由来窒素の水稲による吸収量や土壌への残存量は、気象、土壌、堆肥の性質等の条件に影響される。
具体的データ
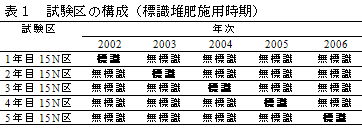
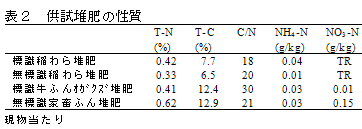
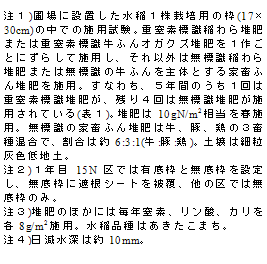
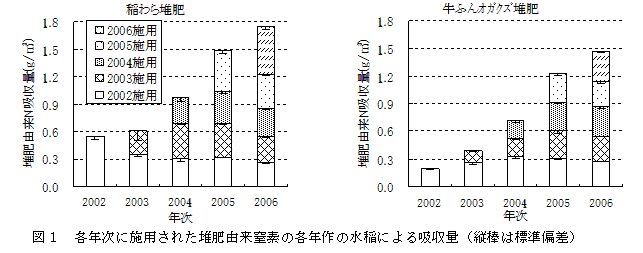
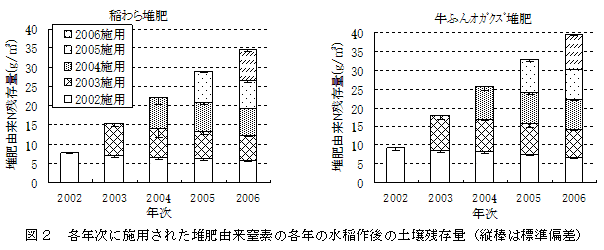
その他
- 研究課題名:
- 課題ID:211-k
- 予算区分:重点研究強化、交付金プロ(有機農業)
- 研究期間:2002年度、2003~2007年度
- 研究担当者:西田瑞彦、関矢博幸、加藤直人、住田弘一
地域条件を活かした高生産性水田・畑輪作のキーテクノロジーの開発と現地実証に基づく輪作体系の確立
