水稲の幼穂形成に及ぼす気温と水温の作用メカニズム
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
水稲の葉の分化は水温に依存する。あきたこまちでは7葉期以降、日長感応が始まり、それ以前の期間の長短は水温で決まる。7葉期以降、短日では日長感応が優先し気温影響は抑制される。長日では気温感応が顕著になり、高温で幼穂形成が促進される。
- キーワード:水稲、幼穂形成、日長感応、気温、水温
- 担当:東北農研・寒冷地温暖化研究チーム
- 連絡先:電話019-643-3462
- 区分:東北農業・基盤技術(農業気象)、共通基盤・農業気象
- 分類:研究・参考
背景・ねらい
頻発する異常気象や今後の温暖化に適応する技術体系の確立が求められている。作物の温度応答の中で、発育(開花や出穂の早晩)は 温度の高低に最も敏感に反応し、その早晩が異常高温・低温影響回避のポイントにもなっている。イネ品種の出穂早晩性は、これまで基本栄養生長性、感光性、 感温性という概念で整理されてきたが、どの部位の温度がどのように作用するかは明らかでない。最近、葉の日長感応シグナルが、生長点に形成された受容体に 届いて、花芽が分化することが明らかになった(Blázquez、2005、Science、309)。水稲では、幼穂形成期前後まで生長点が水中にある ため、受容体形成には水温が、また葉のシグナル形成には気温が作用すると考え、水温・気温・日長を制御した実験系を用いて、水温と気温の作用メカニズムを 明らかにする。
成果の内容・特徴
- 葉齢展開(葉の分化)速度は、水温に支配され、気温の作用を受けない(図1)。
- 7葉期前後まで日長に感応しない(図2)。また気温影響も7葉期以降に現れる(図3の第1作期)。
- 以上1,2から、生長点における受容体は7葉期前後に形成され、受容体形成までの期間(従来の基本栄養生長相)の長短は水温で決まる。
- 7葉期以降に始まる幼穂形成には、その間の日長と気温が作用する。日長が短いほど日数は短くなる。気温影響は短日で抑制され長日で増大する(図3の第2作期,図4)。長日下では高温で幼穂形成が促進される。
- 上の4から、葉における花芽分化シグナル形成に気温が関与し、その作用は日長の長短で異なると考える。
- 第1作期において、出芽から幼穂形成期までの日数は、水温を3℃高めると約13日、気温を4℃高めると約6日、それぞれ早まった。あきたこまちで通常の作期を想定すると、水温影響は約4.3日/℃、気温影響は約1.5日/℃であり、水温影響が3倍大きい。
成果の活用面・留意点
- 当成果は、あきたこまちで詳細に解析された結果であるが、コシヒカリやひとめぼれも6-7葉期まで日長に感応せず、それ以降長日下で気温影響が顕著になる。
- 日長感応を示さないきらら397では、日長に関わらず気温影響が現れる。但しその程度はわずかである。
- 水温は、日射や用水温、減水深、水管理などの影響を強く受けるので、気温-水温の関係は並行ではない。水管理による発育制御や水温推定モデルと組み合わせた発育予測法の開発に当成果を活用できる。
- 当成果は、温暖化に適応する品種の探索・導入、新品種の育成にも活用できる。
具体的データ
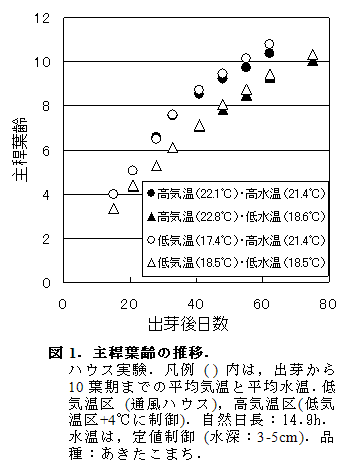
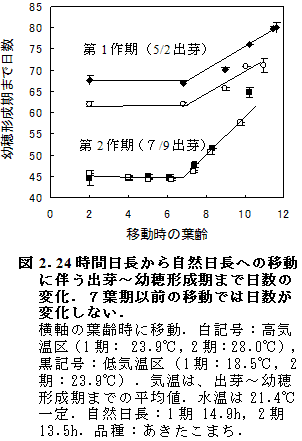
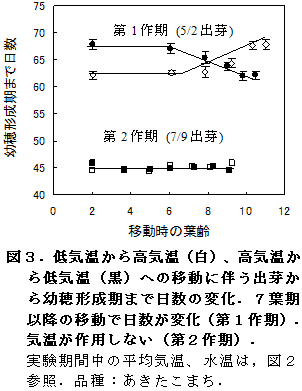
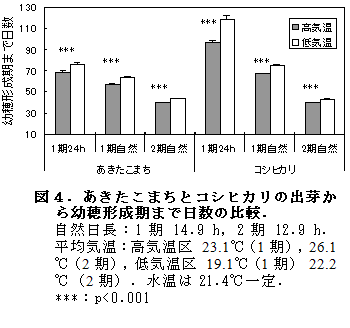
その他
- 研究課題名:寒冷地における気候温暖化等環境変動に対応した農業生産管理技術の開発
- 課題ID:215-a
- 予算区分:科研費
- 研究期間:2005~2007年度
- 研究担当者:長菅輝義、岡田益己
