ナタネを含む寒冷地水田輪作体系におけるナタネの耕種的雑草化防止策
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ナタネ刈り取り後、耕起した場合に比べ不耕起条件でナタネ落ち種の減耗は早い。ナタネ残さを移動させることで、さらに減耗は早まる。1ヶ月以上の湛水は、ナタネ種子を死滅させるのに有効で、1作の復田により90%以上が死滅する。
- キーワード:ナタネ、落ち種、雑草化、湛水、不耕起、残さ
- 担当:東北農研・東北水田輪作研究チーム兼雑草バイオタイプ総合防除研究チーム
- 代表連絡先:電話019-643-3433
- 区分:共通基盤・雑草、東北農業・作物(冬畑作物)、共通基盤・総合研究(輪作)
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
ナタネは、寒冷地の水田輪作体系への導入が可能なエネルギー作物として期待が大きいが、ナタネ栽培では機械化生産技術の体系化が遅れており、機械化栽培に対応した雑草管理技術も確立されていなかった。機械化ナタネ栽培においては、特にコンバインによる収穫損失によって散布された落ち種を発生源とする自生ナタネの雑草化が懸念されていた。本研究は水田輪作体系へのナタネの導入を可能とするため、自生ナタネの雑草化防止策の開発を目指し、ナタネ落ち種の生存に対する耕種管理の効果を明らかにする。
成果の内容・特徴
- ナタネ刈り取り後、夏期から秋期にかけて刈跡を不耕起状態で管理すると、耕起を行った場合に比べ、ナタネ落ち種の減耗は早い(図1A)。不耕起管理した刈跡でのナタネ落ち種の生存数は莢などの残さが集積しているウインドロウ部に多く、集積したナタネ残さをウインドロウ部からウインドロウ間に移動させることで落ち種の減耗はさらに早まる(図1B)。
- 夏期の湛水処理は土中ナタネ種子を死滅させるのに有効で、特に1ヶ月以上の湛水の有効性が高く(図2)、1作の復田により土中のナタネ種子の90%以上が死滅する(図3)。
- ナタネの雑草化防止の観点からは、ナタネ作翌年に水稲を作付ける体系が望ましい(図4)。復田が困難な場合は、夏作を休耕し不耕起管理することで一定の雑草化防止効果が期待できる。
成果の活用面・留意点
- ナタネを導入した水田輪作体系における自生ナタネの雑草化対策の要素技術として活用が期待される他、作付計画の策定の際の参考として活用が期待される。
- 無エルシン酸、低グルコシノレートのダブルロー品種キラリボシを用い、岩手県盛岡市の東北農業研究センタ-内で実施した実験の結果に基づく成果である。
- 不耕起管理した刈跡でのナタネ種子の減耗には、エンマコオロギ、ゴミムシ類などの摂食が関与していることから、これら種子食性昆虫の生息密度が低い条件での不耕起管理の有効性については明らかでない。
具体的データ
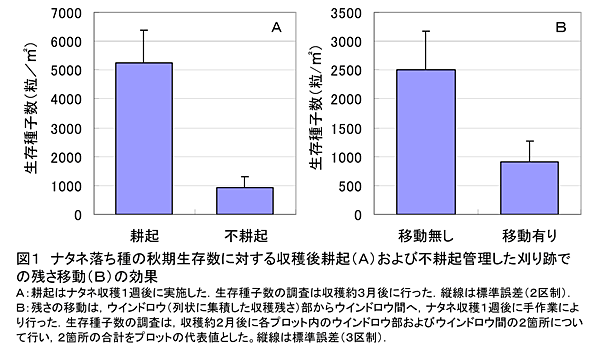
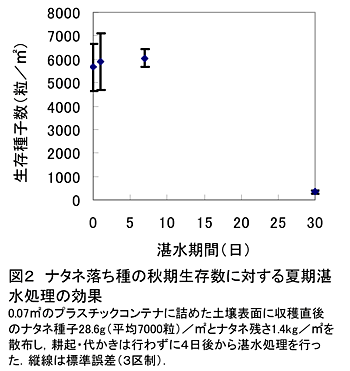
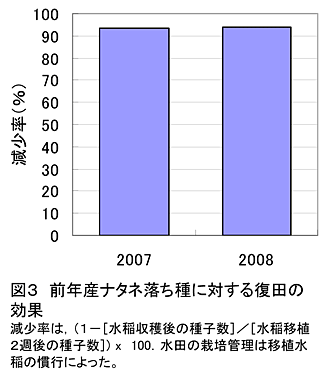
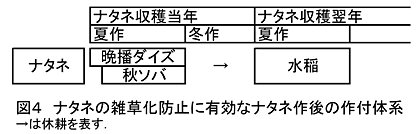
その他
- 研究課題名:難防除雑草バイオタイプのまん延機構の解明及び総合防除技術の開発
- 課題ID:214-b
- 予算区分:交付金プロ(油糧作物)、基盤
- 研究期間:2005-2008年度
- 研究担当者:中山壮一、澁谷幸憲、天羽弘一、橘雅明、西脇健太郎、大谷隆二
