東北地域の飼料用稲栽培におけるタイヌビエの許容残草量
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
東北地域の飼料用稲栽培において、圃場生産物の減収、生産物水分の上昇による発酵品質の低下およびタイヌビエの埋土種子量の増加を防止する許容残草量は、8月下旬の収穫では乾物重で151 g/m2、9月中旬の収穫では10 g/m2と推定される。
- キーワード:タイヌビエ、飼料用稲、許容残草量、水分含有率、埋土種子数
- 担当:東北農研・東北飼料イネ研究チーム
- 代表連絡先:電話0187-66-2771
- 区分:東北農業・作物(稲栽培)、共通基盤・雑草
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
東北地域の飼料用稲栽培においてタイヌビエは問題となる雑草の一つである。しかし、飼料用稲栽培では、食用米栽培と異なり、収穫物に混入したタイヌビエが飼料となり得るため、許容される残草量は明確でない。適切な雑草防除の水準を明らかにする目的で、1)圃場生産物(イネ+タイヌビエ)の収量が減少しない、2)発酵品質の低下を防ぐために圃場生産物の水分含有率を65%以上にしない、3)次年度の繁殖源となる埋土種子の数が増加しない、という3つの条件を設定し、タイヌビエの許容残草量を推定する。
成果の内容・特徴
- タイヌビエの混入による圃場生産物(イネとタイヌビエの合計乾物重)の減収は認められない(図1)。
- タイヌビエの水分含有率は、8月下旬以降9月中旬までの期間に徐々に減少するが、9月中旬でも65%以下にはならない(図2)。タイヌビエが混入しても圃場生産物の水分含有率が65%以上とならない残草量の上限は、収穫日が遅くなるに従い多くなり、8月下旬では乾物重で151 g/m2、 9月中旬では455 g/m2となる(図3)。
- タイヌビエの稔実率は、8月下旬から9月中旬にかけて高くなり(図4)、種子生産数も多くなる。タイヌビエの埋土種子数が増加しない残草量の上限は、収穫日が遅くなるに従い少なくなり、8月下旬では乾物重で205 g/m2、 9月中旬では10 g/m2となる(図3)。
- 減収の防止と発酵品質の低下の防止およびタイヌビエの埋土種子数の増加防止という3つの条件の全てを満たすタイヌビエの許容残草量は、8月下旬の収穫では乾物重で151 g/m2、 9月中旬の収穫では10 g/m2となる(図3)。
成果の活用面・留意点
- 飼料用稲栽培におけるタイヌビエの許容残草量を設定する際に参考となる。
- 本成果は秋田県大仙市の東北農業研究センター場内圃場で「ふ系飼206号」、「べこごのみ」、「ふくひびき」、「べこあおば」を供試して得られた結果である。
- 成果の内容は、倒伏のない試験条件下で得られたデータを基にしている。多量のタイヌビエの残草は倒伏を助長する場合もあることに留意する。
具体的データ
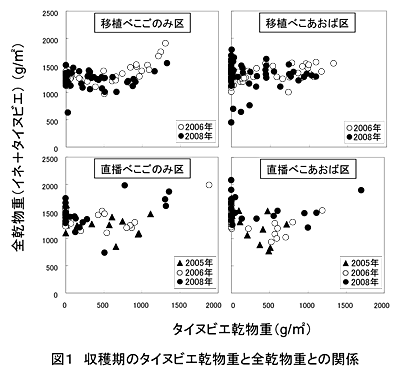
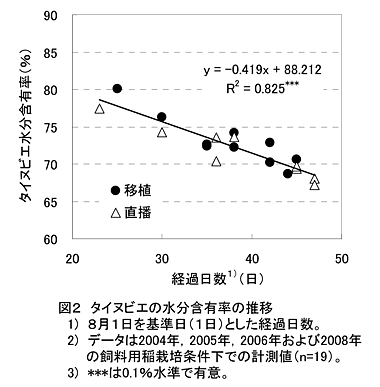
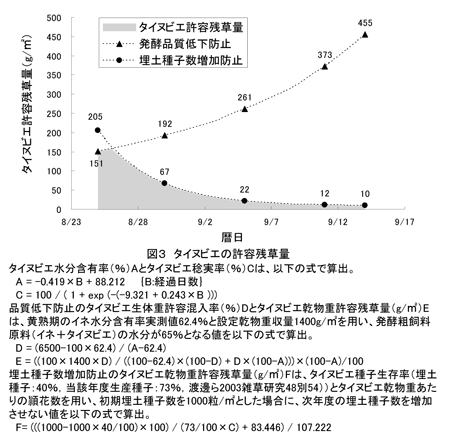
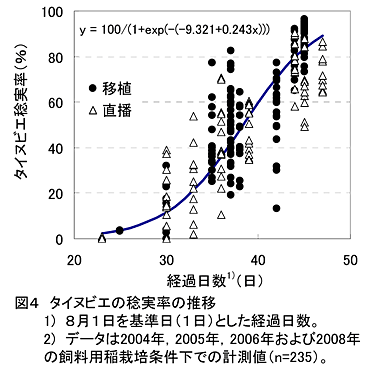
その他
- 研究課題名:東北地域における水田高度利用による飼料用稲生産と耕畜連携による資源循環型地域営農システムの確立
- 課題ID:212-b.1
- 予算区分:基盤、委託プロ(えさ)
- 研究期間:2004~2008年度
- 研究担当者:橘 雅明、中山壮一
