小型データロガーを利用したウシの採食・反芻時間測定装置
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
安価で自作可能な本装置は舎飼いされるウシの咀嚼行動を長時間にわたり記録できる。咀嚼インターバルの分布記録から採食、反芻および舐め行動等を迅速に判別し、その時間を算出することができる。
- キーワード:ウシ、咀嚼、反芻、小型データロガー
- 担当:東北農研・東北飼料イネ研究チーム
- 代表連絡先:電話019-643-3556
- 区分:東北農研・畜産、畜産草地
- 分類:研究・参考
背景・ねらい
反芻行動はウシの特徴的な行動であり、また、採食時間と反芻時間は粗飼料の物理性を評価する際の重要な項目の一つである。しかし、舎飼いのウシの採食時間と反芻時間を計測するには高価な装置或いは多大な労力を要する。そこで、長時間の咀嚼行動の記録ができる安価で自作可能な装置を開発し、迅速な採食と反芻行動の解析方法を目指したものである。
成果の内容・特徴
- 咀嚼時間の測定装置はエッジスイッチ(図1中のア)、小型データロガー(イ, Onset Computer Corporation社製 HOBO data logger )と動作確認のためのモニタとしての市販の歩数計(ウ)で構成される(図1,本装置を以後SCRUM:Sequential Chewing and Rumination Measuring Systemと称する)。頭絡に組み込んだエッジスイッチはウシの下顎の動きに伴い、開口時にON、閉口時にOFFとなる。小型データロガーはエッジスイッチのONになった時刻を記録する。ウシへの装着は一人で極めて容易にできる。
- 小型データロガーには図2のデータが記録される。
- 2より得られたON時刻のインターバル(秒)を表計算ソフトにより計算処理することにより、採食、反芻および舐め行動等の判別に必要なデータが得られる(図3)。
- 観察法とSCRUM法による記録から、給餌後、2秒以下のインターバルが連続する波形が採食行動(図3-a)、2秒以下のインターバルの連続上に20秒以下のインターバルが規則的に生じる波形が反芻行動(図3-b)、インターバルが不連続・不規則的な波形が舐め行動等(図3-c)と定義する。
- 観察法(ビデオ解析による)と本法の24時間測定結果の採食時間、反芻時間は供試牛1、2と4では10分以下の差である。粗飼料価指数(RVI)でも同様、わずかな差である。観察法では反芻となめ行動が混在する個体は熟練した観察者でも判別が困難である。しかし、SCRUM法 では容易に判別できる(表1)。
成果の活用面・留意点
- 本装置は一台(総重量300g)につき約25千円(PCおよび表計算ソフト等は除く)と安価に制作が可能である。
- 本装置は粗飼料の物理性評価に有効である。
- 本装置の使用部品、製作、ウシへの装着およびデータの解析方法の詳細は東北農研ホームページ(http://www.naro.affrc.go.jp/tarc/symple_blog/scrum/index.html)より入手可能である。
具体的データ
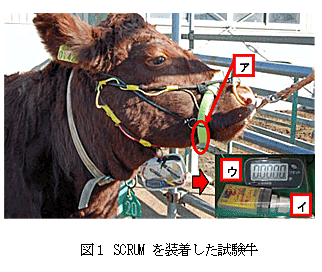
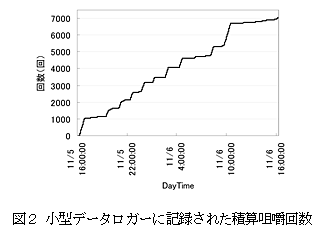
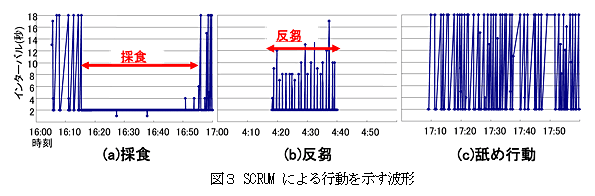
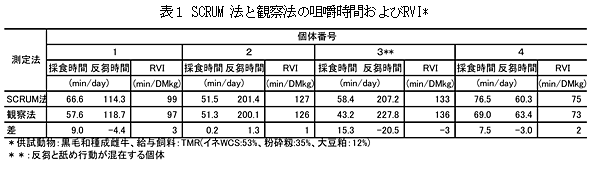
その他
- 研究課題名:東北地域における水田高度利用による飼料用稲生産と耕畜連携による資源循環型地域営農システムの確立
- 課題ID:212-b.1
- 予算区分:基盤(所内活性化)
- 研究期間:2008年度
- 研究担当者:福重直輝、小松篤司、大谷隆二、河本英憲、押部明徳
