窒素量の日調節による養液栽培トマトの個体群葉面積制御
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
窒素施用量の日調節による、施設内環境の変化に対応した養液栽培トマトの個体群葉面積制御法を開発した。
- 担当:野菜・茶業試験場 施設生産部 気象環境研究室
- 連絡先:0569-72-1166
- 部会名:野菜・茶業
- 専門:農業気象
- 対象:果菜類
- 分類:研究
背景・ねらい
果菜類の養液栽培に関し、最大収量や高品質を得るための個体群葉面積の形成と維持管理の研究は、葉面積制御が難しく解析が遅れている。また、施設環境の変化に対応した個体群葉面積の制御は、現在の養液栽培法ではほとんど不可能である。そこで、培養液による養液栽培トマト個体群の葉面積制御法を開発する。
成果の内容・特徴
- 窒素を毎日個体当たり1~6mg施用したトマトは、各窒素区とも第5果房収穫期が定植7月後の1993年3月20±3日であり、葉数34~35、茎長 2.3~2.5mで、斜め誘引により高さ2mの個体群を構成し、各花房の開花・収穫日、葉数および茎長の窒素施用量による差異は小さかった。この個体の生 葉数(暖候期25、寒候期28)が一定に管理されると個体及び個体群の葉面積は窒素施用量に応じて増加する(表1)。一方、窒素以外の培養液濃度(電気伝導度:EC)の差(1~6)による葉面積の変化幅は、窒素施用量による葉面積の変化幅と比較し小さい(表2)。
- 上記の結果を利用し、個体群の葉面積制御法は以下のとおりにする。 1)目標の葉面積個体群を形成するには、第1花房開花期から表3を参考に窒素施用量を順次増量し、各果房3果をつけた健全な第5花房開花期の個体を養成する。第5花房から第8花房の開花期にかけて表4に示す窒素施用量に漸次調節、以後調節を継続し、第5花房収穫期に目標とするLAI:1~4、高さ2mの葉面積個体群を形成する。 2)個体群の葉面積を維持するには、毎日施用する窒素量を、開花花房から下位1~3果房の着生果数が9より多いと増し、開花花房を付ける茎径が収穫期果房の茎より太ければ減じ、開花花房を付ける節間の長さが収穫果房の節間長より長ければ増す。
- 本方法にて管理したトマト個体群(LAI:4)の生産構造図(図1)は、 新葉の伸長・展開がほぼ終わる床面からの高さ140~155cm層の生葉重が、高さ40~55cm層にいたる各層の生葉重にほぼ等しく、新規に展開する葉 面積量と古葉の除去量が長期間均衡することを示している。すなわち、本個体群の葉面積は長期間一定に維持されることを示す。
成果の活用面・留意点
- 本成果は、現在トマトの長段養液栽培について最大収量や高品質を得るための個体群葉面積の解析や適正管理の研究に活用されている。本方法の原理は、養液栽培される果菜類の個体群葉面積の制御維持に応用できる。
具体的データ
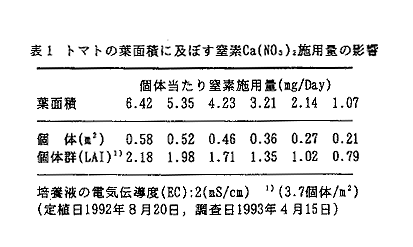
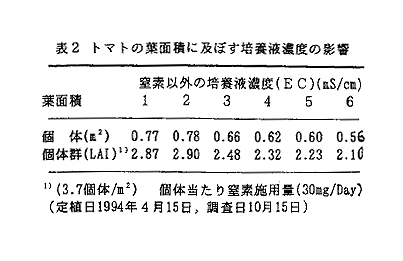
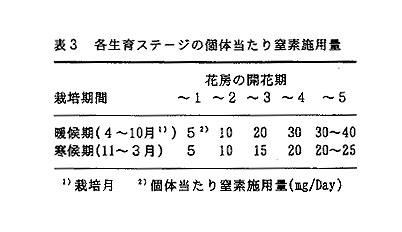
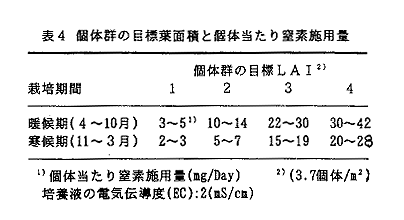
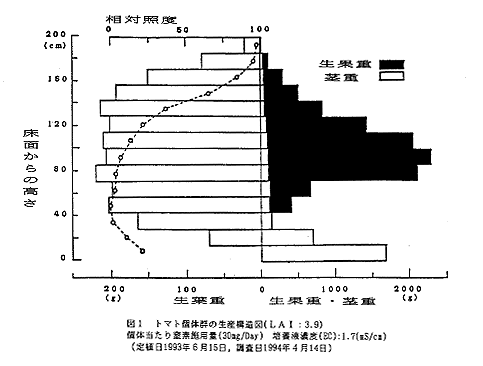
その他
- 研究課題名:気象・地象環境の変動が野菜の収量および品質に及ぼす影響
- 予算区分 :経常・重点基礎
- 研究期間 :平成6年度(平成4~6年)
- 発表論文等:窒素少量分肥と養液濃度を用いた養液栽培トマトの生育制御法.
施設園芸,平成6年9月号,1~3,1994
