トマト受光体勢の適正制御による環境保全型・多収・周年養液栽培
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
窒素施用量の日調節による葉面積制御栽培システムの活用により、トマト個体群の受光体勢適正制御を図ると、過繁茂にならず通年培養液交換が不要で、栽培終了時にも施設の外へ窒素排出がなく環境保全型で多収の周年養液栽培が可能である。
- キーワード:葉面積制御栽培システム、受光体勢適正制御、環境保全型、多収、周年養液栽培
- 担当:野菜・茶業試験場施設生産部環境制御研究室
- 連絡先:0569-72-1596
- 部会名:野菜・茶業、生産環境
- 専門:農業気象
- 対象:トマト
- 分類:指導
背景・ねらい
我が国のトマト養液栽培は、暖候期栽培が高温のため非常に困難であり、寒候期を中心に栽培され、気象資源が高度に活用されているオランダと比較し年間収量 が少なく生産性は著しく劣る。そこで、すでに開発した窒素施用量の日調節技術の自動化を図り葉面積制御栽培システムを構築し、それを用いて我が国の低軒高 施設でも可能な、環境保全型で暖候期の豊富な日射・温度資源を活用したトマト周年・多収養液栽培法の開発を試みた。
成果の内容・特徴
- 葉面積制御栽培システム(図1)で は、窒素施用量(Ca(NO↓3 )↓2 )の日調節をタイマ-を用い定量ポンプの稼働時間制御により行う。一方、ECとpHは、NとCa以外の必須要素を含む培養原液及びNaOHとHClを用 い、トマトの生育に合わせEC:0.5~2、pH:5~6の範囲でセンサ-により自動調節する。
- 葉面積制御は、トマトの生育に合わせ窒素施用量(個体)を毎日調節して遂行する。すなわち、個体あたり日窒素施用量は定植時(第1花房 開花期)の3mgから始め、肥大を終えた主茎の直径が13mmになるように順次増して、各果房3果を付けた第5花房開花期個体群を育成する。第5~8花房 の開花期にかけて個体群の葉面積指数(LAI)を時々調査し、目標LAIと比べその多少から毎日の窒素施用量を調節する。以降、栽培が終るまでこれを繰り 返す。
- 高さ2m個体群が多収を達成するための適正なLAIは、暖候期4~5,寒候期3~4である(図2)。このLAIでは、成熟過程の果実に木漏れ日があたる程度である。
- 第8花房開花期以後LAIの制御目標を4、小型で揃った35枚程度の本葉が付く主茎を高さ2mに保ち斜め誘引した個体群を形成し、気象資源が豊富な暖候期を中心に周年養液栽培すると、年間収量は30トン/10アール達する(表1)。
- 本システムが稼働し、高さ2m、LAI:3~4のトマト個体群が生育する施設では、換気扇の稼働と植物の蒸発散(7.5トン/10アール/日)により、盛夏期の気温は40°C以上にならず(表1)、養液温度30°C環境にてトマトの根は健全に生育し、果実の日焼けなど温度障害はない。
- 本システムは、培養液交換が不要であり、窒素(硝酸態)は供与後2~3時間で全て吸収され、栽培終了後も施設の外へ窒素排出がなく環境保全型である(表2)。窒素施用の制限に伴い他要素の吸収が抑制され、従来型の養液栽培と比べ肥料使用量(効率)の改善も図られている。
成果の活用面・留意点
本システムは、品質・収量の栽培目標を養液濃度(EC)と供与窒素量の調節により果実糖度3.5・収量32トン~糖度7・収量10トン/10アール/年の範囲で変えることができる。
具体的データ
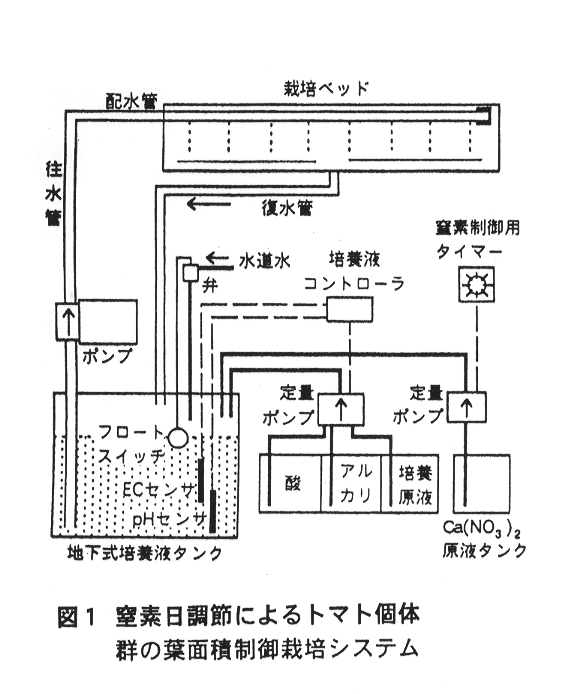
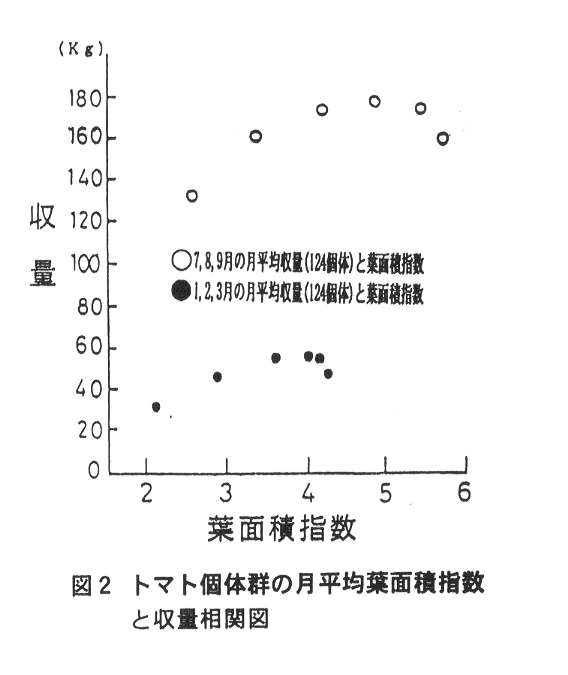
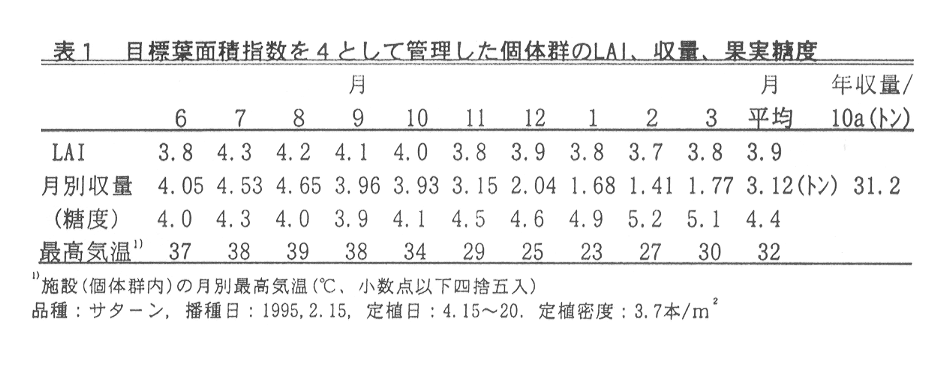
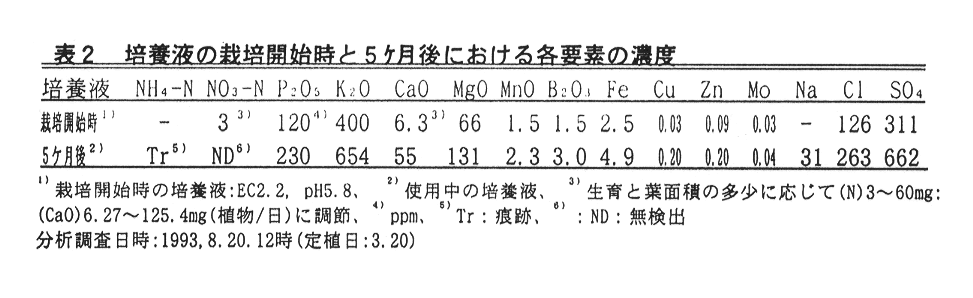
その他
- 研究課題名:気象・地象環境の調節による作物の葉面積制御に基づく施設野菜の栽培管理法
- 予算区分:経常
- 研究期間:平成9年度(平成3~7年、7~13年)
- 研究担当者:細井徳夫
- 発表論文等:
1)細井徳夫(1994):窒素量の日調節による養液栽培トマトの個体群葉面積制御.野菜・茶業研究成果情報,平成6年度,pp.13~14.
2)細井徳夫(1997):トマト個体群の持続的維持が可能な葉面積調査法.農業気象東海支部会誌,55,13~16.
