強酸性茶園土壌からの亜酸化窒素生成機構
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
亜酸化窒素は、土壌pHが低く、窒素施肥量が多い茶園土壌から多量に生成する。また、亜酸化窒素は硝酸化成反応と脱窒反応から生成し、細菌だけでなく、糸状菌も関与している。
- キーワード:亜酸化窒素、土壌pH、窒素施肥量、茶園土壌、糸状菌
- 担当:野菜・茶業試験場茶栽培部土壌肥料研究室
- 連絡先:0547-45-4101
- 部会名:野菜・茶業
- 専門:土壌
- 対象:茶
- 分類:研究
背景・ねらい
亜酸化窒素はオゾン層の破壊と温室効果による地球温暖化に関与する微量ガスで、国際的にもその生成量の削減が求められている。酸性化した土壌環境では亜酸化窒素生成量が増加するとされているが、強酸性化した茶園土壌では調べられていない。そこで、茶園土壌からの亜酸化窒素生成量を室内実験で測定し、その生成機構を明らかにすることで、亜酸化窒素生成量削減技術の開発のための基礎資料とする。
成果の内容・特徴
- 肥培管理の異なる茶園から採取した土壌の亜酸化窒素生成量を比較すると、同一府県から採取した土壌の間では、土壌pHが低く、窒素施肥量が多い茶園の土壌ほど生成量は多い(表1)。
- 亜酸化窒素は土壌中では、硝酸化成と脱窒から生成することが知られている。硝酸化成阻害剤であるニトラピリンを加えた場合、亜酸化窒素生成量は無添加土壌の80%に低下する(図1)。このことは、茶園土壌からは硝酸化成と脱窒の両方から亜酸化窒素が生成するが、脱窒が主要反応であることを示している。
- 硝酸化成、脱窒ともに、一般には土壌細菌が行っている。しかし、抗細菌性抗生物質であるクロラムフェニコールを加えた場合に比べ、抗真菌性抗生物質であるシクロヘキシミドを加えた場合の亜酸化窒素生成量の低下が大きいことから、茶園土壌における亜酸化窒素生成には糸状菌の関与が大きい(図2)。
成果の活用面・留意点
- 圃場での亜酸化窒素生成量削減技術開発のための基礎的知見となる。
- 地球温暖化に対する茶園土壌由来の亜酸化窒素の寄与を考える場合、圃場での生成量を測定する必要がある。
具体的データ
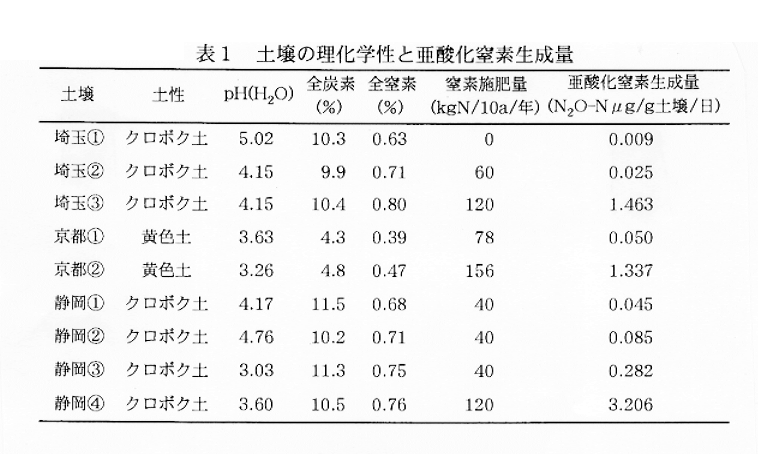
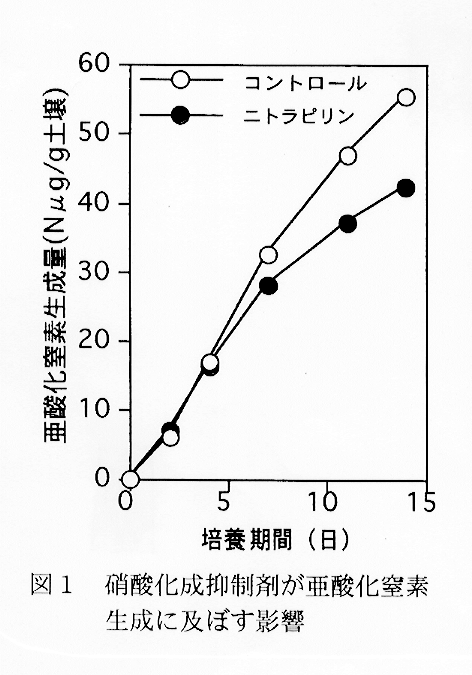
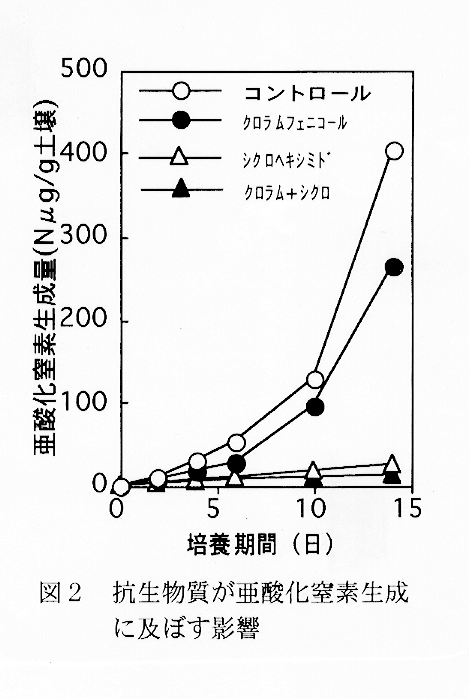
その他
- 研究課題名:茶園土壌からの亜酸化窒素生成機構の解明
- 予算区分:経常
- 研究期間:平成9年度(平成7~9年)
- 研究担当者:徳田進一・加藤忠司
- 発表論文等:なし
