スイカ果実汚斑細菌病菌の植物からの検出を目的とした選択培地
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
スイカ果実汚斑細菌病菌(Acidovorax avenae subsp. citrulli)の検出を目的とした選択培地・AacSMを開発した。AacSMは選択性と識別性に優れ、種子や発病植物から本病原細菌を分離・検出するのに適している。
- キーワード:Acidovorax avenae subsp. citrulli、スイカ、果実汚斑細菌病、選択培地
- 担当:野菜茶研・果菜研究部・病害研究室
- 連絡先:059-268-4641
- 区分:野菜茶業・野菜生産環境
- 分類:行政・参考
背景・ねらい
1998年に我が国で発生が確認されたスイカ果実汚斑細菌病は、アメリカで甚大な被害をもたらした種子伝染性の病害である。このため、本病の国内での蔓延と海外からの再侵入を防止するために病原細菌・Acidovorax avenae subsp. citrulli (以下Aac)の検出技術の開発が必要である。選択培地は、生きている病原細菌を分離・検出することが出来ることから主要な細菌性病害で開発され、植物検疫現場、研究現場などで使用されてきた。しかし、本病原細菌に対しての優秀な選択培地は開発されていない。そこで、植物検疫、発生生態の解明などの研究での使用を目的とした選択培地を開発する。
成果の内容・特徴
- Aacの細菌学的性質を調査し、これに基づいて無機塩を主体とした選択培地・AacSMを開発した。
- AacSMの組成は以下の通り。
KH2PO4 0.5g、Na2HPO4・12H2O 2.0g、(NH4)2SO4 2.0g、アジピン酸二アンモニウム 10g、酵母エキス 10mg、MgSO4・7H2O 29mg、CaCl2・2H2O 67mg、 Na2MoO4・2H2O 25mg、BTB 12.5mg、寒天 15g、蒸留水 1000 ml、pH7.0~7.2。高圧滅菌(121℃、15分)後にアンピシリン 20mg、フェネチシリンカリウム 100mg、ノボビオシン 2mg、シクロヘキシミド 25mgを無菌的に添加する。 - AacSMを用いて36℃~40℃で培養した場合、Aacは3日後に特徴ある集落を形成する(図1)。
- AacSMを用いた場合、Aac培養菌の回収率は60~100%である。また、古い病斑から分離した場合、通常の増菌培地と比較して効率よくAacを分離することができる(表1)。
- AacSMは、ほとんどの植物部病原細菌の生育を阻止するが、一部のイネ褐条細菌病菌(A. avenae subsp. avenae)菌株は集落を形成する。
- AacSMの選択性は高く、土壌、種子および植物体上に生息する99%以上の細菌の集落形成を阻止する(表2、3)。
- 本培地を使用して40℃で培養することでより高い選択性を得ることができる(表2、3)。
成果の活用面・留意点
- 本選択培地は、植物検疫、種子生産における幼苗検定、発生予察、発生生態などの場面で利用できる。
- 本選択培地上での集落の識別を修得するまでは、Aacを陽性対象として使用する。
- フェネチシリン、ノボビオシンを添加しない場合のAacの回収率は100~120%であり、新しい病斑や比較的きれいな種子から分離する場合など高い選択性を要求しない場合は、これらの抗生物質を添加しないで使用できる。
具体的データ

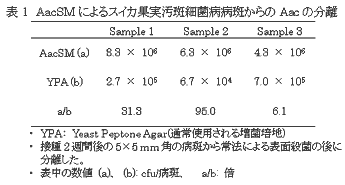
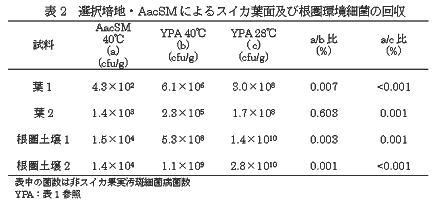
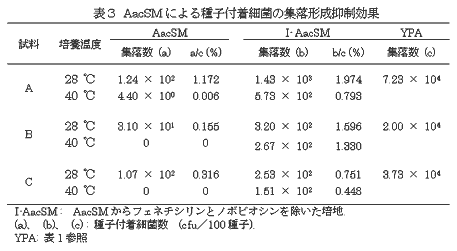
その他
- 研究課題名:病原細菌の種子および発病個体からの高感度検出法の確立
- 予算区分:行政対応特別研究(スイカ細菌病)
- 研究期間:1999~2001年度
- 研究担当者:白川隆、合澤雅夫(那覇植防)、小宮友紀子、我孫子和雄
- 発表論文等:1) 白川・我孫子(1999)日植病報 65(3):359(講演要旨).
2) 白川ら(2000)日植病報66(2):132(講演要旨).
