熱水土壌消毒を導入したメロン栽培
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
熱水土壌消毒を導入することにより、つる割病、黒点根腐病、根こぶ線虫病などの発生を抑え、安定したメロン生産が可能である。熱水土壌消毒によりメロンの生育は旺盛となり果実は大型化する。糖度や味に影響はない。
- キーワード:熱水土壌消毒、メロン、つる割病、黒点根腐病、根こぶ線虫病
- 担当:野菜茶研・果菜研究部・病害研究室、九州沖縄農研・地域基盤研究部・上席研究官、
熊本農研セ・農産園芸研究所・病虫部、鹿児島農試・病虫部、鹿児島県大崎農改 - 連絡先:電話059-268-4641、電子メールnishikaz@affrc.go.jp
- 区分:野菜茶業・野菜生産環境、九州農業・病害虫
- 分類:技術・普及
背景・ねらい
メロン栽培現場では土壌病害が多発し、臭化メチルやクロルピクリンなどによる土壌消毒が広範に実施されている。しかし近年は、農薬の使用をできるだけ減らした栽培を求める声が高くなってきており、加えて主要な土壌消毒剤である臭化メチルは、2005年以降は使用できなくなる見込みで、農薬に頼らない新しい土壌消毒技術が求められている。そこで熱水土壌消毒法を導入したメロンの栽培技術を確立する。
成果の内容・特徴
- 熱水土壌消毒を実施することにより、メロンの主要病害であるつる割病、黒点根腐病、根こぶ線虫病の発生を抑え,安定した生産をあげることが可能である(表1~3)。また、土壌中に埋没している白絹病菌や菌核病菌の菌核も死滅させる。
- 熱水土壌消毒後のメロンは、初期生育が旺盛となり果実は大型化することが多い(表4)。細根はよく発達し、根毛は慣行の臭化メチルやクロルピクリンによる土壌消毒を実施した場合よりも多く形成される。糖度や味は、慣行栽培と差がない。
- 熱水注入量は150/m2以上とするが、対象病害虫の種類や土質・土性、地温などの環境要因を考慮して決定する。熱水土壌消毒の実施には季節的な制限が少なく、少なくとも九州地域の平野部では厳冬期でも実施可能である。
- 熱水土壌消毒後定植までに必要な最短期間は、土壌水分が作業機械の運転に支障のないレベルに低下するまで,あるいは土壌水分が定植に好適な水準となるまである。消毒後定植までの期間が長くなっても、消毒効果は長期にわたって(少なくとも4ヵ月間)維持される。
成果の活用面・留意点
- 熱水土壌消毒の効果は、透水性の悪い圃場や傾斜している圃場では発揮されにくい。
- 土壌伝染性ウイルス病に対する熱水土壌消毒の効果については、未検討である。
- 熱水土壌消毒後は生育が旺盛となる傾向にあるので、施肥管理に留意する。
具体的データ
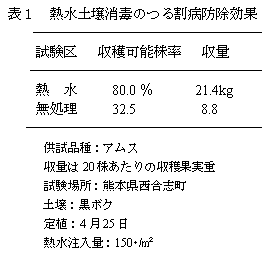
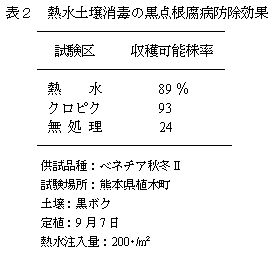
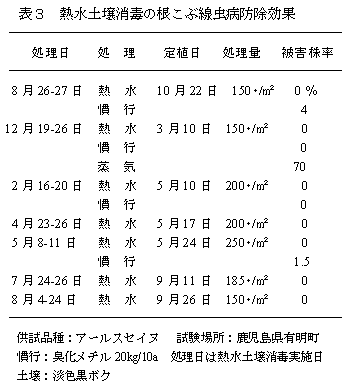
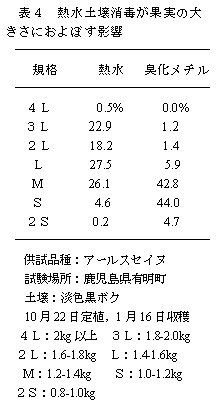
その他
- 研究課題名:熱水消毒、抵抗性台木等による土壌病害防除技術の実証
- 予算区分:IPM
- 研究期間:2002~2003年度
- 研究担当者:西 和文、佐藤 衛、窪田昌春、山崎宏滋(大崎農改)、森山美穂(熊本農研セ)、
江口武志(熊本農研セ)、横山 威(熊本農研セ)、野島秀伸(鹿児島農試)、中島 隆(九州研) - 発表論文等:1)西(編)(2002)熱水土壌消毒・その原理と実践の記録 日本施設園芸協会 185p
