キャベツ市販種子の黒すす病菌汚染実態
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
キャベツ市販種子から黒すす病菌が高率に分離され、殺菌剤処理によって分離率は半減しているものの、なお、6~11%の汚染が見られる。また、採種地域別では、東海以西産の種子では黒すす病菌分離率が高い傾向がある。
- キーワード:キャベツ、種子伝染、黒すす病
- 担当:野菜茶研・果菜研究部・病害研究室
- 連絡先:電話059-268-4641、電子メールkubota@affrc.go.jp
- 区分:野菜茶業・野菜生産環境
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
キャベツのセル成型育苗では高温期に糸状菌病害である黒すす病の被害が大きい。本病では地上部に病斑が形成され、茎部や頂芽が侵された場合には立ち枯れや生育不良となる。また、本病は種子伝染することが知られており、同一ロットの種子由来のほとんど全ての株に何らかの病徴が認められた場合もある。ここではキャベツ市販種子の汚染状況を調査する。
成果の内容・特徴
- 10℃以下で保存されてきた1984~2001年産のキャベツ市販種子の各ロットから100粒ずつを素寒天上で24°C、6日間培養すると、56~100%のロットから糸状菌が分離され、黒すす病菌については33~90%のロットから分離される。殺菌剤処理されたロットでは、いずれの年代でも全糸状菌、黒すす病菌が分離されるロットの割合は低い(図1)。
- 種子からの糸状菌分離率は7~37%、黒すす病菌については6~21%であり、保存期間が長い種子ほど全糸状菌、黒すす病菌の分離率は低下する(図2)。また、殺菌剤処理された種子では全糸状菌、黒すす病菌の分離率が低下する。
- 殺菌剤非処理のロットを生産地域別にグループ分けすると、黒すす病菌が分離される種子の割合が40%以上となるロットは東海以西で認められ、平均の分離率も東海以西産で14%以上、関東、北信越では4%未満である(図3)。
成果の活用面・留意点
- 黒すす病菌の有効な防除薬剤はないが、育苗時における底面給水法は本病の発病拡大を抑制する(平成13年度研究成果情報)。
具体的データ
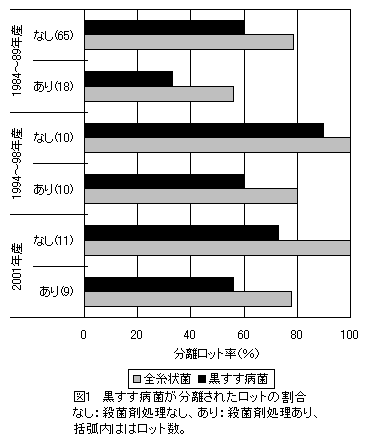
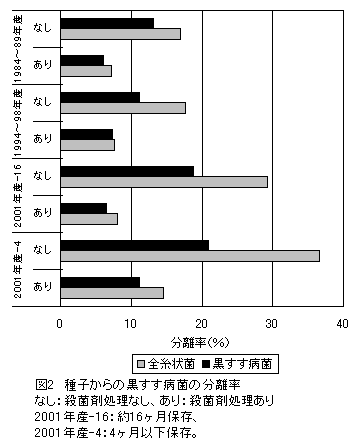
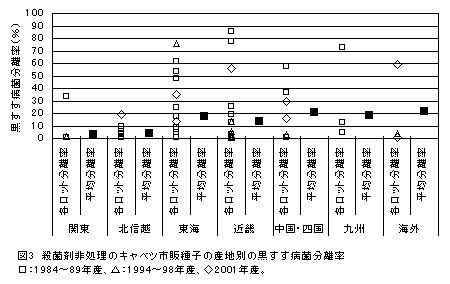
その他
- 研究課題名:野菜のセル成型育苗における病害防除技術
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2001~2002年度
- 研究担当者:窪田昌春、西和文、我孫子和雄、栁澤幸雄(群馬西部農業総合事務所)
