トマト養液栽培における水中根と湿気中根の形態および窒素吸収の差異
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
トマトの養液栽培において、水中根は分枝の少ない小さな根系となるが、湿気中根は分枝根および根毛が発達し大きな根系となる。同一根系内に湿気中根と水中根を併せもつ植物体では、窒素吸収能および地上部への流出量は水中根が湿気中根よりも大きい。
- キーワード:トマト、養液栽培、根系形態、窒素吸収
- 担当:野菜茶研・果菜研究部・栽培システム研究室
- 連絡先:電話0569-72-1490、電子メール yuka88@affrc.go.jp
- 区分:野菜茶業・野菜栽培生理
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
養液栽培において、根の一部を湿気中に露出させると生育が安定することが知られている。湿気中と水中では水分、温度、酸素など多くの物理・化学的条件にお いて差異があるが、それらが根の機能や形態に及ぼす影響は明らかではない。そこで、培養液中に浸漬して発達した根である「水中根」と,湿ったシート上に発 達して空気中に露出している根である「湿気中根」について,トマトを用いて外部・内部形態および養分吸収の違いを明らかにする。
成果の内容・特徴
- 地上部の成長は湿気中根をもつ植物体と水中根をもつ植物体で同程度であるが、根の成長は湿気中根が水中根よりも旺盛であり、湿気中根をもつ植物体は地上部重/地下部重比が小さい。
- 側根のフラクタル次元(構造の見た目の複雑さを表す尺度)は湿気中根で水中根よりも大きく、湿気中根では分枝根が発達していることを示す(図1)。
- 湿気中根は水中根に比べて根毛の発生数が多く(図2)、根の原生木部道管、皮層細胞層、中心柱の直径が増大し、外皮におけるリグニン沈着がみられる。
- 同一根系内に湿気中根と水中根を併せもつ場合、水中根は窒素吸収能と地上部への流出量が大きい。一方、湿気中根は根量が大きいものの単位乾物重当たりの窒素吸収能は小さく、水中根の吸収した窒素が多く流入する(図3)。
成果の活用面・留意点
- 単位根重当たりの湿気中根の養水分吸収能は水中根よりも小さく、湿気中根では根量の大きさによってその機能が補償されると考 えられる。湿気中根を形成させる毛管水耕、パッシブ水耕などの養液栽培方式について、根系が水平方向に拡大できるよう、湛液水耕の場合よりも大きな容量と する。
- トマトの湿気中根と水中根の両方を形成させる養液栽培では、湿気中根への養水分供給が不足しないように管理する。
具体的データ
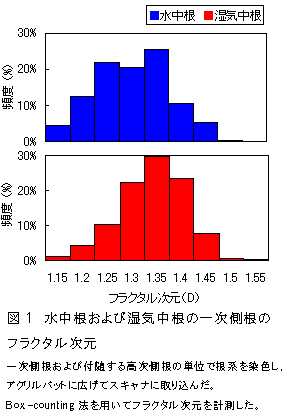
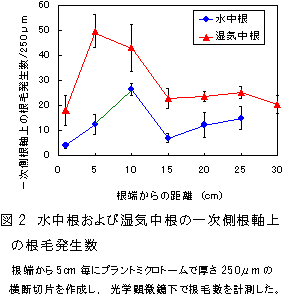
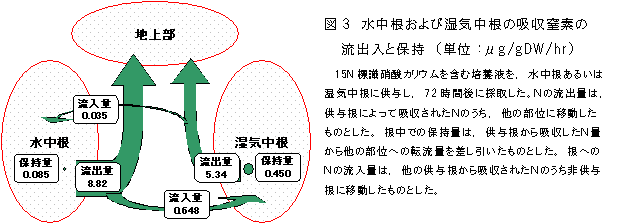
その他
- 研究課題名:養液栽培における根系形態と機能の解析
- 課題ID:11-05-04-01-06-02
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2000~2002年度
- 研究担当者:中野有加、岡野邦夫、渡辺慎一、高市益行、川嶋浩樹
- 発表論文等:
1)中野ら(2003)園学雑 72(2):148-155.
2)中野ら(2003)園学雑 72(2):156-161.
