茶葉の熟度の違いによる抗酸化能の変化
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
β-カロテン-リノール酸法及びDPPHラジカル捕捉法に基づく茶の抗酸化能は、熟度が進むにつれて減少し、エステル型カテキン類含有量との間に強い正の 相関がある。摘採晩期の茶葉から製造した荒茶では、摘採初期のものよりリノール酸抗酸化能は約6割、DPPH捕捉能は約1割程度減少する。
- キーワード:チャ、抗酸化能評価、熟度、エステル型カテキン類、EGCG
- 担当:野菜茶研・機能解析部・茶品質化学研究室
- 連絡先:電話 0547-45-4982、電子メール kks914@affrc.go.jp
- 区分:野菜茶業・茶業
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
茶が抗酸化能を有し、中でもカテキン類が強い抗酸化能を示すことがよく知られている。一方、カテキン類の総量は茶葉の熟度 が進むに従って減少することも知られているが、エピガロカテキンガレート(EGCG)とエピカテキンガレート(ECG)のエステル型カテキン類が減少する のに対し、エピガロカテキン(EGC)とエピカテキン(EC)の遊離型カテキン類は増加するなど、必ずしも増減は一定ではない。そこで、抗酸化能測定法と して、β-カロテン-リノール酸法(リノール酸抗酸化能)及び1,1-Diphenyl-2-picrylohydrazylラジカル捕捉法(DPPH捕 捉能)を取り上げ、抗酸化能が熟度によってどの程度変化し、熟度がかなり進んだ茶葉でもどの程度抗酸化能が確保されるかを明らかにする。
成果の内容・特徴
- リノール酸抗酸化能とDPPH捕捉能は、茶生葉乾燥試料(生葉を電子レンジでブランチング処理し、乾燥させたもの)及び荒茶試料の双方において、熟度が進むに従い減少する(表1と図1)。
- 摘採晩期の茶葉から製造した荒茶(5月7日製造)では、摘採初期の茶葉から製造した荒茶(4月22日製造)と比較して、リノール酸抗酸化能では6割程度(表1)、DPPH捕捉能では1割程度減少する{図1-(b)}。リノール酸抗酸化能での減少が大きい。
- リノール酸抗酸化能とDPPH捕捉能は、エステル型カテキン類(EGCG + ECG)との間に強い正の相関があり、中でも、EGCGとの間には強い相関がある。この相関は、アスコルビン酸(AsA)を加えることでわずかながら強くなる傾向にある(表2)。
成果の活用面・留意点
- リノール酸抗酸化能とDPPH捕捉能以外の抗酸化能については、今後検討する必要がある。
- 抗酸化能の減少割合は、製茶条件により変動する。
具体的データ
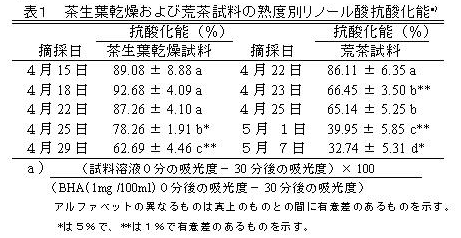
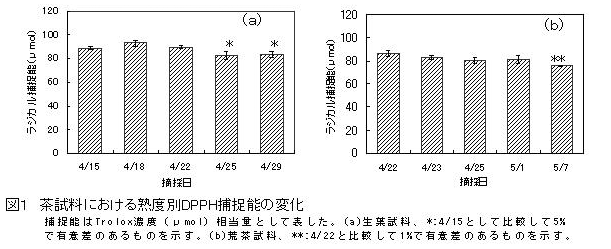
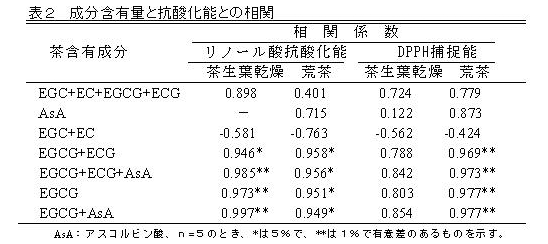
その他
- 研究課題名:茶含有製品の機能性評価に基づく健全性評価法の開発
- 課題ID:11-10-04-01-06-03
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2001~2003年度
- 研究担当者:木幡勝則、氏原ともみ、林宣之、堀江秀樹
- 発表論文等:1) 木幡ら (2004):茶研報、96、63-68
2) 木幡ら(2004):茶研報、96、69-74
