チャ品種「べにふうき」における中切り後の再萌芽の特徴
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
茶園で樹高を低くするために行われる中切り処理後の再萌芽数増加には、大きな品種間差異が認められる。「べにふうき」の再萌芽数の増加は、「やぶきた」より遅く、再萌芽数増加が比較的遅い「ゆたかみどり」に比べてもさらに遅い。
- キーワード:チャ、茶園、中切り、再萌芽、べにふうき
- 担当:野菜茶研・茶生産省力技術研究チーム
- 代表連絡先:電話0547-45-5190
- 区分:野菜茶業・茶業
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
茶園では年々上がって行く樹高を低くするため、数年に一度全葉層を刈り落として樹高を下げる「中切り」作業が行われている。この中切りによって茶園は管理作業に好適な樹高に維持される。一方、すべての葉層が刈り落とされるため、中切り後の再萌芽とその後のスムーズな葉層再生が翌年以降の茶の生産安定にとって重要である。中切り後の再萌芽には品種間で遅速があることが経験的に知られていたが、多品種を比較したデータは今まで無い。また、最近新植が増えているチャ品種「べにふうき」は、もともと紅茶用品種として育成されたため、枝条の生育特性が主力品種「やぶきた」とは大きく異なっており、摘採や整枝等の栽培管理が再萌芽や葉層再生に及ぼす影響の予測が難しい。そこで、中切り後の葉層再生を規定する主要な要因である再萌芽の遅速について、「やぶきた」等他品種との比較により品種間差異を明確にし、「べにふうき」の適切な栽培管理に役立てる。
成果の内容・特徴
- 中切り後の「べにふうき」の再萌芽開始は他品種に比べると遅い(図1)。再萌芽開始後の再萌芽数増加も「やぶきた」に比べ大幅に遅れる(図2)。中切り後の再萌芽数増加が遅い「ゆたかみどり」に比べても「べにふうき」の再萌芽数増加はさらに遅い(図1)。
- 中切り1ヶ月後の再萌芽数をもとに品種を区分すると、「べにふうき」は再萌芽の最も遅い品種群に属し(表1)、葉層の再生も遅れる(図2)。
成果の活用面・留意点
- 定植9年目の野菜茶業研究所金谷茶業研究拠点内茶園において、2008年一番茶後の5月15日に地表面から約50cmの高さで中切りを行って得られたデータである。
- 個々の茶園における「べにふうき」の再萌芽の遅速は、栽培地帯や気象条件、樹齢や栽培管理前歴などによって変動するが、品種間差異は基本的に変わらないと考えられる。
- 「べにふうき」をはじめて中切りをする場合には、前年度に一部の株で予備的に中切りを行って、再萌芽の経過とその後の葉層再生に関連する生育反応を十分に把握しておくことが肝要である。
- 「べにふうき」を中切りする場合には、一番茶摘採後なるべく速やかに実施することにより、再萌芽後の葉層再生期間をなるべく長く確保する必要がある。
具体的データ
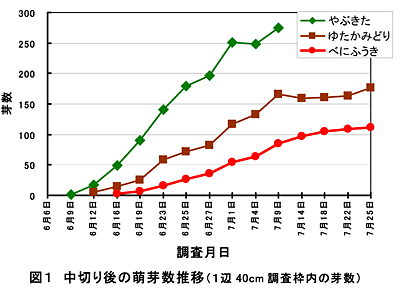

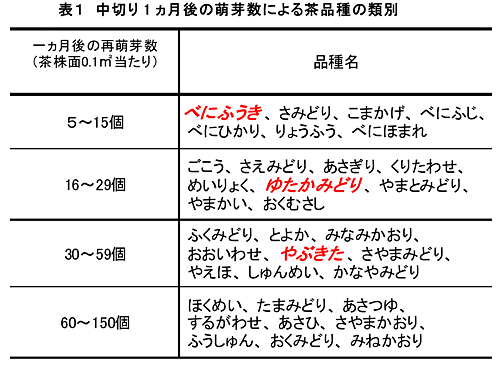
その他
- 研究課題名:生体情報及び高度センシング技術による茶の省力栽培・加工技術の開発
- 課題ID:223-b
- 予算区分:基盤研究費
- 研究期間:2006~2008年度
- 研究担当者:松尾喜義、岡本毅、荒木琢也
