イネもみ枯細菌病苗腐敗症の発生機構
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
イネもみ枯細菌病苗腐敗症の発生は、感染の場における病原細菌の病原力とその周辺の、病原に対して抑制的に働く微生物との相互関係により支配される。本病の特徴である日和見的発生の機構も、このことから説明できる。
- 担当:中国農業試験場 生産環境部 病害研究室
- 連絡先:0849-23-4100
- 部会名:生産環境
- 専門 :作物病害
- 対象:稲類
- 分類:研究
背景・ねらい
イネもみ枯細菌病菌による苗腐敗症の発生生態に関する一連の研究は,本病の発生に関与する重要要因として,発病抑制能を持つ微生物の存在を示している(平成5年度成果情報)。この推論をさらに補強し、本病の発生機構を解明する。
成果の内容・特徴
- 同一の汚染籾でも、ある範囲の浸種粒数では、浸種容器により発病程度が異なる。この場合、播種粒数の多少はほとんど発病程度に影響しない。発病程度の異なる2つの容器から籾を1粒ずつ取り出し接触させ播種すると,容器の組み合わせにより苗はともに発病するか、発病しないか、どちらかとなる傾向が強い。
- 低温での浸種は、本病の発病に有利に働く。高温浸種では、浸種籾数が増加すると、発病率が低下する(図1)。これは、籾数の増加とともに強い抑制力を持った微生物を保持している籾の混入数が多くなるためと考える。
- 特定の汚染籾を30または100粒づつ別々に浸種・播種した汚染籾からの発病は、全苗発病または健全のいずれかに分かれる傾向が強い(表1)。全苗発病分と全苗健全分の残った籾と浸種液を混ぜ合わせた後,籾粒の一部を取り出して播種すると,発病程度は全苗発病または健全のいずれかに分かれる(表2)。
- 本病に対して強い発病抑制能を持つPseudomonas属細菌4株が,籾の浸種液等から得られている(平成7年度成果情報)。
- 上記の諸事実から、病原細菌と抑制能を持つ微生物(主体は細菌と考える)は,ともに籾粒により偏在するが,浸種時にともに増殖・拡散し、播種後には近隣の籾への拡散が起こり、最終的に発病するか否かは、感染の場における病原菌と抑制能を持つ微生物間との相互関係(病原性または抑制能と増殖量の合わさったもの)により決まると考える(図2)。本病の特徴である日和見的発生も、この考え方で説明できる。
成果の活用面・留意点
本病の生態的・耕種的新防除技術の開発に有用な基礎的知見として活用が期待できる。
具体的データ
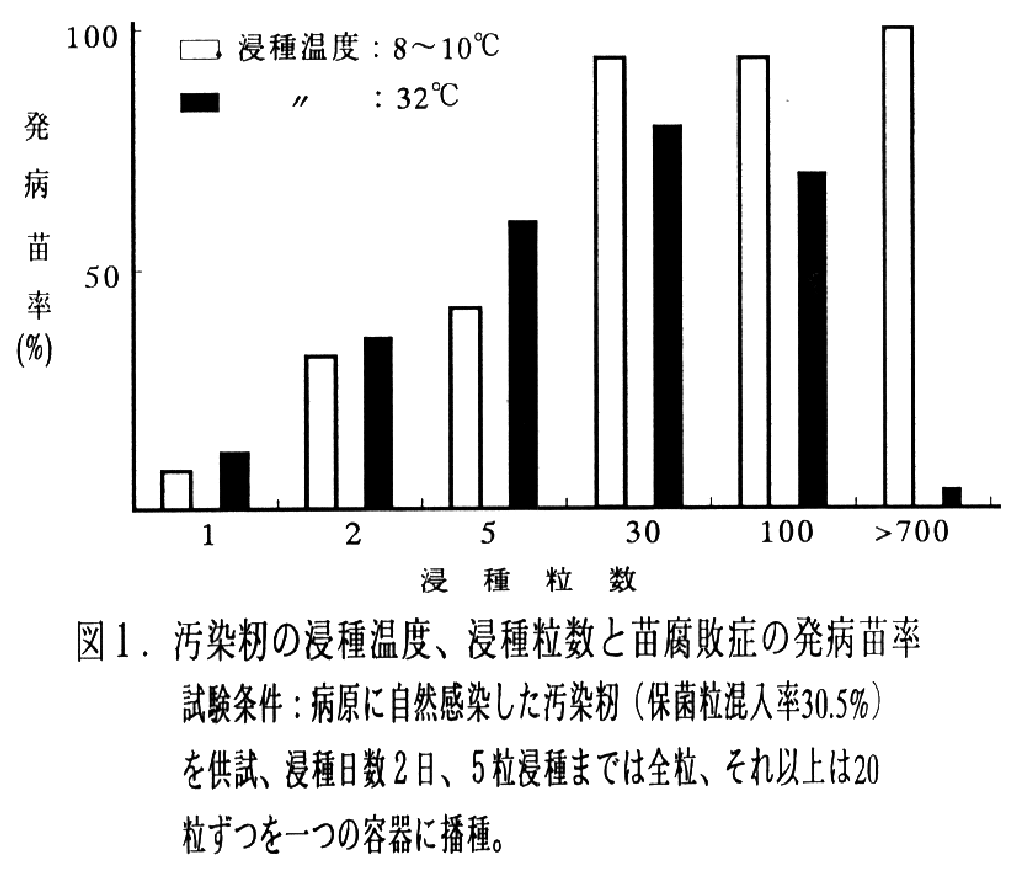
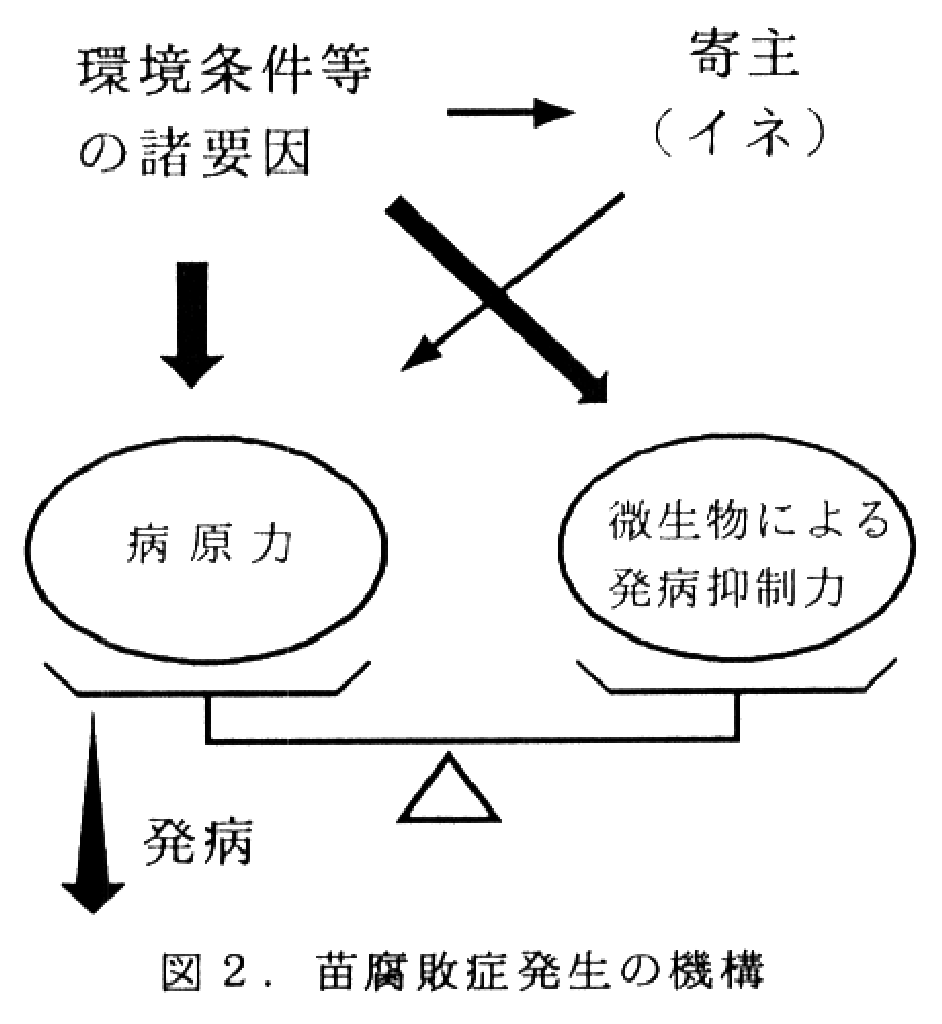
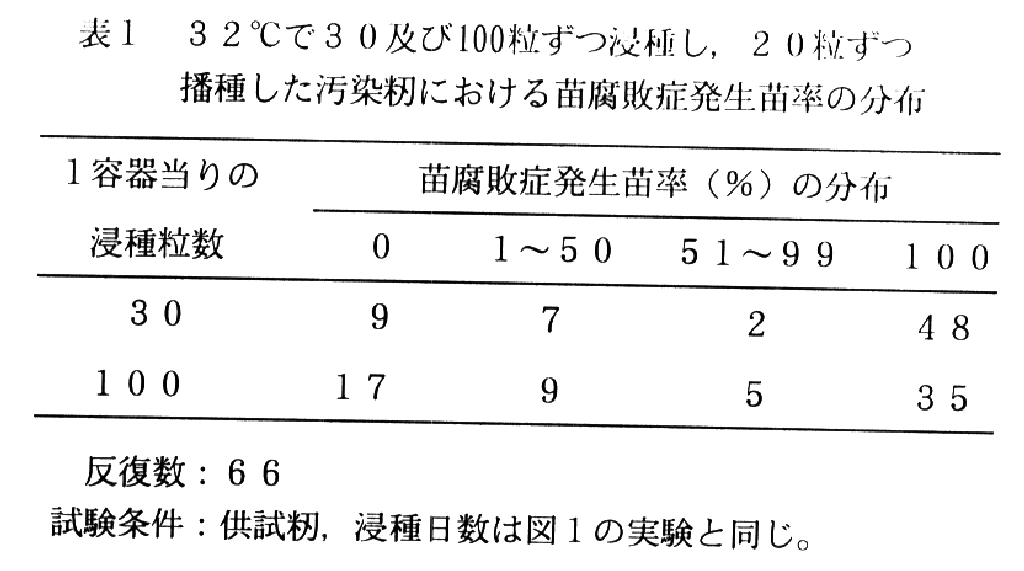
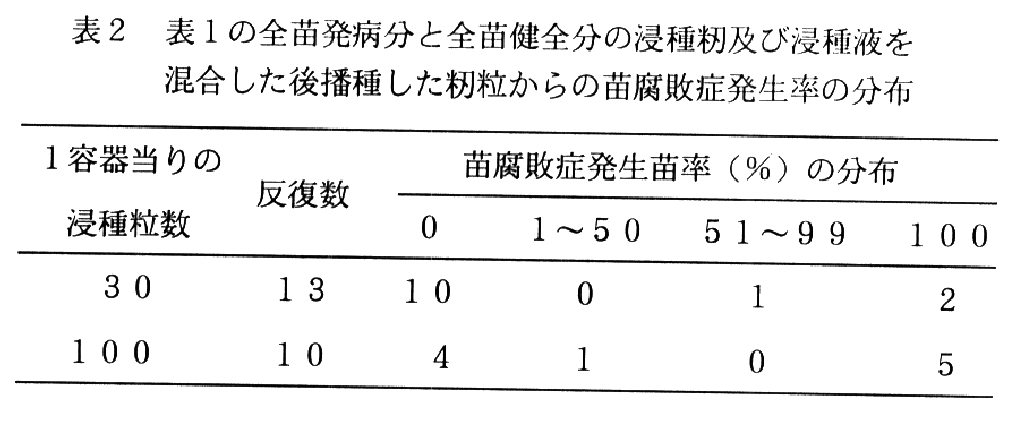
その他
- 研究課題名:水稲種子伝染性細菌病制御技術の開発
- 予算区分:経常
- 研究期間:平成7年度(昭和62~平成(6)7年)
