ススキ型草地における放牧牛を用いた防火帯作りの省力化技術
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
火入れ予定のススキ草地の外縁部を電気牧柵でベルト状に囲い、肉用繁殖牛を放牧させて草を採食させることで、極めて省力的に防火帯を創り上げることができる。
- キーワード:生態、野草類、放牧、防火帯、半自然草地、火入れ
- 担当:近中四農研・畜産草地部・草地飼料作物研究室
- 連絡先:0854-82-1962
- 区分:近畿中国四国農業・畜産草地
- 分類:技術・普及
背景・ねらい
火入れ、採草、放牧などの人為的管理によって維持される日本の半自然草地は、省力・低コストな畜産資源としてのみならず、我が国に希有なすぐれた景観、自然史的・文化的遺産、貴重な動植物の生息地、レクリエーション空間としての重要性が指摘されている。しかし、草地を利用する農家の減少と高齢化は、それらの維持管理を困難にしつつある。とくに、火入れ前に準備する防火帯作りは、草刈り機を用いた危険な作業であるため、各地で継続が危ぶまれている。
この問題を解決するため、島根県大田市の国立公園三瓶山では、ススキ型草原を対象に平成10年(1998年)より、放牧経験牛による防火帯作り(通称モーモー輪地)が試みられている。ここでは、この技術を広く全国に普及するため、その有効性を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 移動式電気牧柵を用い、火入れ予定草地の外縁部の防火帯部分を幅10~40m、長さ約1000mの防火帯部分をベルト状に囲い、その中に春、秋それぞれ1~4回程度、放牧経験のある肉用繁殖雌牛を放牧させることで、極めて省力的に防火帯を作り上げることができる(図1)。
- 防火帯の外の火入れ草地はススキ主体の長草型草地で、秋期には群落高は144cm、地上部乾物重は1540kg/10aにも達するが、防火帯内では放牧牛の採食によって草丈12cm、乾物重108kg/10aに抑えられ、ススキの株は数年でほとんど消滅する(表1)。可燃物量の少ない防火帯部分は、火入れの際の火勢を十分に抑えられる
- 放牧地として囲った防火帯は、可燃物量が少ないだけでなく、幅が広いので、火入れの際の消火作業の安全性も高まる。したがって、作業に不慣れな火入れ支援ボランティアなどの参加、受け入れも容易になる。
- 放牧による防火帯作りの年間作業時間は、1人1ha当たり約9.5時間にすぎず(表2)、人力刈り払い・搬出による防火帯切り作業(同じく約130時間)よりも省力的で、また、作業が一時期に集中することもない。
- 放牧を導入した場合のha当たり経費は約42,000円で、従来の人力刈り払い・搬出に比べてコストは大幅に節減される(表3)。さらに、放牧牛への粗飼料節減効果を考慮すれば、メリットはさらに拡大する。
成果の活用面・留意点
- 環境省の「草原景観維持モデル事業」では、「防火帯切り省力化」の有望な手段として、この電気牧柵と放牧牛による防火帯作りの技術が採用され、平成12年(2000年)から、阿蘇地方で普及、拡大に向けての現地実証が行われている。また、カルスト台地の山口県秋吉台においても、平成13年(2001年)から当技術が現地に適用されている。
- 人手不足で火入れによる草地管理が難しい牧野組合、市町村で活用できる。また、牛は登坂能力に優れるので、傾斜度30度までは放牧による防火帯作りが可能である。
- 給水場の確保が不可欠で、供試牛は放牧経験の豊かな高齢繁殖牛が向いている。個人農家の牛を供用する場合は、共済制度や放牧報酬(放牧手当)についても考慮する。火入れは適期に実施する。
具体的データ
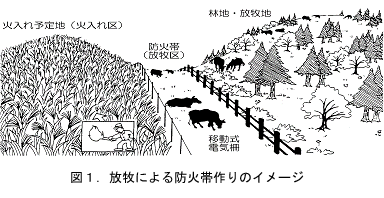
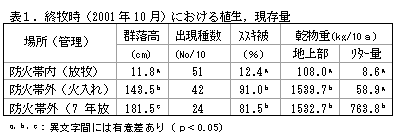
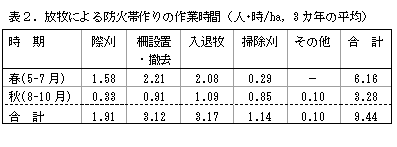
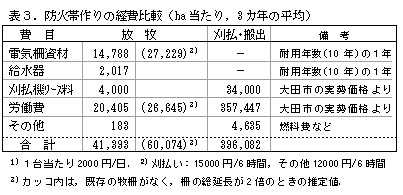
その他
- 研究課題名:短草型草地の植生遷移と生産力(草地動態)
- 予算区分:交付金
- 研究期間:1992~2001年度
- 研究担当者:高橋佳孝、内藤和明(現姫路工大)、周 進(現旭川教育大)、井出保行、佐藤節郎
- 発表論文等:1)Takahashi (2001) Natural Environment Management and Applied System Analysis: 277-293.
2)高橋ら(2002)畜産の研究56(1):33-37、56(2):269-275.
