技術導入等を契機とした傾斜棚田地域の集落活性化
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
傾斜棚田地域では、稲作の継続に加えて、野菜・花きなど集約作目の担い手組織、山羊利用による放棄地の省力的管理体制など、技術導入等を契機とした担い手組織の重層的育成による営農システム再編が集落活性化に有効である。
- キーワード:技術導入、傾斜棚田地域、営農システム再編、集落活性化
- 担当:近中四農研・総合研究部・園芸経営研究室
- 連絡先:0887-63-8117
- 区分:近畿中国四国農業・農業経営
- 分類:行政・参考
背景・ねらい
傾斜棚田地域の集落活性化を図るため、営農面では、稲作継続、園芸作導入、放棄地管理など重層的な営農システムの再編が必要である。本情報では技術導入等を契機とした担い手組織の育成と営農システム再編による活性化効果を、高知県T町N集落を事例に示す。
成果の内容・特徴
- 傾斜棚田地域における集落活性化のために必要な営農面の機能は、A機能:稲作の維持継続、B機能:農業収入の底上げ、C機能:耕作放棄地の管理、の3つである。集落の活性化のためにはA機能の充実とともに、B、C機能を発揮させるために新たな技術開発とその担い手の育成を図る必要がある。N集落ではA機能を担う組織は存在したが、新たにB、C機能の充実強化が必要であった(表1)。
- 各世帯の農業収入の底上げ(B機能)を担う園芸作の導入においては,意欲や栽培技術のレベルに応じて多様な担い手が必要である。N集落では,傾斜ハウスや新作目導入など新たな技術導入等により、・これを契機に畜産から園芸作への経営転換を図った農家(3戸)、・レタス部会やN野菜研究会に参加するなど園芸作の規模や品目を拡大し、追加的な収入増加を図る農家(14戸)、・湧水育苗施設を利用した花苗や山野草栽培などに取り組む各世帯の高齢者(16名)などが生まれた(表1)。
- B機能の重視につれて稲作からの転換が進行し、A機能の能力を上回って発生する放棄地に対して省力的な管理手法が求められる(C機能)。N集落では、山羊による雑草管理法の確立を経て、現地で取り組まれ、01年には現地の担い手により山羊バンクが設立されている(表1)。
- 以上の結果、N集落では97年の稲作中心の営農体制に対して、01年には園芸作の多様な担い手の形成が進んだ(表2)。この経済的効果として、園芸作導入によるN集落における所得増大効果を97年と01年で比較すると、園芸品目の栽培面積で107a(約74%)、販売額(推計)で1,090万円(約74%)増加し、園芸作に関係する1戸平均では約52.7万円(57%)の販売額増加が試算される(表3)。これら経済的効果のほか、花苗栽培の共同栽培が高齢者に与える充実感、園芸品目販売によるマーケティング意識の芽生え、などの効果もある。
成果の活用面・留意点
- 苗生産の組織的取り組みや山羊利用による放棄地の雑草管理は推進体制が整った段階である。今後、栽培技術や販売ノウハウの蓄積により一層の収益向上が見込まれる。
具体的データ
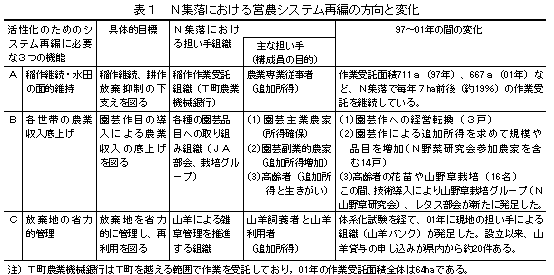
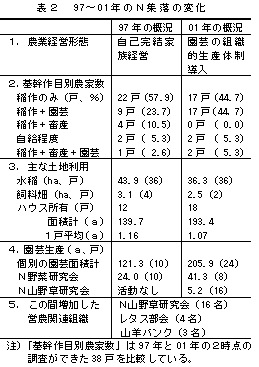
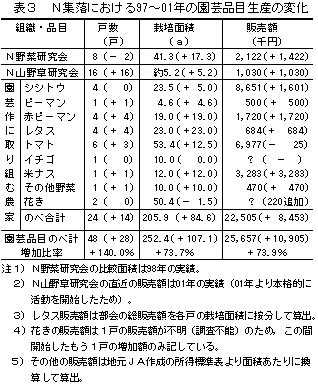
その他
- 研究課題名:地域資源の活用による新たな地域営農システムの策定
- 予算区分:傾斜地野菜・花き
- 研究期間:1999~2001年度
- 研究担当者:迫田登稔、関野幸二、島義史、野中瑞生、的場和弘、川嶋浩樹、長崎裕司
