急勾配水路の底部分水流れにおける分流量の評価方法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
急勾配開水路の水路底に設けた開口部より分流する流れにおける分流量を、水路勾配、水路流量や、開口部の大きさおよび形状等から評価できる。
- キーワード:開水路、急勾配水路、底部分水、水理、水利施設
- 担当:近中四農研・傾斜地基盤部・地域防災研究室
- 連絡先:電話0877(63)8120、電子メール shima@affrc.go.jp
- 区分:近畿中国四国農業・生産環境(土壌・土木・気象)
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
傾斜地農地における射流の生ずる急勾配水路で分水を行う場合、水路底に開口部を設ける底部取水方式の分水工を用いれば減勢 は不要となる。また、この方式の分水工は、水路流量の変動に対して安定した分流量が一般に期待できることが明らかにされており、安全性、経済性および利便 性において有利である。底部取水方式の分水工で生ずる底部分水流れの分流量の決定においては、開口部形状や、開口部下端に現れるよどみ点の位置の重要性が 指摘されている(図1参照)。そこで、底部分水方式の分水工の合理的かつ効率的な設計に資するため、開口部形状、よどみ点位置および分流量の関係を明らかにする。なお、取り扱いを簡単にするため、鉛直2次元の流れとして取り扱う。
成果の内容・特徴
- 底部分水流れにおいて、図2に例を示すように開口部形状等により定まる分流比(水路流量/分流量)をある値に定めようとするとき、以下に示す手順により開口部形状を決定することができる。
- 実験で求めた関係式を用いて、開口部上流での流速と水深(これらの関係は水路勾配と流量から定まる)、および開口幅から、分流比に対応するよどみ点の位置を求めることができる。この関係式は、下流端角度および上下流高低差をパラメータとして含まない。
- ポテンシャル流解析の結果に実験による補正を加えて求めた、下流端角度および上下流高低差をパラメータとして含む関係式を用いて、2.で求めたよどみ点位置を実現するための、開口部下流端角度および開口部の上下流高低差を求めることができる。
- 実験により明らかにした、Vd/Vo (Vd :開口部垂直方向の断面平均流速、Vo :開口部上流での水路断面平均流速)が流速や開口幅にほとんど依存しないことを用いると、水路勾配、下流端角度、および上下流高低差が一定との条件下では、流量や開口幅の変化に伴う分流比の変化を計算する際、比較的煩雑なVd/Vo の計算が1回で済み、全体の計算が簡略化できる。
- 簡略化した計算方法により求めた分流比と実測値は良く一致する(図3)。
成果の活用面・留意点
- 本成果は、急勾配水路で用いる底部分水方式の分水工の設計・管理に活用できる。
- 本成果では、鉛直2次元の流れを前提としているため、実際の設計に活用する際は、水平方向の影響を考慮する必要がある。
具体的データ
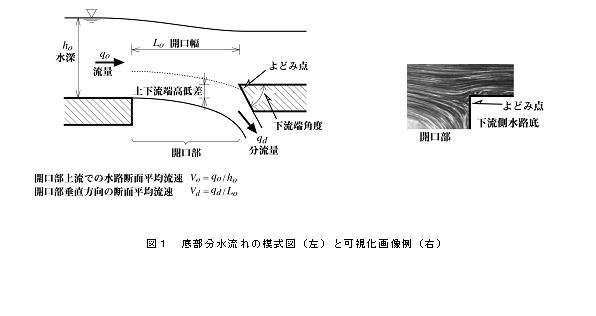
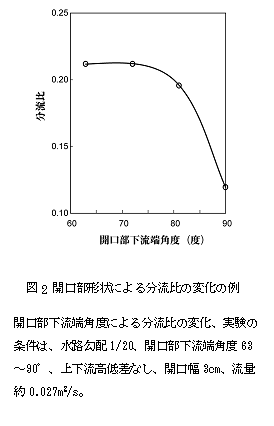
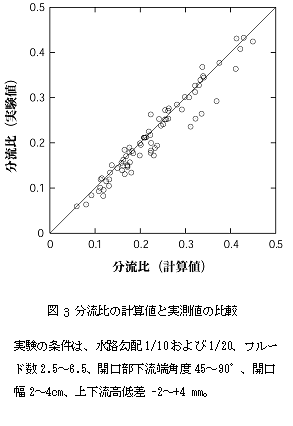
その他
- 研究課題名:傾斜地農地の水利施設に適した画像解析を用いた水理解析手法の開発
- 課題ID:06-02-02-*-04-03
- 予算区分:運営費交付金
- 研究期間:2001~2003年度
- 研究担当者:島崎昌彦、川本治、吉村亜希子、吉迫宏
- 発表論文等:島崎・川本(2003)水工学論文集 47:793-798
