飼料用稲生産の専用収穫機利用にかかわる連携効果と収支改善策
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
収穫・調製機械利用を通じた集落営農連携は初期投資の負担軽減と固定費の共同負担により、31%の費用節減効果を生む。連携を構築する中で技術対策(高収量・省力化)、実需者対策(高単価)を併用することで飼料用稲生産が収益部門として成立する。
- キーワード:専用収穫機利用、集落営農連携、飼料用稲生産、収支改善策
- 担当:近中四農研・総合研究部・経営管理研究室
- 連絡先:電話084-923-4100、電子メールmtanada@affrc.go.jp
- 区分:近畿中国四国農業・農業経営
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
中国中山間地では、大豆等畑作物の生産性が上がらない集落営農組織において転作作物として飼料用稲に期待が寄せられている。しかし集落規模が小さい場合、高額な専用収穫機の利用において、単独組織では稼働面積が確保できず非効率な状況が生まれる。また、転作助成金が大幅に減額される実状にあることから、飼料用稲の採算性の向上策が求められる。そこで、集落営農間での作業受委託による専用収穫機(調整機等含む一式)の連携利用の効果を明らかにするとともに、飼料用稲生産の収支改善策について検討する。
成果の内容・特徴
- 集落営農組織が栽培管理から収穫・調製、運搬まで一貫して実施する飼料用稲生産において、専用収穫機(一式)の連携利用の経済的効果は、その稼働面積を確保すること等により補助事業が活用でき、初期投資の負担が軽減され、また、収穫・調製過程の固定費を複数組織で共同負担することで生まれる。こうした連携効果は、組織内・組織間で行われる作業受委託の料金水準に反映する(図1)。なお、委託側との共同作業により作業受託を実施する場合、また、組織間での収量や作業時間の差により変動費の格差が無視できない場合、それらを考慮して作業料金を調整することが連携の条件になる。
- 連携事例の実態に基づく試算によると、補助事業を活用しない7haの単独利用と比べ、連携利用の12haでは減価償却費の圧縮処理が伴い飼料用稲生産の費用は31%節減される。しかし、転作助成金が4.4万円/10aに減額されたため、構成員農家(Y営農組合)の所得は極めて低位となる。また、地代・労賃を構成員に分配する集落営農組織(I法人)では飼料用稲生産部門は赤字になり、地代支払いが困難になる(表1)。
- 収支改善策として、新たな連携構築による稼働面積のさらなる拡大(組織的対策)、収量向上及び直播栽培による省力化(技術対策)を図り、また、飼料用稲WCS販売価格を引き上げるような実需者対策を講じるものとし、それらの効果を試算した(図2)。その結果、i)それぞれの対策を独立して実施しても赤字解消・収支改善にはつながらないため(図中の*)、黒字転換には複数の対策の併用が必要になること、ii)技術対策の有効性は省力化と増収を同時に実現することで発揮されること(同**)、iii)収量が現行水準にとどまれば直播導入と組織的対策による生産費用の削減では十分な改善が見込めず、実需者対策を組み合わせることが不可欠になること(同***)、iv)4つの全ての対策を併せて講じることで収益(余剰)は転作助成金の75%の水準に達し(同****)、財政的支援に対する依存度を大幅に低下し得ることが示される。
成果の活用面・留意点
- 専用収穫機の連携利用を含めた収支改善の方策・方向を示すものとして活用できる。
- 広島県中山間地の事例に基づく試算である。なお収量向上の場合、肥料費等変動費の増加が無いものと仮定しており、その効果はやや大きく推計されている。
- 実需者対策とは畜産農家の要望を満たす飼料用稲WCSの提供を通し、製品に対する正当な評価を得て、販売価格についての合意を図るような対応を指す。
具体的データ
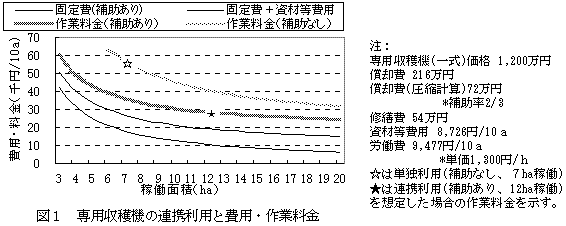
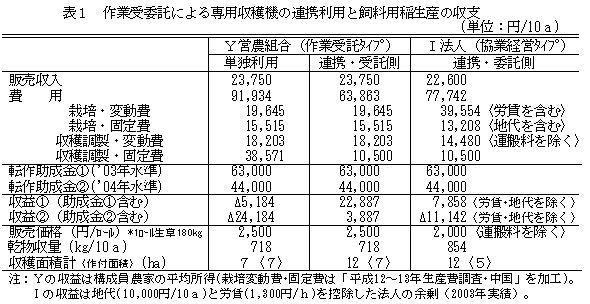
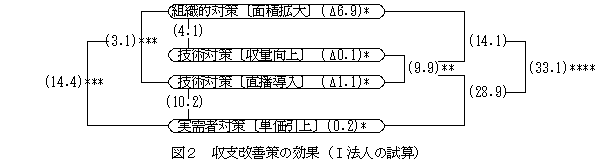
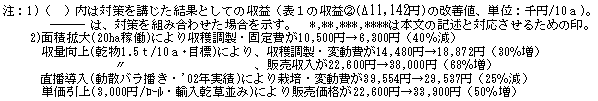
その他
- 研究課題名:飼料用稲生産・利用の経済性の解明
- 課題ID:06-01-03-*-07-04
- 予算区分:中山間耕畜連携
- 研究期間:2003~2005年度
- 研究担当者:棚田光雄、堀江達哉、井上憲一、恒川磯雄
