大豆「サチユタカ」の莢先熟の発生は莢伸長始期∼粒肥大始期の土壌乾燥により増大する
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
大豆品種「サチユタカ」は、莢伸長始期∼粒肥大始期に土壌が乾燥すると莢先熟の程度が高まり、期間中の平均pF値が2.5以上では茎が緑色を呈する莢先熟となる。この期間の土壌乾燥によって稔実莢数や総粒数などが減少するほど莢先熟の程度が高まる。
- キーワード:ダイズ、莢先熟、青立ち、莢伸長始期、粒肥大始期、土壌乾燥、サチユタカ
- 担当:近中四農研・作物開発部・栽培生理研究室
- 連絡先:電話084-923-4100、電子メールwenarc-seika@naro.affrc.go.jp
- 区分:近畿中国四国農業・作物生産(夏作)、作物・夏畑作物
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
大豆に莢先熟が発生するとコンバイン収穫の際に汚損粒が発生して外観品質が低下する。莢先熟発生の原因の一つとして開花期以降の土 壌乾燥があげられており、灌水管理によってその発生が軽減されることが知られている。しかし、開花期以降のどの時期の土壌乾燥が莢先熟の発生程度を高める のかについての知見はほとんどない。そこで、近中四地域で普及が拡大しつつある大豆品種「サチユタカ」における灌水の効率化と莢先熟防止のために、開花後 の土壌乾燥の時期と乾燥の程度が莢先熟発生に及ぼす影響を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 大豆品種「サチユタカ」は開花期以降では莢伸長始期∼粒肥大始期の土壌乾燥処理によって莢先熟の程度が高まる(図1)。
- 莢伸長始期∼粒肥大始期における地下30cmの平均pF値が2.3以下では莢先熟の程度は1.4∼1.6(茎の色はほとんど緑色が残らない状態)と軽微であるが、平均pF値が2.5以上の乾燥状態では青立ちの程度が2.2∼2.9となり、茎が緑色を呈し葉柄がわずかに残る状態なので、収穫遅延や汚損による外観品質低下の要因となる(図2)。
- 莢伸長始期∼粒肥大始期における土壌乾燥処理中の群落上部の葉温(晴天日13∼14時)は、土壌水分が76.6kPa(pF値2.9)までは気温よりも低いが、さらにpF値が高まると葉温は急激に上昇し、土壌乾燥による水ストレスが顕著となる(図3)。
- 莢伸長始期∼粒肥大始期の土壌乾燥処理によって発生する莢先熟の程度は、粒茎比が低いほど、そして稔実莢数や総粒数が無処理株と比較して少ない株ほど高まる。
- このように莢伸長始期∼粒肥大始期に土壌が過度に乾燥すると、稔実莢数や総粒数が減少して莢先熟の程度が高まり、収量も低下するので、灌水等により土壌水分がpF値2.5以上とならないようにする必要がある。
成果の活用面・留意点
- 本成果は、近畿中国四国農業研究センター内のライシメーター(灰色低地土)を使用した地下水位制御による試験結果であり、地下灌漑施設を使用した栽培技術への応用が期待できる。
- pF値はテンシオメーター(約1万円)で測定できる。
- 群落の葉温は、熱画像解析装置(NEC社 TH9100)により群落上部の熱画像を取得して算出した値である。
- 本成果は、開花期以降に渇水となった場合に灌水時期を判断する際の参考となる。
具体的データ
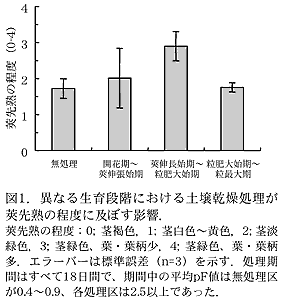
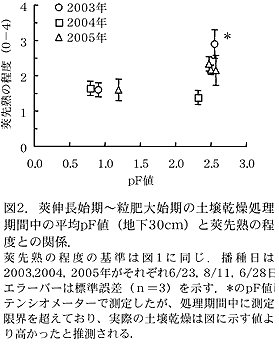
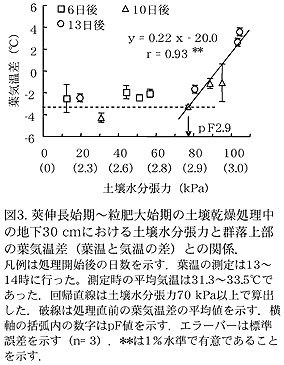

その他
- 研究課題名:リモートセンシングによる乾湿害の発生状況と生育ムラの調査技術の開発-土壌乾燥が青立ち発生に及ぼす影響の解明-
- 課題ID:06-03-06-01-02-05
- 予算区分:ブラニチ2系
- 研究期間:2003∼2005年度
- 研究担当者:竹田博之、大平陽一、佐々木良治
