人為選抜によるナミテントウ飛翔不能系統の作出
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
飛翔測定装置フライトミルを用いて飛翔能力の低いナミテントウ成虫を約20世代にわたり選抜することで飛翔不能の系統を作出できる。
- キーワード:ナミテントウ、飛翔不能化、人為選抜
- 担当:近中四農研・地域基盤研究部・虫害研究室
- 連絡先:電話084-923-4100、電子メールwenarc-seika@naro.affrc.go.jp
- 区分:近畿中国四国農業・生産環境(病害虫)、共通基盤・病害虫(虫害)
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
ナミテントウの成虫はアブラムシの捕食性天敵としての利用が期待されているが、飛翔分散能力が高いためにビニールハウス内での定着 率が低いという問題がある。物理的に飛翔不能化されたナミテントウが国内で販売されているが、成虫になるまで飼育する必要があるためコストが高い。一方、 遺伝的に飛翔不能化された系統であれば、成虫、幼虫および卵塊のいずれの段階でも利用可能なため最適放飼技術の開発により低コスト化が期待される。そこで 遺伝的に飛翔不能な系統を確立する。
成果の内容・特徴
- 飛翔測定装置フライトミルを用いてナミテントウ成虫の飛翔距離を雌雄50頭ずつ測定し、その中で飛翔距離の短い個体を30%選抜し、次世代を得るという操作を約20世代行うと、成虫の飛翔距離は世代を経過するにつれて低下する(図1)。
- 20世代めでは、ガラス温室の中央に立てた高さ60cmの棒の頂上からおよそ70%の成虫が飛翔できない(図2)。
- 20世代め成虫のアブラムシ捕食数は非選抜の対照系統に劣らない(図3)。卵の孵化率は対照系統の方が高いが、成虫体サイズ(蛹重)、産卵数に違いは見られない(表1)。
成果の活用面・留意点
- 飛翔不能化した成虫のビニールハウス内における定着率及びアブラムシの防除効果を検証する必要がある。
- 飛翔不能系統における、長期間の選抜による近親交配等の影響および選抜を中止した場合の飛翔能力回復の可能性を検証する必要がある。
具体的データ
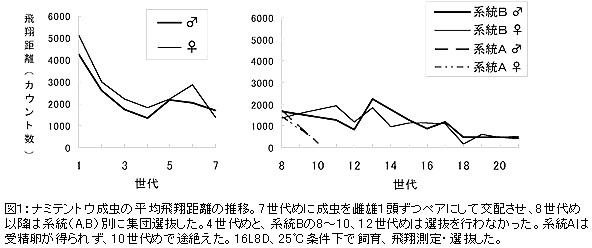
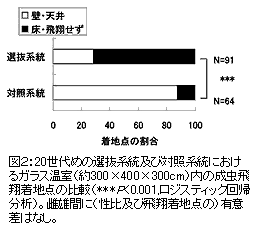
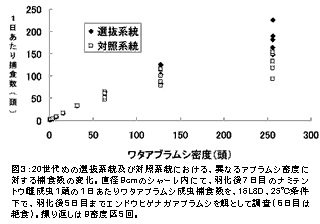
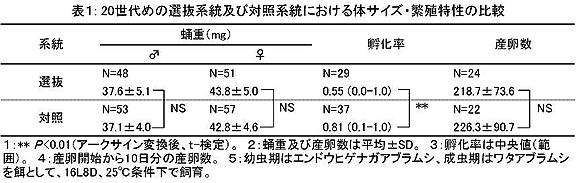
その他
- 研究課題名:ナミテントウの飛翔不能系統の確立と生物的防除における有効性の評価
- 課題ID:06-08-02-*-12-05
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2003∼2005年度
- 研究担当者:世古智一、三浦一芸、大泰司誠、菊地淳志
