堆肥供給組織による運搬・散布サービスの所要労働時間の推定方法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
堆肥供給組織による運搬・散布サービスの所要労働時間は、散布圃場の平均面積、出役時間、圃場の位置・分散、組織設立年数、作業期の初日・最終日、水稲作付予定圃場の有無、単位面積当たり堆肥散布量、からなる決定式で推定できる。
- キーワード:家畜ふん尿、堆肥供給組織、運搬・散布サービス、所要労働時間、推定方法
- 担当:近中四農研・中山間耕畜連携・水田輪作研究チーム
- 連絡先:電話084-923-4735、電子メールwenarc-seika@naro.affrc.go.jp
- 区分:近畿中国四国農業・営農、共通基盤・経営
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
中国四国地域の水田地帯では、堆肥供給組織(以下、組織)が各地で設立され、組作業による運搬・散布サービス(以下、サービス)の提供が進みつつある。組織によるサービスの持続的提供では、作業計画の精緻化によって単位面積当たり労働費を節減する一方、単位面積当たり労働費の試算値を作業料金に反映させることが重要となる。そのためにはまず、単位面積当たりの出役時間の総和(以下、所要労働時間)を、各種作業条件に応じて予測する必要がある。しかし、サービスの組作業の場合、性質の異なる複数の作業が同時に進行するため、所要労働時間の構造式の導出は困難である。そこで、広島県内の先進事例における7年間(1998~2004年)の記帳データをもとに、サービスの所要労働時間の推定方法を提示する。
成果の内容・特徴
- 記帳データによる作業日ごとの組作業能率(a/人・h)の推定では、候補説明変数のうち、(イ)散布圃場の平均面積、(ロ)各作業者の最大出役時間、(ハ)堆肥センターから圃場までの距離と圃場分散(図1)、(ニ)組織設立年数、(ホ)作業期の初日・最終日、(ヘ)水稲作付予定圃場の有無、(ト)単位面積当たり堆肥散布量、が有意な変数として残る。そこで、作業日ごとの所要労働時間Y (人・h/10a)の決定式は、これらの変数で表せると考える(表1)。
- 本推定方法では、まず、記帳データを用いて(1)式を重回帰分析することにより、作業条件が所要労働時間Yに与える影響を推定する。(ハ)をあらわす通作距離Dと圃場分散度Sの算出には、あらかじめGISソフトなどで地理座標を求める必要がある。10a当たり堆肥散布量は、2.6m3(約1.3t)、5.2m3(約2.6t)の2水準とし、それぞれ、2tダンプトラック積載1台分、2台分に相当する。先進事例の組作業は、(i)積み込み(1人、ショベルローダ)、(ii)運搬(1~3人、2tダンプトラック)、(iii)積み替え・誘導(1人、キャリアブリッジ・牽引用トラクタ)、(iv)散布(1人、自走式マニュアスプレッダ)からなる。
- 先進事例の作業日単位の127サンプル(平均1.30人・h/10a、標準偏差0.50)で(1)式を推定すると、パラメータの符号が、定性的な事実と矛盾しない表2の(2)式が得られる。
- 得られた推定式に、作業計画にもとづく各種作業条件を代入することで、作業日ごとの所要労働時間の推定値Yが試算できる。妥当性を確認するため、先進事例の127サンプルで推定値Yを求めると、全体の6割が観測値に対して±15%の範囲内に収まる。本推定方法の現場での使用例は、通作距離Dのみ変化させた場合の推定値Yを事例の実態に則して試算し(図2)、その結果を単位面積当たり作業料金に反映させることが考えられる。
成果の活用面・留意点
- 普及指導員や営農指導員の立場で、サービスの所要労働時間を作業条件別に試算する際に、参考の情報として活用できる。
- (1)式の主な対象は、水田地帯で(i)~(iv)の組作業体系を採用する組織である。
- 設立1年目の組織を対象とする場合は、パラメータの推定に用いる記帳データがないため、類似の事例の記帳データで代用するか、計画値を用いて推定する。
- 組作業能率の規定要因(イ)~(ト)の詳細については、[その他]の発表論文を参照のこと。
具体的データ
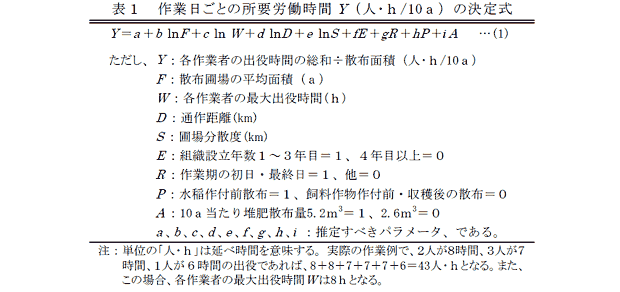
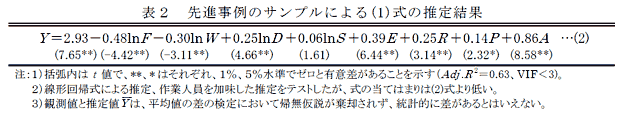
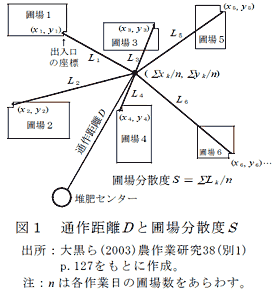
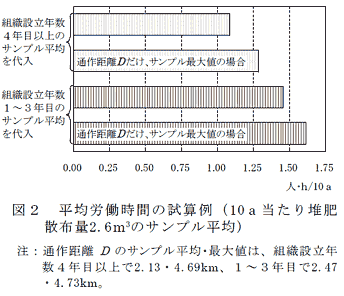
その他
- 研究課題名:近畿・中国・四国地域における中小規模水田利用システムの開発
- 課題ID:411-c
- 予算区分:基盤
- 研究期間:2005~2006年度
- 研究担当者:井上憲一、高橋英博
- 発表論文等:1)井上・高橋(2005)農業経営研究 43(1):104-107.
2)井上・高橋(2005)農業経営通信 226:22-25.
